
物流ライター。青山女史短期大学を卒業後、物流会社に14年間勤務。現場管理を伴う、事務職に従事する。その後、2022年にフリーライターとして独立し、物流やECにまつわるメディアで発信。わかりやすく「おもしろい物流」を伝える。

BOPIS(ボピス)とは、店舗受け取りサービスを意味するマーケティング用語です。コロナ禍での生活の変化により、ますますニーズの多様化が進む小売業やEC事業では理解が必須ともいえます。
本稿ではBOPISのメリット・デメリット・導入手順・事例・導入の課題を解説します。
BOPIS(ボピス)とは
BOPISは日本語でボピスと読みます。まずは基本概念を理解しましょう。
BOPISの意味 |「クリック・アンド・コレクト」との違い
「BOPIS(ボピス)」とは「Buy Online Pick-up In Store(バイ・オンライン・ピックアップ・インストア)」の頭文字をとった言葉です。つまりオンラインで購入し、店舗で受け取る仕組みを意味します。
類似する言葉である「Click & Collect(クリック・アンド・コレクト)」は、オンラインで購入し、自宅以外の場所で受け取る仕組みです。店舗受け取りも含まれますが、宅配ロッカーの活用やコンビニ受け取りも該当するため、厳密な意味としては異なります。
BOPISが注目される背景
BOPISの注目が高まる背景には「コロナ禍での密集リスクの回避」がきっかけとして挙げられます。
コロナ禍では人手が多く集まる店舗での滞在時間を削減したいと感じる人が増えました。とはいえ、「宅配を待つ暇がない」「送料は負担したくない」「受け取りを急いでいる」などのニーズも無視できません。
これらの課題を打開するために注目されたのがBOPISです。顧客が時間と場所に縛られることなく買い物を楽しめる取り組みは現代のライフスタイルに合致し、OMOやオムニチャネル施策の一環として始める企業が増えています。
BOPISの市場規模
世界におけるBOPISの市場規模は2021年時点で2,438億9,000万米ドルと小さい数字ではありません。
日本国内ではなかなか浸透が進まなかったBOPISですが、小売業を牽引する「ウォルマート」を筆頭に欧米では定着しています。2017年、米国で11.6%であったEC化率は、翌2018年には14.3%までに向上しました。オムニチャネル化を進めるうえでBOPISに着手した影響といわれています。対する日本のEC化率は2021時点においても8.78%にとどまっており、今後BOPISを始める企業がさらに増えることによるEC化率の向上が期待されています。
市場調査レポートBOPISの世界市場:予測(2022年~2027年)、業界動向、成長、洞察、COVID-19の影響、企業の機会分析によると、2027年にBOPISの世界における市場規模は7,031億8,000万米ドルに達すると見込まれており、今後も市場は拡大すると予測できます。
BOPISのメリット【顧客視点】

一見、「自宅で受け取る方が楽では?」とも感じるかもしれませんが、顧客ニーズがあるのには以下の理由があります。
- 好きな時間に商品を受け取れる
- 送料の負担がない
- 返品がしやすい
- 商品を探し回る時間とレジ待ち時間を短縮できる
- あらかじめ在庫を確保できる
①好きな時間に商品を受け取れる
日中のほとんどを外で過ごす人にとって、商品を受け取るために自宅に滞在するのは、小さなストレスを生むこともあります。店舗でゆっくり買い物をする時間はないけれど、好きなタイミングで受け取りをしたい場合にBOPISを選択するケースがあるでしょう。
②送料の負担がない
また送料の負担がないのも顧客にとってのメリットです。「ほしい商品だけ購入しても送料無料ラインに到達しない」「送料の負担がかかる大きな商品を買いたい」などさまざまな観点により、送料の負担が少ない店舗での受け取りを希望します。
③返品がしやすい
店舗で受け取りをすれば、その場での返品も容易です。例えば衣服であれば、「人気商品の在庫を確保したいけれども、来店時に試着してみてサイズが合わなければ返品したい」といったニーズもあるでしょう。
返品・交換の重要性についてこちらの記事でも解説しています。
「返品・交換の物流構築が売上に繋がるワケ!顧客体験向上のメリットを解説」
④商品を探し回る時間とレジ待ち時間を短縮できる
BOPISにより事前に商品を購入すれば、店舗で探し歩く時間とレジ待ちの時間を短縮できます。日々忙しく過ごす顧客にとって、買いたい商品が決まっているケースでは、「買い物時間=タイムロス」と捉えるかもしれません。
当日の夜に使いたい食材や翌日の朝に着用したい服など、急を要しているけれどもゆっくり買い物をする時間がない場合に利便性を感じられることもメリットです。
⑤あらかじめ在庫を確保できる
品薄商品や人気商品がほしい場合に、あらかじめ在庫を確保できるのも消費者がBOPISで享受できるメリットです。店舗まで足を運んだにも関わらず品切れという落胆を防げます。
事前に欠品がわかれば、入荷や他店からの取り寄せを待って、受け取る選択肢も顧客に提供できます。
BOPISのメリット【事業者視点】
事業者視点でBOPISを取り入れるメリットは以下の通りです。
- 物流コストの削減効果がある
- CSの向上が期待できる
- ついで買いを誘発できる
- 直接コミュニケーションが取れる
- データをマーケティングに活用できる
①物流コストの削減効果がある
1つ目のメリットは物流コストの削減です。
BOPISにより宅配が減れば、各納品先への運賃や梱包・発送にかかる費用がカットできます。実店舗に在庫がない場合でも、倉庫から他の商品の補充とあわせて定期便で配送できるため、トータルでみて物流コストは低減します。
②CSの向上が期待できる
2つ目のメリットは、顧客満足度の向上が望めることです。
業界によっては日本でもBOPISの導入が進んでおり、選択肢として当たり前の時代が迫りつつあります。顧客に多くのメリットを提示しなければ、競合他社に淘汰されてしまうといっても過言ではありません。積極的にCSの向上に向き合う必要があるでしょう。
③「ついで買い」を誘発できる
3つ目のメリットは「ついで買い」や「衝動買い」の誘発につながり、売り上げの向上が見込める点です。レジ横の商品を、つい手に取って購入してしまった経験はありませんか?BOPISの施策は顧客単価をアップさせます。
④直接コミュニケーションが取れる
4つ目のメリットは店舗に足を運んでもらう機会につながり、顧客と直接コミュニケーションができる点です。EC需要の高まりから見てもわかるように、買い物をオンラインで済ますニーズが増加しています。ECサイトから店舗へ誘導し、対面接客ができれば、顧客との関係性構築に役立ちます。
⑤データをマーケティングに活用できる
5つ目はデータをマーケティングに活用できる点です。BOPISを導入するためには、オンラインとオフラインの顧客データを紐付ける必要があります。
分断されてしまっていたオフラインのデータを一元管理できれば、より正確に「誰が」「何を」「いつ」「どのくらい購入しているのか」などの情報を捉えられます。レコメンド機能に反映させたり、購入頻度に合わせた対策を施したりと、活用できるデータが増えるのもメリットです。
BOPISのデメリット
導入すればメリットの多いBOPISの取り組みですが、顧客の選択肢を増やすためにはデメリットもあります。
店舗に保有する在庫の増加
店舗に保有する在庫が増え、保管スペースが必要になることはデメリットのひとつです。BOPISで注文を受けた商品は店舗の在庫から用意するか、もしくは倉庫から店舗あてに送り、受け取りまで保管します。
基本的に店舗の在庫から融通するとなれば、BOPIS用の需要を考慮して発注・保管しなければなりません。SKUが多ければ多いほど、その分バックヤードに必要なスペースも広くなります。
店舗スタッフの業務負担が増加
店舗スタッフの業務負担が増えるデメリットもあります。具体的には次のような業務です。
- 商品の受け渡し
- 問い合わせ対応
- 在庫管理
- 受注した商品の準備
アパレルのようなSKUが多い業態は業務が煩雑になりやすく、店舗が大きいほど商品を探してピックアップするために時間を割かなくてはなりません。
店舗業務負担が増えるにも関わらず、売上がECショップ側の評価に反映される仕組みにおいては、店舗スタッフのモチベーション低下も考えられるでしょう。
BOPISを導入するための4STEP

ここでは、BOPISを導入するために必要な手順を紹介します。
STEP1.BOPIS対応のECサイト・モールを準備する
まずは実店舗があるのは前提のうえ、店舗受け取りができるECカートやECモールを準備する必要があります。
ECモールとしては楽天市場やYahooショッピングなどが対応。各種ECカートもBOPISに対応しており、人気のShopifyやBASEも店舗受け取りの設定ができます。
<関連記事>「【ECサイトを初めて構築する方向け】作り方・サービスとその費用を解説」
STEP2.在庫管理を行う
店舗とECの在庫情報を連携するには、まず商品マスタが統一されていなければなりません。どの棚に保管されているか、ロケーション管理を適切に行い、スムーズにピッキング作業ができるようにします。また欠品で顧客をがっかりさせてしまわないよう、数量を正確に管理しましょう。
STEP3.システムの活用で店舗とECのデータを連携する
店舗側のPOSシステムとEC側の情報を同期します。データ上で連携できない場合、ECから店舗へ電話確認などのアナログな対応が必須です。時間と手間がかかり、タイムラグが生まれてしまいます。
在庫情報のリアルタイムな連携と顧客情報を共有できるシステムの活用を推奨します。
STEP4.店舗スタッフへBOPIS対応の教育
システムや在庫管理の環境が整い次第、店舗スタッフに対しBOPIS対応の教育も必須です。システムの使い方や保管・ピッキングのやり方、問い合わせ対応、商品の受け渡しなど滞ることのないよう研修を行いましょう。担当者を選任するのもひとつの手です。
BOPISの導入の課題
BOPIS導入にあたって、在庫管理が課題となります。オンラインからの注文であっても、店舗受け取りを希望する場合は、実店舗の在庫状況を反映させなければなりません。
これまではオンラインとオフラインの一元化を前提とせず開発されたシステムを利用してきた企業も多いでしょう。リアルタイムの在庫反映が困難であったり、倉庫から在庫が引き当てされるばかりに在庫の用意にリードタイムを要してしまったりと課題が発生してしまうケースもあります。
システム改修費用を見込んでの運用開始がおすすめです。
<関連記事>「オムニチャネルの在庫管理にシステム活用が重要な理由!リアルタイム反映と見える化」
日本企業におけるBOPISのの導入事例

次にBOPISの成功事例を確認していきましょう。
ヨドバシカメラ
ヨドバシカメラのヨドバシ・ドット・コムはサービスレベルの高いBOPIS導入例といえます。注文した商品は在庫があれば最短30分で、指定したヨドバシカメラ、石井スポーツ、アートスポーツの店舗受け取りが可能です。一部店舗では24時間受け取り可能な窓口が用意されています。他店からの取り寄せも可能なため、新商品や品薄商品をいち早く手に入れたいといった要望に対応できるでしょう。
イオン
イオンでも多くの店舗でBOPISを展開しています。カウンター渡し、ロッカー渡し、ドライブスルー形式、と3種類の受け取り方が選べます。商品の提供時間は店舗によってまちまちですが、例えばイオン葛西店であれば当日9時までの注文で、当日12〜14時までの受け取りができるといったようにリードタイムは短く設定されています。もちろん手数料・送料は無料。忙しく働く人や小さい子連れの母親に重宝されている事例です。
ワークマン
ワークマンも国内BOPISの成功事例です。オンライン注文で自宅への配送は購入額が1万円以上でなければ送料が発生してしまいます。この負担を嫌う購入者によって積極的に活用されてきました。BOPISに勝機を見出したワークマンは、2022年から5年以内にECでの宅配を全廃し、オンラインからの購入は店舗受け取りのみに絞ると発表しています。
注文から最短3時間、出勤前の朝7時から夜8時まで受け取り可能。逼迫して「今すぐ欲しい」という需要の少ないワークマンの製品だからこそ、BOPISがマッチしたともいえるでしょう。
海外企業におけるBOPISの導入事例|ウォルマート
小売最大手のウォルマートは2016年ごろにBOPISを開始。2022年時点で3,700店舗以上が対応しています。
注文を受けた商品は、「ピックアップタワー」と呼ばれる大型ロッカーから受け取りができるほか、駐車場で車に乗ったまま商品を受け取れる「カーブサイド・ピックアップ」、カウンター渡しの選択が可能です。いち早くBOPISに取り組み、世界にその施策を認知させた事例といえます。
BOPISの取り組みを検討しよう
BOPISは顧客のニーズを捉えており、また事業者にとっては、オムニチャネルを成功させるうえでも必須な仕組みといえます。EC需要が高まる時代において、実店舗へ集客する仕組みが必要です。
導入には在庫管理の課題がありますが、すでに向き合わざるをえないフェーズにきているといっても過言ではありません。富士ロジテックでは、BOPIS・オムニチャネル対応が可能なフルフィルメントサービスを展開しています。
さまざまなシステムとのAPI連携も実装しているため、業務効率化を安心してお任せいただけます。BOPISの導入について質問・相談・見積もりを承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
田中なお
物流ライター。青山女史短期大学を卒業後、物流会社に14年間勤務。現場管理を伴う、事務職に従事する。その後、2022年にフリーライターとして独立し、物流やECにまつわるメディアで発信。わかりやすく「おもしろい物流」を伝える。
タグ一覧
カテゴリー



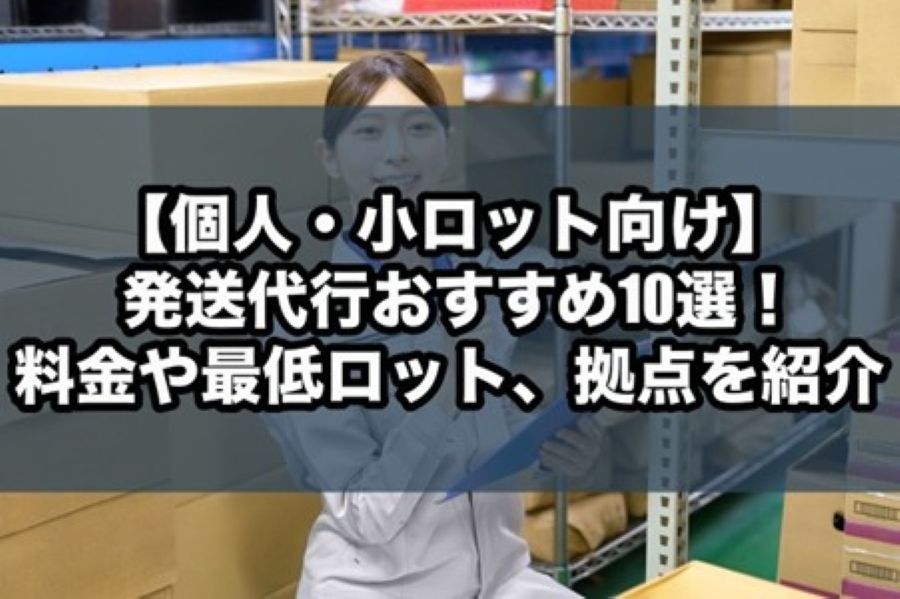
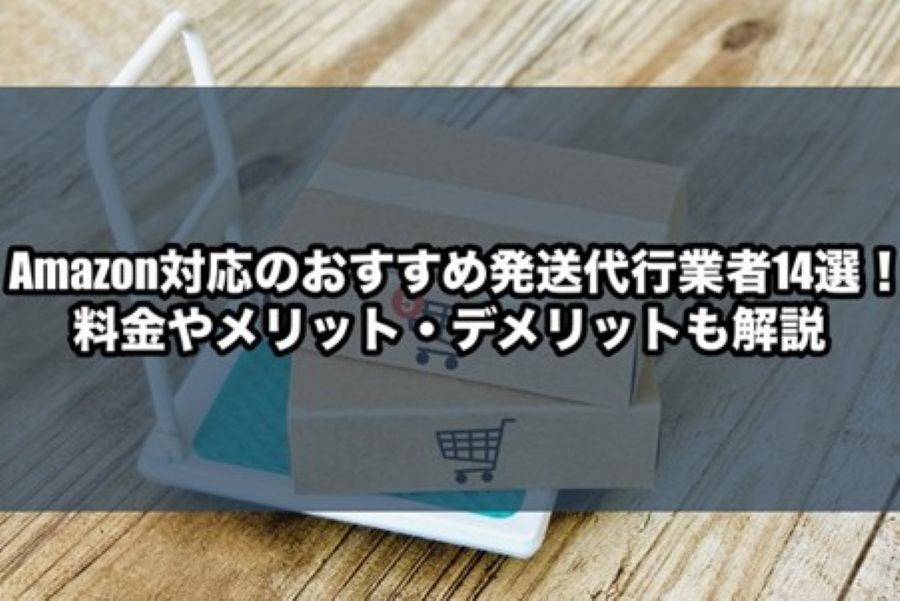
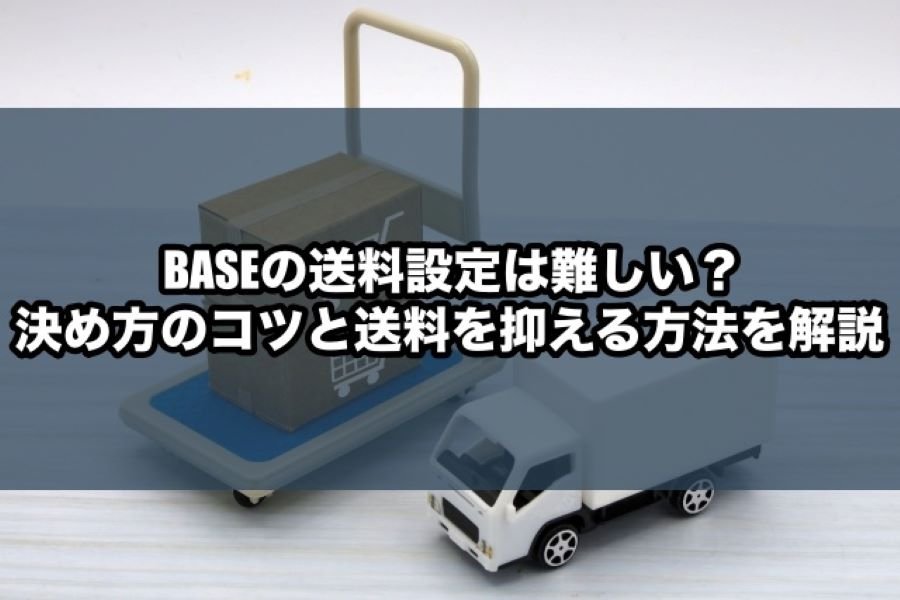
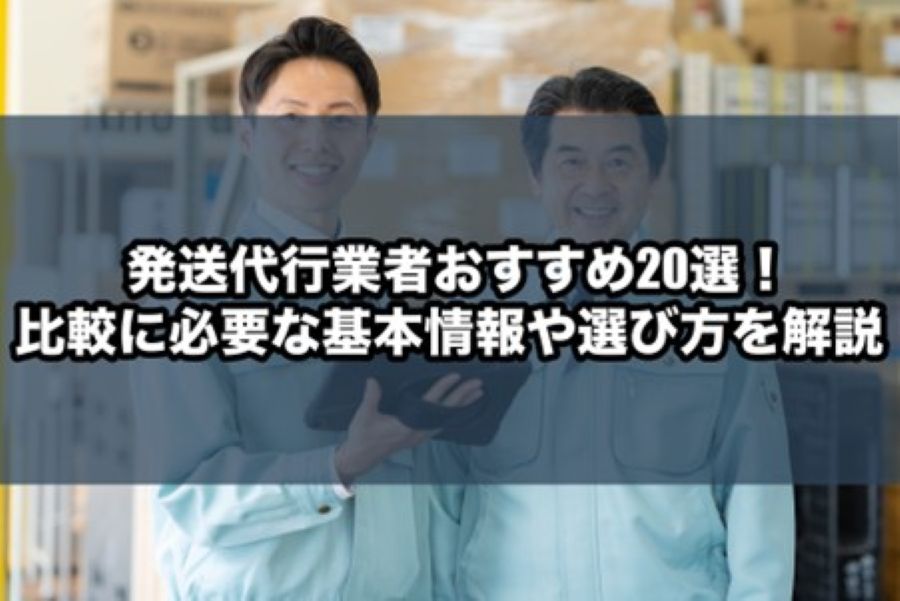


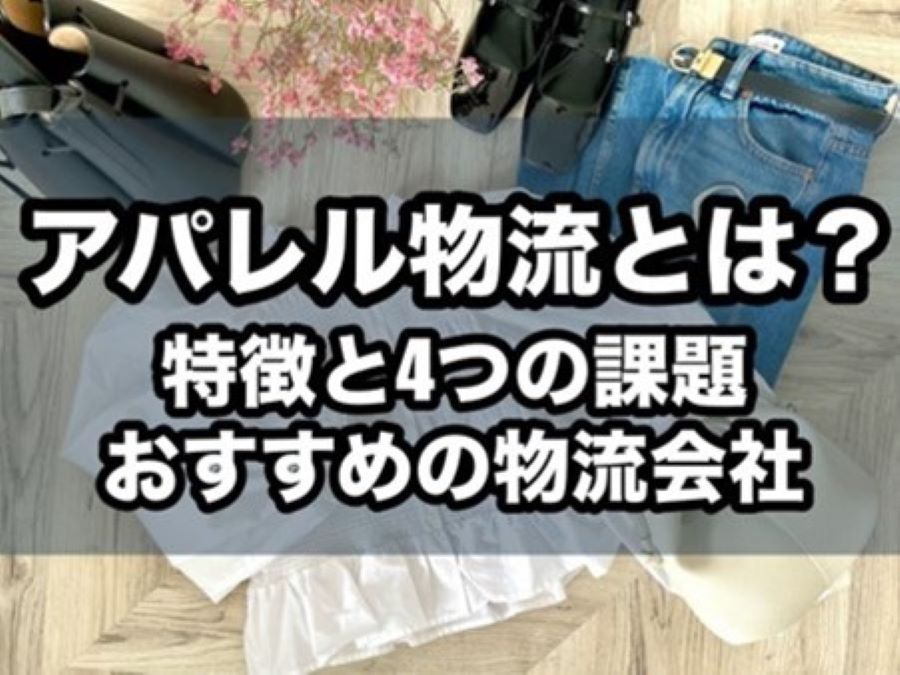







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)