
国内外のECをはじめ、リユース、美容・健康、音楽などあらゆるジャンルで執筆中のフリーランスライター。中国への留学経験を生かし、13年間、繊維製品や楽器、雑貨の輸入業務に携わる。現在はライター業のかたわら、個人で越境ECのセラーとしても活動中。

クラウドファンディングは、インターネット上で多数の人から出資を募る資金調達の方法です。
比較的新しい手法で明確な定義はないため、寄付との違いなどわかりにくい点も多いかと思います。そこで本記事では、クラウドファンディングの仕組みと種類、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
クラウドファンディングとは?|意味
クラウドファンディングということばは、クラウド(群衆)ファンディング(資金調達)を合わせた和製英語です。まずは簡単に仕組みからご説明します。
- クラウドファンディングの仕組み
- クラウドファンディングの目的
クラウドファンディングの仕組み
クラウドファンディングとは、プロジェクトを立ち上げた個人や法人が、不特定多数の人からインターネットを通じて資金を調達する仕組みです。
まず起案者は、新しいアイデアや取り組みたい活動をクラウドファンディングの運営企業に申請します。
審査に合格したプロジェクトはインターネット上で公開され、賛同した不特定多数の人が出資者となり、資金を提供するという流れです。
クラウドファンディングを運営するおもなサイトには、MakuakeやCAMPFIRE、BOOSTERなどがあります。
クラウドファンディングの目的
起案者はクラウドファンディングで得た資金を使い、プロジェクトを実現するのが目的です。
資金調達のほかに、商品やサービスのPRや新商品に対する消費者の反応を見るテストマーケティングの目的にも利用されます。
クラウドファンディング6種類とおすすめのサイト

クラウドファンディングというと、新商品に対して支援する「購入型」や、社会貢献に利用される「寄付型」をイメージする方が多いと思います。
ほかにもいくつか代表的な型があるので、ここでは代表的な以下6つについて見ていきましょう。
- 購入型クラウドファンディング
- 寄付型クラウドファンディング
- 事業投資型クラウドファンディング
- 不動産型クラウドファンディング
- 株式型クラウドファンディング
- 貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
|
|
プロジェクトの成立 |
リターン(返礼品) |
返金 |
|
All-or-Nothing方式 |
目標金額に達した場合のみ |
プロジェクトが成立した場合のみ |
プロジェクト不成立で全額返金 |
|
All-in方式 |
目標金額に達しなくても進行する |
目標金額に達しなくても必ずリターンが必要 |
なし |
1.購入型クラウドファンディング
購入型は支援者が商品やサービスを購入し、プロジェクトを応援するクラウドファンディングで、日本では主流の型です。
たとえばアーティストの作品を購入して活動を支えたり、地方の特産物を購入して地場産業を支援したりできます。
ネットショッピングをするように気軽に参加でき、まだ世にでていない新しい商品をいち早く購入できるのも魅力の一つ。
購入型には、以下の表のようにAll-or-Nothing方式とAll-in方式という2種類の方式があります。
おすすめのサイトには、MakuakeやGREEN FUNDING、Readyforなどがあります。
リターン(返礼品)について詳しく知りたい方は「クラウドファンディング リターン」の記事で詳しく解説しています。
2.寄付型クラウドファンディング
寄付型は、支援者がリターンを求めないクラウドファンディングの型です。お礼として手紙、写真を受け取ることもあります。寄付型にもAll-or-Nothing方式とAll-in方式があり、サイトによって取り扱いが異なります。
たとえば、発展途上国や被災地に対する寄付など社会的貢献度の高いものに多い型です。
最近の事例では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止活動で、医療機関や生活困窮者への支援に7億3,000万円ほどの寄付金が集まりました。
インターネットで資金の使途やプロジェクトの進ちょく状況を報告する必要があり、支援の透明性が確保できるのが、これまでの寄付とは大きく違う点です。
おすすめのサイトには、GIVING100やCAMPFIRE、Readyfor Charityなどがあります。
3.事業投資型クラウドファンディング
ファンド型ともよばれ、特定のビジネスに対して個人投資家が投資や融資をおこなうクラウドファンディングの型です。
リターンは金銭的なもの以外に、事業に関係する商品やサービスの割引券の場合や、両者の組み合わせもあります。金銭の場合は、売り上げの成果や出資額に応じ分配金が支払われます。
これまで新規事業の資金調達には金融機関で融資を受けるのが主流でしたが、クラウドファンディングサービスを利用することで、ベンチャー企業や個人でも手軽に資金を調達できるのが魅力です。
おすすめのサイトには、セキュリテ、Sony Bank GATE 、クラウドバンクなどがあります。
4.不動産型クラウドファンディング
複数の投資家がそれぞれ小口の資金で不動産事業に投資するクラウドファンディングの型です。
支援の対象は、リゾート開発、居住マンションや商業ビルなど多岐にわたり、集まった資金は不動産の取得と運営にあてられます。リターンは事業利益の分配なので、投資商材のひとつです。
不動産投資より少額の1万円からでもはじめられ、入居者の管理や修繕などのコストは起案者側が負担するので手軽にはじめられるのが魅力です。
おすすめのサイトには、CREALやCOZUCHI、CRE Funding、TECROWDなどがあります。
5.株式型クラウドファンディング
個人ではなく、株式会社が資金を調達するクラウドファンディングの型です。起案者は個人投資家から資金を集め、見返りとして非公開株を提供します。
2014年に金融商品取引法が改正され、総額1億円の資金調達ができるようになったことを受け、利用が増加しました。支援者にとっては、非上場企業の未公開株が買えるのが最大の魅力だといえるでしょう。
おすすめのサイトには、FUNDINNOやGoAngelなどがあります。
6.貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
クラウドファンディングのサイト運営事業者が仲介者となり、投資家から資金を集め企業に貸し付ける融資型の方式です。
たとえば資金を必要とする企業が起案者となり、資産運用をしたい投資家が支援者となります。
起案者にとっては、創立年数が浅いなどの理由で銀行から融資を受けられない場合もソーシャルレンディングなら資金が調達できるのが利点です。
支援者としては、投資として銀行よりも高い利回りが期待できるのが魅力だといえます。また投資には貸し倒れ(借りた企業が倒産し音信不通になるなど)のリスクがつきものですが、ソーシャルレンディングには担保や保証がついているものも多いのがポイントです。
おすすめのサイトには、OwnersBookやFunds、クラウドバンクなどがあります。
クラウドファンディングのメリット・デメリット

では次に、クラウドファンディングのメリットとデメリットについて、起案者側と支援者側それぞれの立場から見ていきましょう。
- 起案者側のメリット・デメリット
- 支援者側のメリット・デメリット
起案者側のメリット・デメリット
起案者側のメリット
起案者側のメリットとしては、
- 宣伝効果がある
- 誰でも始められる
- 大きなプロジェクトにもチャレンジ可能
- テストマーケティングができる
などがあげられます。
インターネットを利用するのでプロジェクト自体にも宣伝効果があるうえに、プレスリリースやSNSを通じてもさらに宣伝ができます。その結果、新規顧客やファンの獲得にも効果的です。
プロジェクトにはサイト運営側の審査が伴うものの、個人でも気軽に始められます。支援者の協力を得て、起案者だけでは実現できない大きなプロジェクトにチャレンジできるのも魅力です。
またプロジェクトに対する世間の反応を調査できるので、テストマーケティングの場としても活用する企業が増えています。
起案者側のデメリット
起案者側のデメリットは、
- プロジェクト失敗の可能性もある
- アイデアを盗用されるリスクがある
- プラットフォーム利用料が差し引かれる
などです。
プロジェクトページの作成には、動画や画像を作る経費や管理費用がかかります。目標金額に到達しない場合は、経費だけがかかって赤字になることもあるでしょう。
プロジェクトはネットでの拡散力が高いので、競合の目に止まった場合にはせっかく考えたアイデアを盗用されてしまうリスクがあります。
そのほか、集めた資金から10%〜20%ほどをサイト利用料として差し引かれることもデメリットの一つといえるでしょう。
支援者側のメリット・デメリット
支援者側のメリット
支援者側のメリットとしては、
- 少額から気軽に始められる
- 他では入手できない商品やサービスを得られる
- 社会貢献ができる
- 住民税や所得税の負担が軽減される(寄付型)
などがあげられます。
購入型ならネットショッピング感覚で利用できます。事業投資や株式型でも1万円程度から支援できるので、気軽に利用できるのが最大のメリットです。
まだ世に出ていない新商品をいちはやく手に入れられるのも魅力です。
寄付型では災害復興支援などのほかにも、購入型や事業投資型でも環境問題を改善するための製品を購入することで社会貢献に参加できます。
また寄付型では支援金が寄付金控除の対象になり、住民税や所得税の負担が軽減されるメリットもあります。
支援者側のデメリット
支援者側のデメリットは、
- リターンが受けられないないトラブルがある
- 基本的に支援をキャンセルできない
- 金銭を騙し取られるケースもある
などです。
たとえば起案者の見積もりが甘かった場合など資金不足でプロジェクトがとん挫し、リターンが制作できない事例も発生しています。
また支援者が投じた資金は、基本的にキャンセルができません。
購入型や寄付型で資金が目標額に到達しない場合は、プロジェクト失敗となり返金されます。一方、All-in方式の場合は目標額に達しなくてもプロジェクトが進行するため、返金されないので注意しましょう。
悪質なケースでは、そもそも実行する予定のない架空のプロジェクトを立ち上げる不正利用の可能性もあるので、要注意です。
クラウドファンディングは比較的新しい方式のため、支援者を守る制度がまだ完全には整っていません。当事者やサイトを通して解決できなければ、最終的に消費者センターや弁護士に相談することになるでしょう。
クラウドファンディングの市場規模は拡大見込み

画像出典:国内クラウドファンディング市場の調査を実施(2022年)矢野経済研究所
矢野経済研究所の調査結果によれば、今後もクラウドファンディングの市場規模は増加傾向にあります。
なかでも事業投資型、不動産型、株式型は規制緩和や法の整備の後押しを受け、今後も拡大する見込みです。一方、貸付型は2017〜2018年にクラウドファンディング運営企業が相次いで行政処分を受けた影響で大幅に減少し、現在も低迷が続いています。
このような経緯から、クラウドファンディング事業者が消費者保護の強化に取り組みはじめました。たとえば、プロジェクト内容の審査の厳格化、保険の提供やリスク開示の義務化などが含まれます。
これらの取り組みや2021年の起案者と支援者のニーズのさらなる増加から、今後もクラウドファンディング市場は拡大する見通しです。
クラウドファンディングを始めたいと考えている方は、手順や始め方も確認しておきましょう。「クラウドファンディング やり方」の記事で紹介しています。
クラウドファンディングは資金調達の手法

クラウドファンディングは新しい資金調達の手法として、定着しつつあります。銀行からの融資が難しい創立したての企業や、資金が十分に用意できない中小企業や個人でも新しいアイデアを諦めずチャレンジできる場です。
富士ロジテックホールディングスは、クラウドファンディングのリターン(返礼品)の発送業務を代行し、あなたのプロジェクトを応援します。
大切なプロジェクト支援者さまへの返礼品の入荷や保管、発送はもちろんのこと、感謝の気持ちをこめた特別な梱包作業にも対応可能です。
クラウドファンディング向けに特別料金をご準備しておりますので、詳細はぜひお気軽にご相談ください。
<関連記事>
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
オガミキヨ
国内外のECをはじめ、リユース、美容・健康、音楽などあらゆるジャンルで執筆中のフリーランスライター。中国への留学経験を生かし、13年間、繊維製品や楽器、雑貨の輸入業務に携わる。現在はライター業のかたわら、個人で越境ECのセラーとしても活動中。
タグ一覧
カテゴリー


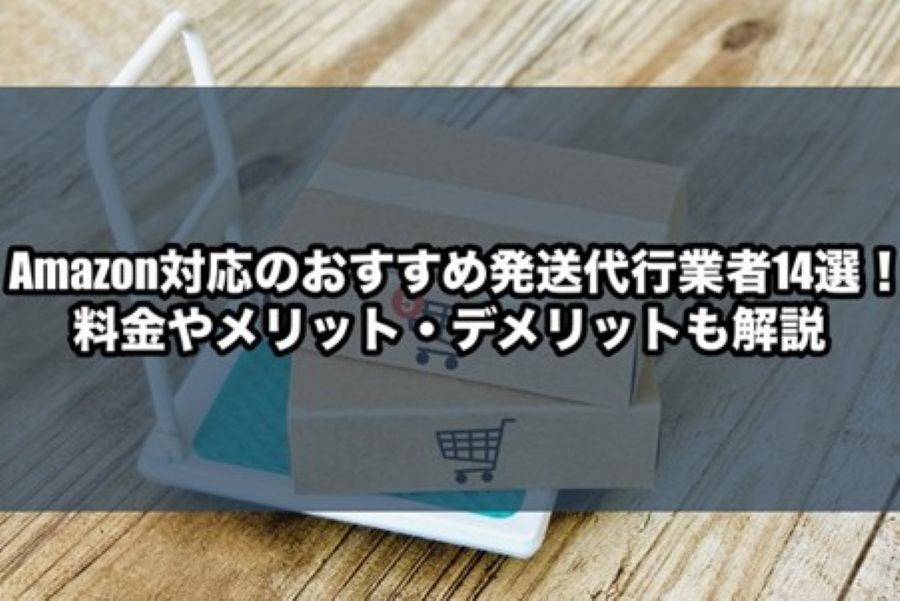
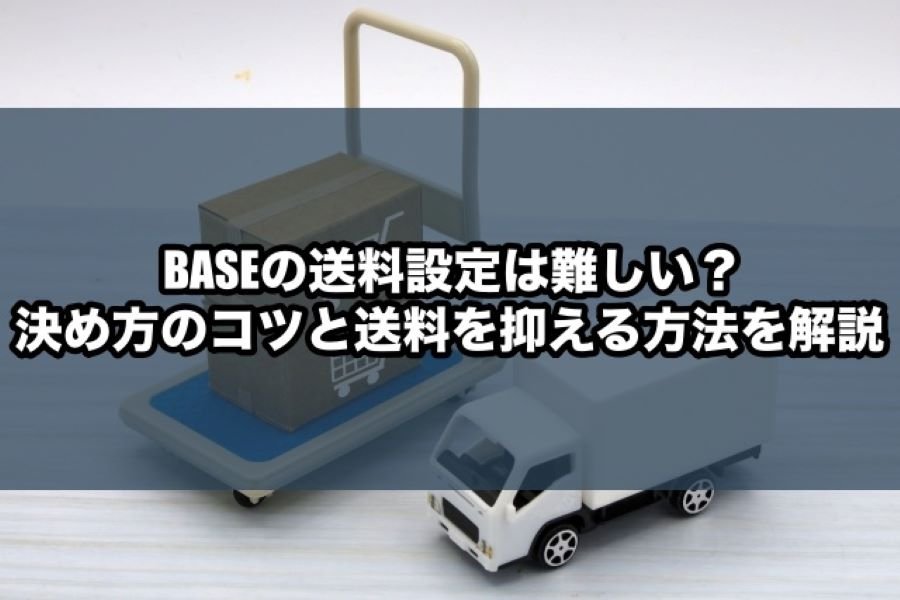
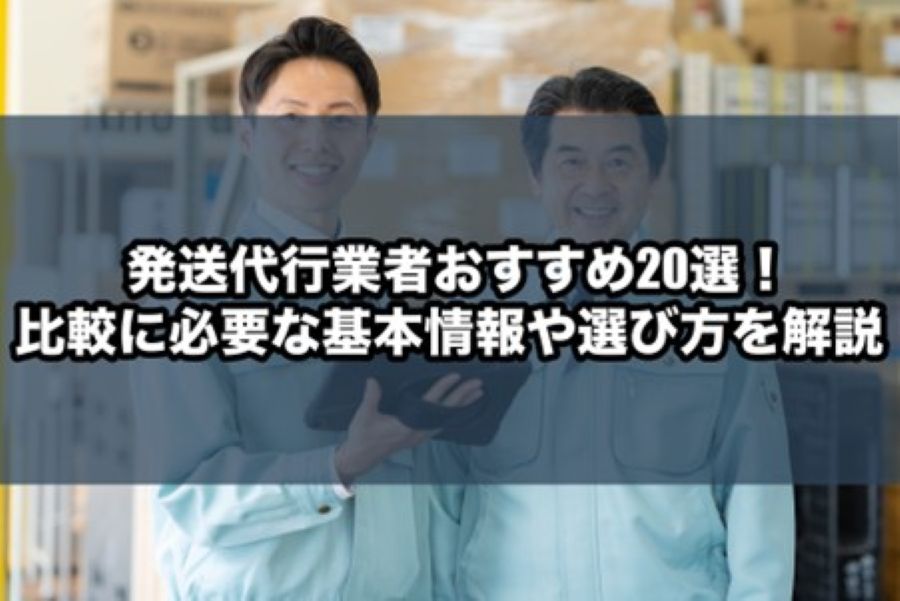


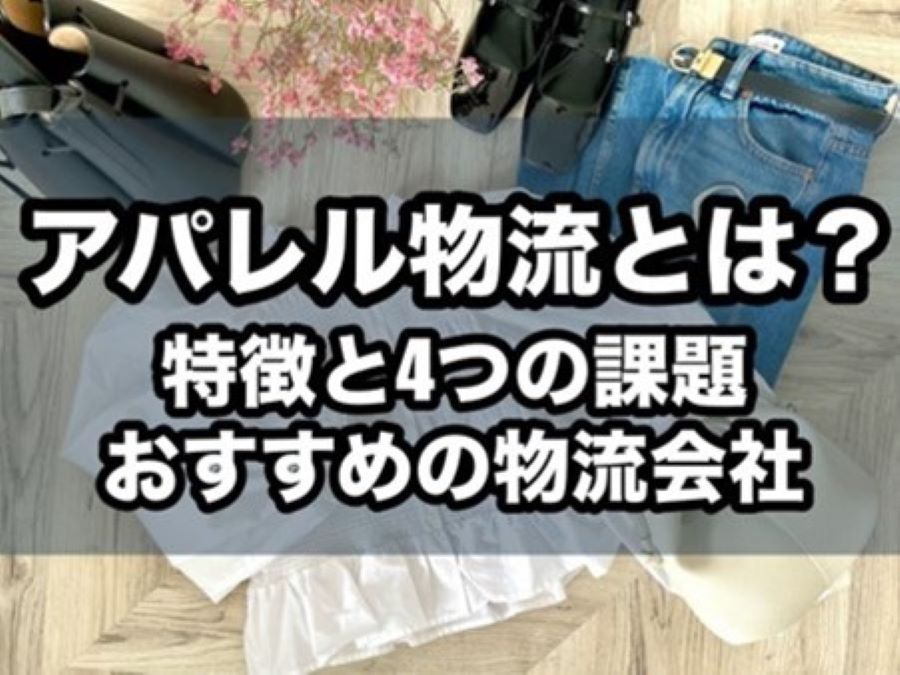
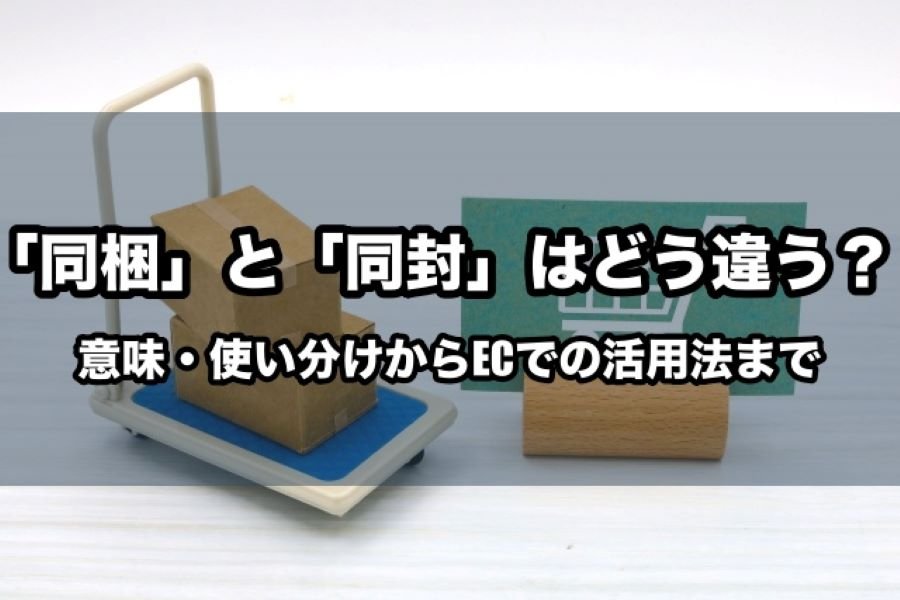
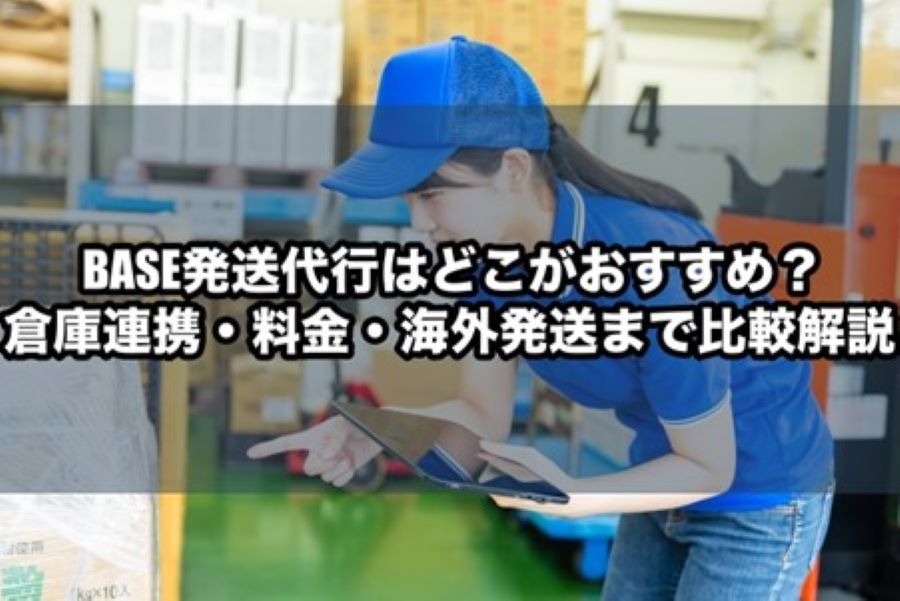







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)