
貿易事務と物流代行営業の経験を活かし、専門知識に基づいた記事作成を行っています。お客様に寄り添い、分かりやすく役立つ情報を提供します。

ECショップで商品を発送する際、ただ商品を箱に入れるだけになっていませんか?同梱施策を取り入れることで、顧客満足度の向上やリピート率の改善など、さまざまなメリットが得られます。
この記事では、同梱と同封の違いを整理し、同梱施策のメリットやデメリットを解説します。目的別に活用できる同梱物の種類を紹介しますので、ぜひ、自社の販促活動にお役立てください。
同梱の意味・同封との違いを解説
まずは、同梱の意味や正しい使い方を解説します。
- 同梱とは|読み方・意味・言い換え
- 同梱の使い方・例文
- 同梱と同封の違い:「入れる場所」が違う
同梱とは|読み方・意味・言い換え

「同梱」は「どうこん」と読み、注文された商品を1つの箱にまとめることを意味します。また、以下のような言い換えも可能です。
- まとめて発送します
- 付属しております
- 添付いたします
- もれなく付いてきます
ECショップでは、自社商品の販促を目的として、チラシやクーポン券などの同梱が可能です。
その他、EC取引では「同梱不可」といった言葉もよく使われます。この場合、複数の商品を1つの荷物にまとめて発送せず、個別発送になることを意味します。例えば、冷凍食品と常温商品を同時購入が発生した際は、配送方法が異なるため同梱不可と表記します。
同梱の使い方・例文
ECショップ運営でよく使われる「同梱」の例文をご紹介します。
- ご注文の商品に、次回購入で使える500円の割引クーポンを同梱いたします。
- 来月使える特別クーポンを商品に同梱してお届けします。
- 商品の使い方は、同梱のパンフレットをご確認ください。
このように、同梱はECショップ運営のさまざまな場面で活用されています。
同梱と同封の違い:「入れる場所」が違う

同梱と同封は、どちらも「一緒に入れる」という意味を持ちます。混同されやすい言葉ですが、入れる場所に違いがあります。
同封(どうふう)は、チラシや挨拶状などを封筒に入れる際に使う言葉です。一方、同梱は、小包や段ボールなどにチラシやクーポン、サンプル品などを商品と一緒に入れることを指します。
|
当メディアを運営する富士ロジテックホールディングスは、EC物流サービスを提供する物流会社です。 商品の保管や発送だけでなく、同梱作業も担い、EC事業者様の業務効率化をサポートします。複雑な同梱作業をプロに任せたい方はぜひ、資料をダウンロードしてサービスをご確認ください。 |
同梱施策で得られる5つのメリット

発送物に同梱施策を用いることで、さまざまなメリットが得られます。代表的な5つのメリットを解説します。
- 高い開封率で確実に届けられる
- リピート購入につながりLTVが向上する
- 購入意欲が高い顧客にアプローチできる
- DMより低コストで効率的に販促できる
- 顧客の声を集めサービスの向上が期待できる
高い開封率で確実に届けられる
ECショップでは、購入商品と一緒にチラシやクーポン券を同梱できるため、確実に顧客の手元に届けられます。開封される可能性が高く、内容に目を通してもらえる機会も増えるでしょう。
一方、メルマガやLINEなどのデジタル通知は、情報が埋もれやすく、開封率は約20%(※)と低い傾向です。同梱物であれば開封率に左右される心配がなく、自然な形で顧客との接点を作りやすい点がメリットです。
※出典:Benchmark Email|メルマガ平均開封率レポート【2024年版】
リピート購入につながりLTVが向上する
同梱により次回購入のきっかけを提供し、リピート購入の促進が期待できるメリットがあります。例えば、初回の購入者に次回使えるクーポンや関連商品の案内を同梱すると、購入後も顧客の関心を維持しやすくなります。
さらに、クーポンやポイント付与などの施策では、再購入のハードルを下げ、定期購入につなげることも可能です。このようにリピート購入が増えると、LTVの向上につながります。
LTV(顧客生涯価値)とは、顧客がサービスを利用し始めてから終了するまでに企業が得られる利益の総額です。同梱施策は、LTVを高めるうえで有効な手段のひとつといえるでしょう。
購入意欲が高い顧客にアプローチできる
ECショップの購入者は、すでに商品やブランドに魅力を感じている顧客です。そのような購入意欲の高い顧客に対して、直接アピールできるのも同梱施策のメリットです。
新商品の紹介やキャンペーン情報を同梱し、自然に情報を届けられます。その結果、前向きに検討してもらいやすく、追加購入や次回購入につながりやすくなります。
DMより低コストで効率的に販促できる
同梱物は、DM(ダイレクトメール)より低コストで効率的に販促できる点がメリットです。DMを送る場合は、以下のような配送コストがかかります。
- はがき:約70円
- 圧着はがき:約90円
- 封書:約80円
また、印刷代や封筒代など、さらに諸費用もかかります。一方で、同梱の場合は商品の発送に合わせてカタログやチラシを入れられるため、追加の送料や資材費が不要です。
DMを単独で送るよりコストを抑えられ、効率的に情報を届けられます。
顧客の声を集めサービスの向上が期待できる
同梱施策は、顧客の声を直接収集できる点がメリットです。例えば、アンケート用紙やレビュー用のQRコードを同梱することで、商品への満足度や改善点など、顧客のリアルな意見を把握しやすくなります。
購入者の貴重な声は、新商品の開発や既存サービスの向上に役立ちます。
<関連記事>「初回同梱物が通販の売上げを伸ばすワケとは?役割と10のツール事例」
LTVの向上を目的とした同梱物

ここからは、目的別に活用できる同梱物の種類を紹介します。まずは、LTVの向上を目的とした同梱施策を中心に解説します。
- 特典クーポン・お得情報チラシ
- 試供品・サンプル
- 定期購入の案内
特典クーポン・お得情報チラシ
特典クーポンやお得情報チラシは、次回購入のきっかけを作り、再購入を促進できるため、LTVの向上が期待できます。
以下のような特典を用意すると、購入につなげられます。
- プレゼントが付与される
- 1つ購入するともう1つもらえる
- 送料が無料になる
- バースデー特典として割引価格で購入できる
なかでも、誕生月ユーザーに送るバースデー特典は限定感を与えるため、購買意欲を高めやすい施策です。
また、クーポンを配布する際には、有効期限を設けるのがおすすめです。期限を設けることで、購入を促進できます。期限を記載する際は、トラブルを防ぐためにも、利用条件や期日を分かりやすく明記しましょう。
試供品・サンプル
新商品の試供品や期間限定品をサンプルとして同梱すると、自社が展開する商品を広く知ってもらう機会につながります。これらを同梱する際は、ユーザーの購入履歴をもとに関連性の高い商品を選ぶのがポイントです。
例えば、シャンプーを購入した顧客に同シリーズのトリートメントやへオイルなど、ライン使いできる商品を送ることで、クロスセルの機会を創出できます。また、スキンケア用品などの化粧品分野では、美容効果の高い美容液やワンランク上のサンプル品の同梱により、アップセルが期待できます。
サンプル品を同梱する際は、「会員様限定で感謝の気持ちを込めてお送りします」など一言添えると、顧客のロイヤリティを高められるでしょう。
定期購入の案内
単発購入者に対して定期購入を促すには、同梱物を活用したPRが効果的です。商品と一緒に案内チラシや特典情報を同梱することで、自然な形で定期購入の魅力を伝えられます。
例えば、以下のようなメリットを明記すると定期購入を後押しできます。
- 通常購入よりも割引価格で購入できる
- 継続利用に応じて割引率が高くなる
- 送料が無料になる
- 定期購入者限定のプレゼントや特典を受け取れる
- ポイントが通常より多く付与される
- 購入者のライフサイクルに合わせて配送間隔を調整できる
スキップや配送日の変更が柔軟に変更できると、安心感につながり、継続率を維持しやすくなるでしょう。LTVの向上と安定した売上の確保が期待できる施策の一つです。
顧客満足度向上を目的とした同梱物

顧客満足度向上を目的とする場合は、購入後の不安を減らし「買ってよかった」と思える同梱物がおすすめです。
- 挨拶状・サンクスレター
- 商品説明書・使い方ガイド
- アンケート・レビューキャンペーン案内
挨拶状・サンクスレター
購入と一緒に同梱される挨拶状やサンクスレターは、ブランドへの安心感を高め、顧客満足度の向上につながります。特に、初回購入時に丁寧な挨拶状を添えると、顧客との良好な関係性を築きやすいでしょう。
また、挨拶状は毎回同じ内容を送るのではなく、購入商品に応じて個別のメッセージにすることで、ブランドへの信頼感も高まります。余裕があれば、手書きの一言を添えるのも効果的です。
商品説明書・使い方ガイド
商品説明書や使い方ガイドを同梱することで、商品の正しい使用方法を伝えられ、購入後の不安や疑問を解消できます。顧客満足度を高めるだけでなく、商品の誤用やトラブルを未然に防ぎ、問い合わせの削減にもつながります。
同梱する説明書は、図やイラストを用いて手順をわかりやすく伝える工夫が必要です。自社で動画説明を用意している場合は、QRコードを掲載し、視覚的に理解できるコンテンツへ誘導するのも効果的です。
アンケート・レビューキャンペーン案内
商品購入直後のアンケートは、より具体的で有益な情報を集めやすくなります。アンケートやレビューキャンペーンを実施する際は、短時間で簡潔に回答できる設計がポイントです。
商品と一緒にQRコードを同梱し、スマートフォンからすぐに回答画面にアクセスできると効果的です。自由記述は最小限にし、選択形式を中心にすると、回答率が高まりやすくなります。
アンケート回答者には、次回利用できるクーポンや商品サンプルなどの特典を用意すれば、積極的な参加を促せるでしょう。
ファン化を目的とした同梱物

ファン化とは既存顧客との関係性を強め、継続的に選ばれる存在になることを指します。ファン化を目的とした施策には、以下のような同梱物が適しています。
- ブランドブック
- ノベルティグッズ
- お客様体験談・FAQ集
ブランドブック
ブランドブックとは、企業のビジョンや価値観、コンセプトをまとめた冊子です。購入商品と一緒にブランドブックを同梱することで、企業やブランドへの愛着が深まります。
ブランドブックには、以下のような工夫を取り入れると効果的です。
- デザインにこだわり、視覚的な魅力を高める
- PDFで提供し、手軽に閲覧できるようにする
- 付録を添えて特別感を演出する
- 商品開発のエピソードや利用シーン、スタイリングを紹介する
このような同梱施策により、単なる購入者からファンとしての長期的な関係性を築けるでしょう。
ノベルティグッズ
ノベルティグッズとは、企業が自社のロゴ入り商品など(ポケットティッシュやペン、クリアファイルなど)を特典として無料配布する販促品のことです。ノベルティグッズの活用により、ブランドの認知度向上やイメージアップが期待できます。
また、SNSで話題になれば、さらに多くの人にブランドを知ってもらえる機会も増えるでしょう。ただし、同梱する際には「景品表示法」の規定により、以下の上限金額が定められているため、注意が必要です。
|
取引金額 |
景品上限金額 |
|
1,000円未満 |
200円以下 |
|
1,000円以上 |
取引価額の2割(10分の2)以内 |
※参照:消費者庁|景品規制の概要
近年では、エコバッグやタンブラー、モバイルバッテリー、USBケーブルなどバラエティ豊富なアイテムも採用されており、顧客に喜ばれる特典として活用できます。
お客様体験談・FAQ集
体験談やFAQ集は、顧客の不安や悩みを事前に解決できるので、企業に対する信頼感が強まり、ブランドに愛着を持つファン化が期待できます。商品を検討する際、お客様の体験談やFAQ集は大きな決め手となります。
例えば、スキンケア商品や健康食品、家電製品などでは、実際の使用感やレビュー、使い勝手などの体験が分かると、購入につなげやすいでしょう。
リピート購入者の体験談を知ることで、定期購入や継続利用の促進にも役立ちます。
同梱の効果を高める5つのポイント

同梱物で効果を上げるには、いくつかのポイントがあります。
- ターゲットに合わせて訴求する
- 期間限定で特別感を演出する
- オリジナリティを意識する
- サステナブル資材を活用する
- SNSに誘導する
5つポイントを押さえて、同梱施策の効果を高めましょう。
ターゲットに合わせて訴求する
同梱施策で成果を出すには、顧客のニーズに合わせた工夫が必要です。
例えば、「60代・女性・主婦」と「20代・男性・会社員」では、生活スタイルや求める商品、商品を購入したいと感じる動機が異なります。
顧客の購入履歴や年齢層を分析し、ターゲットに合わせた同梱物を届けることで、新商品の購入など次の行動につなげやすいでしょう。
期間限定で特別感を演出する
期間を定めていないクーポン券は「あとで使おう」と放置されがちです。クーポンや割引券は、購入直後など顧客の関心が高いタイミングで、期間限定として同梱するのがポイントです。
例えば、有効期限を1ヵ月以内に設定すると、顧客が次の行動に移しやすくなり、早期の再購入や定期購入に促しやすくなります。
オリジナリティを意識する
同梱施策では、顧客の心に残る工夫が欠かせません。例えば、オリジナルデザインの包装紙や手書きのメッセージカードを添えることで、「大切に扱われている」という印象を与えられます。
このような細やかな配慮により、ブランドの印象をより強め、顧客に特別感を感じてもらえるでしょう。
サステナブル資材を活用する
梱包材や印刷インクにサステナブル資材を取り入れることで、企業が環境に配慮している姿勢を顧客に伝えられます。環境意識の高い顧客にとっては、こうした取り組みが企業やブランドへの共感につながります。
<関連記事>「ecサイトでの同梱物・梱包資材の重要性とは?物流管理の視点から」
SNSに誘導する
同梱物にQRコードを掲載し、公式SNSへスムーズに誘導する方法も効果的です。SNSを活用してフォローを促すことで、継続的な接点が生まれ、ファン化が期待できます。
また、インスタ映えするデザインや、投稿時に使ってもらいたいハッシュタグを用意しておけば、ユーザーが気軽に発信しやすくなります。
同梱のデメリット

同梱施策はメリットが多い一方で、いくつかのデメリットもあります。
- 過剰な同梱物は逆効果になりやすい
- ECモールの規約違反リスクがある
- 費用負担が増加しやすい
- 作業工程が増え業務が煩雑化しやすい
デメリットを事前に把握し、目的や予算に合った同梱施策を無理なく導入しましょう。
過剰な同梱物は逆効果になりやすい
同梱物が多すぎると、開封されても目を通されないまま廃棄されてしまう可能性があります。また、宣伝色が強すぎると押しつけがましく感じられ、ブランドイメージを損なう恐れもあります。
同梱物を入れる際は、顧客のニーズに合ったものを選び、適切な量を意識することが大切です。
ECモールの規約違反リスクがある
ECモールによっては、同梱物に関する規約が定められている場合があります。例えば、外部購入を促すクーポン券や他モールへの案内などURLの記載を禁止するケースもあります。
各モールの規約を事前に確認しておきましょう。
費用負担が増加しやすい
同梱施策では、チラシの印刷代やデザイン費などの制作コストが発生します。さらに、業務が増えることで人材コストがかさみやすく、全体の費用負担が増加しやすい点がデメリットです。
同梱施策をおこなう際は、費用対効果を意識し、無理のない範囲で運用する必要があります。
作業工程が増え業務が煩雑化しやすい
同梱施策は、「誰に・何を・どのタイミングで同梱するか」といった判断が複雑になり、現場の作業負担が大きくなりやすいデメリットがあります。
例えば、「初回購入の顧客には、挨拶状を同梱」「2回目購入の顧客には、サンプルを同梱」のように、条件を起点としてピッキング・梱包をしなければなりません。
特に同梱物の種類が増えると、ミスのリスクが高まり、業務が煩雑化しやすくなります。
このような課題を解消するには、ECショップ側のOMS(受注管理システム)やECカートから、倉庫側のWMS(倉庫管理システム)に理解しやすい指示データを送信する必要があります。
こうした仕組みを自社で構築するのが難しい場合は、ECに強い物流事業者へアウトソーシングするのがおすすめです。
<関連記事>「梱包代行のおすすめ業者12選!料金 やメリット、選定方法まで解説」
同梱の業務負担はアウトソーシングで解決しよう

ECショップでは、同梱施策により顧客との信頼関係を築き、自社ショップのファン化につなげられます。目的別に合った同梱物を取り入れれば、効率的な販促活動が実現できるでしょう。
同梱をおこなう際は、顧客のニーズに合わせて適切な販促物を選ぶことが重要です。富士ロジテックホールディングスでは、複雑な同梱条件に対応できるシステムを活用し、ミスなく発送作業を代行しています。
例えば、「誕生日お祝い専用の割引チケット」や「継続特典用のチラシ」など、個別対応も可能です。さらに、物流業務を一括でアウトソーシングできるため、作業負担も軽減できます。
同梱施策で効果を高めたい方は、ぜひ富士ロジテックホールディングスにご相談ください。現在、スタートアップ新規事業者様限定プランも提供中です。
スタートアップ新規事業者様限定プランの資料をダウンロードする
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
森恵
貿易事務と物流代行営業の経験を活かし、専門知識に基づいた記事作成を行っています。お客様に寄り添い、分かりやすく役立つ情報を提供します。
タグ一覧
カテゴリー








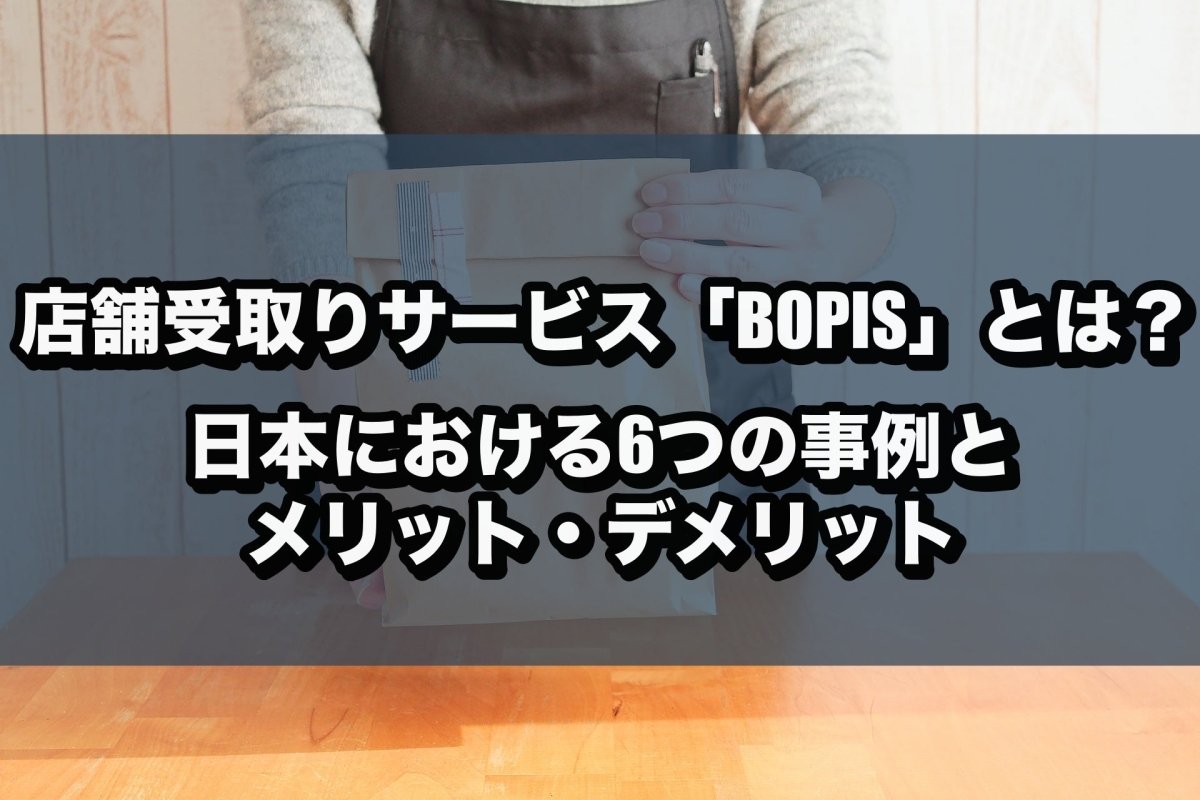
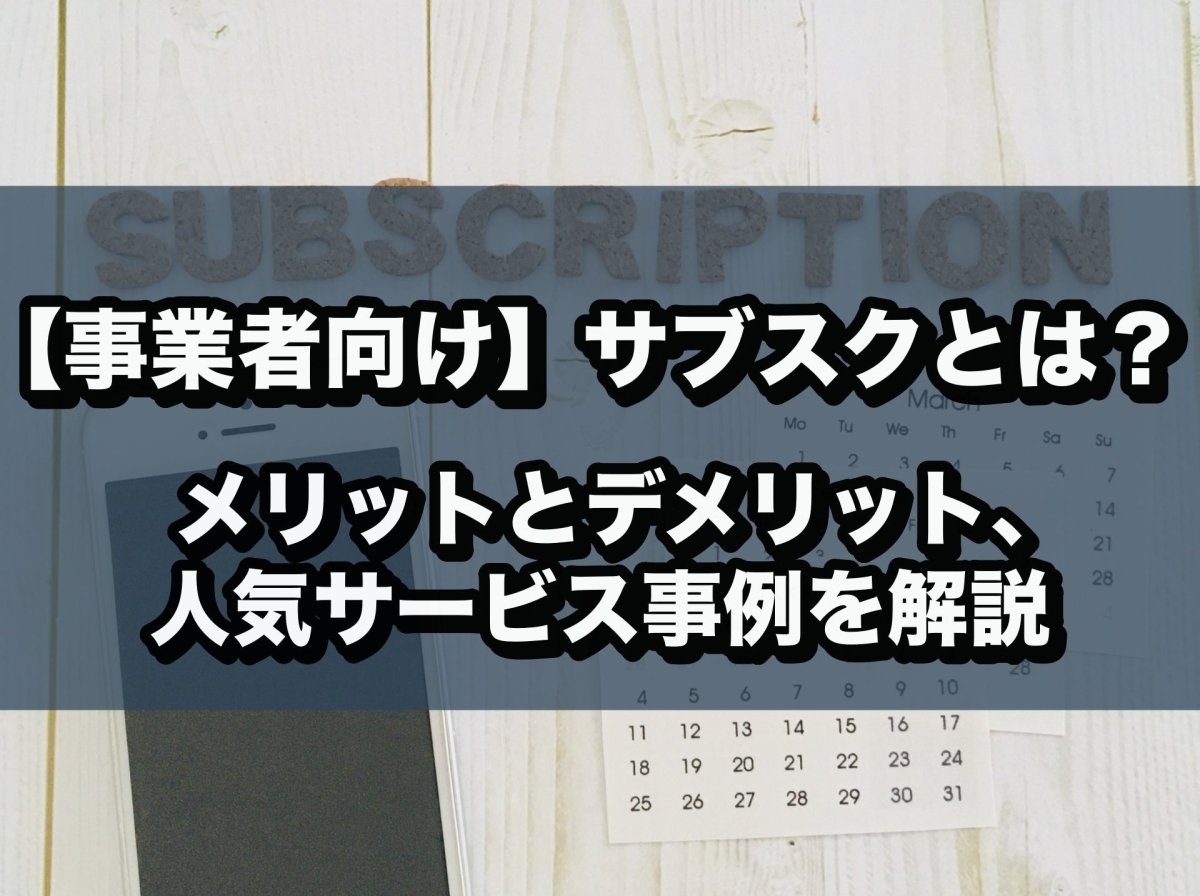
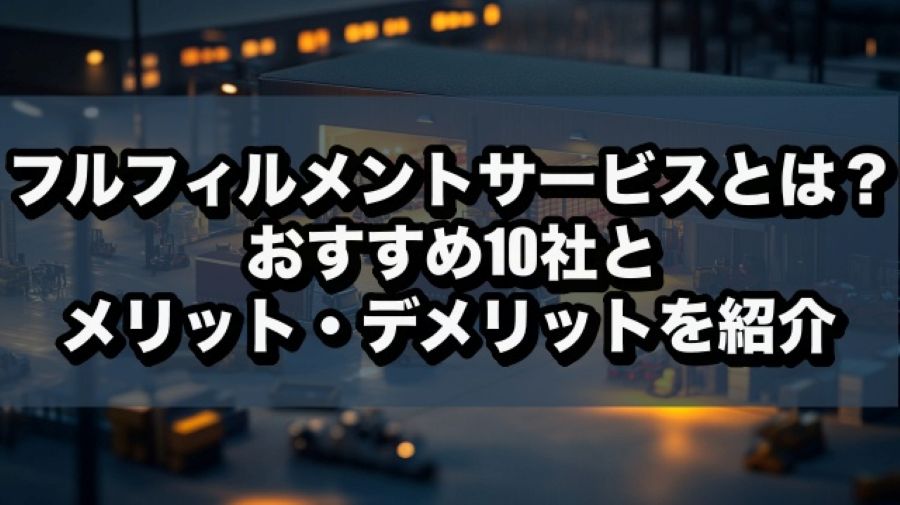
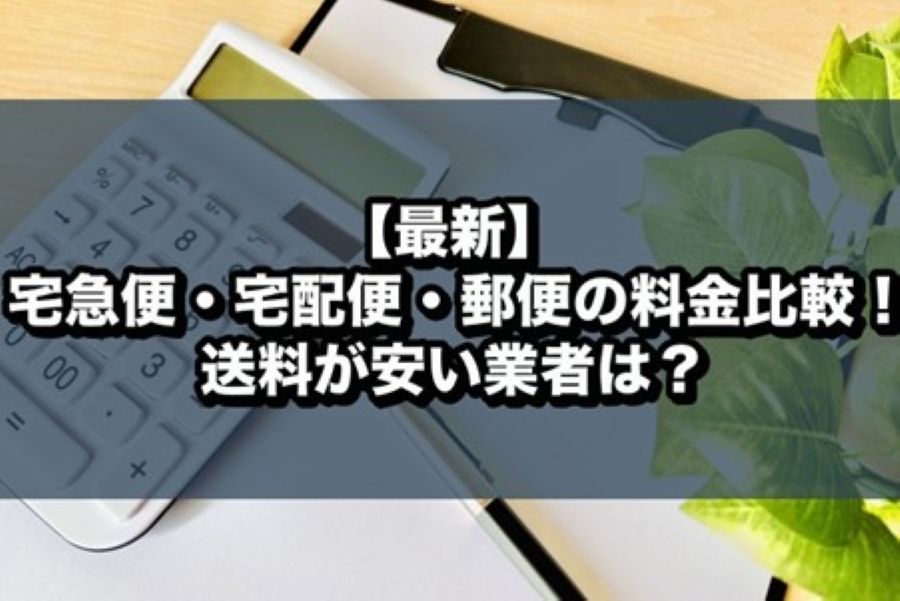
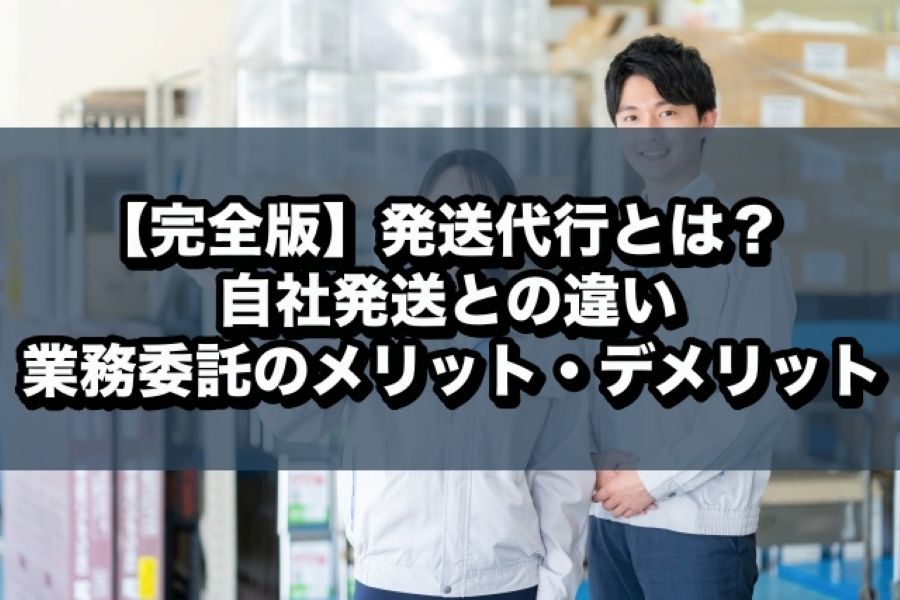










![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)