
物流ライター。青山女史短期大学を卒業後、物流会社に14年間勤務。現場管理を伴う、事務職に従事する。その後、2022年にフリーライターとして独立し、物流やECにまつわるメディアで発信。わかりやすく「おもしろい物流」を伝える。

「テレコ」という言葉、あなたは耳にしたことがありますか?
物流現場やビジネスシーン、関西の会話でも使われるこの言葉。
単に「あべこべ」「交互」といった意味で使われることが多い一方で、物流業界においては重大な出荷ミス=テレコ出荷を指す専門用語としても使われています。
テレコミスは、顧客満足度の低下やコスト増加につながるだけでなく、個人情報漏洩などの重大リスクを引き起こすおそれもあります。
この記事では、テレコの語源や意味をおさえつつ、物流現場で起きる「テレコ出荷」のリスクと、原因・対策について解説します。
テレコとは?意味・語源・由来
テレコは、「あべこべ」「交互」「たがい違い」を表す日本語の俗語です。
関西圏では日常的に使われ、ビジネスシーンでも「順番が入れ替わっている」「取り違えた」といった意味合いで使われます。
語源には諸説ありますが、主に2つの説が知られています。
- 歌舞伎において異なる脚本を交互に上演する形式に由来する説
- 順番を整えるために手を加える「手入れ(ていれ)こ」から転じて、「交互に整える」という意味を持ったという説
物流現場で使われる「テレコ」の意味と使い方

物流業界において「テレコ」は、他とは異なる重大な業務ミスを指す用語として使われています。
この章では、物流現場での「テレコ」の使われ方や、どのようなミスを指すのかを具体的に見ていきましょう。
テレコ出荷とは?|送り先や納品書の取り違え
物流における「テレコ」とは、主に出荷ミスの一種を指します。
たとえば、本来Aさんに届けるべき荷物がBさんに、Bさんの荷物がAさんに届いてしまったといった納品先のあべこべ状態を「テレコ(テレコ出荷)」と呼びます。
テレコは「正しい商品を正しい人に届ける」という物流の基本が崩れてしまう重大なミスです。日頃から、予防策や発生した時の適切な対応が求められます。
物流現場での会話例|テレコの使われ方
「テレコ」は物流業界の中では、口頭報告やメールを通じた事故報告や、関連する業務連絡に使われます。
たとえば、以下のような言い回しが挙げられます。
- 「納品先、テレコになってるみたいです」
- 「在庫差異が発生していないので、テレコかもしれません」
- 「送り状がテレコになって出ちゃってます」
物流業界では「テレコ」という言葉が、単なる状態の表現ではなく、ミスの種類を示す実務用語として定着しています。
テレコが起こりやすい業務プロセス
テレコは、複数の出荷オーダーを並行して処理している現場や、作業が混み合っているタイミングで発生しやすい傾向があります。以下のような業務プロセスでは特に注意が必要です。
梱包時の混在
複数のオーダーを同時に処理していると、帳票や商品を取り違えて梱包してしまうリスクがあります。荷姿や商品内容が似ている場合、商品コードやロット番号などの確認作業を怠るとテレコが発生しやすくなります。
送り状の添付ミス
出荷準備時に送り状を複数枚並べて処理していると、誤って隣の送り状を貼り付けてしまうことがあります。オーダー番号や宛先の確認を怠ると取り違えのリスクが高まります。
輸配送工程での仕分けミス
トラックへの積み込みや方面別仕分けの際、別の方面に振り分けてしまうケースがあります。似た荷姿の外装箱や複数個口の納品は、仕分け時に混乱が生じやすい傾向です。
配達時の納品ミス
類似した住所や納品先名が並ぶ地域では、配達時に商品を取り違えてしまうことがあります。マンションやテナントビルでは、フロアや号室の確認が甘いと、誤配が起きる可能性があります。
テレコ出荷が招く6つのリスク

テレコが発生すると、納品ミスが連鎖的に複数件発生する可能性があります。
顧客・荷主・物流会社のすべてにとって避けるべき損失です。ここでは、代表的なリスクを紹介します。以下の6つです。
- 個人情報の漏洩
- 納品遅延やキャンセルの発生
- 顧客満足度の低下
- 在庫管理の複雑化
- 不良在庫の発生
- 作業工数とコストの増加
1.個人情報の漏洩
テレコによって誤配送が起きると、納品書や送り状に記載された氏名・住所・電話番号などの個人情報が第三者に渡ってしまうリスクが発生します。
BtoB取引では、取引先ごとに商品単価や取扱品が異なるケースもあり、納品書情報の流出によって信頼関係が損なわれることも考えられます。
2.納品遅延やキャンセルの発生
テレコにより誤配送が発生すると、正しい商品を再送するまでに時間がかかり、納品の遅延やキャンセルにつながることがあります。
テレコは、倉庫内の在庫数が帳簿上は一致しているため、現場ではミスに気づきにくいのが特徴です。2件の誤出荷を起こしているにもかかわらず、数量上は問題がないため、お客様からの連絡で初めて発覚するケースも少なくありません。その分、対応が後手に回りやすく、納期遅延のリスクが高まります。
3.顧客満足度の低下
テレコは、受け取った側のストレスや手間を生むため、信頼の低下を招きます。間違った商品を返送したり、連絡を入れたりと、顧客に余計な対応を強いることになるからです。
ECサイトなどでは、こうした対応が低評価レビューに直結することも多く、ブランドイメージや再購入率の低下にもつながります。
4.在庫管理の複雑化
テレコが発生すると、本来の宛先とは異なる顧客に商品が届いた場合でも「出荷済み」として処理されており、在庫差異は発生しません。
しかし、その後の返品や再送、不良品の発生によって、在庫管理が複雑になることがあります。
- テレコした商品が欠品となってしまい、商品が返品がされるまで再送できない
- 一方の納品先が商品を受け入れてしまいテレコ相手が不明となってしまう
- 注文キャンセルとなり出荷処理や売上は取り消さなければならないが、返送されるまで在庫を帳簿上の数字に戻せない
このように、一時的に「使えない在庫」や「戻るかわからない在庫」が倉庫内に発生します。帳簿上の数字と現場の動きにズレが生じることで、在庫の把握や補充判断にかかわる管理工数が増加することもリスクのひとつです。
5.不良在庫の発生
テレコ出荷で誤って納品された商品が、開封・使用された状態で返品されると、再販できなくなる可能性が高くなります。
食品・飲料など、衛生管理が重要な商品はもちろんのこと、衣料品や雑貨もパッケージ破損によって再梱包が必要になり、一時的に不良在庫となるケースは少なくありません。
6.作業工数とコストの増加
テレコが発生すると、本来不要な作業が発生します。
- 誤納品の確認と顧客対応
- 返品処理と正しい商品の再発送
- 顧客への謝罪や返金処理、社内報告・再発防止策の検討
これらの工数・時間・人員コストは、1件あたり数倍の負担になることもあります。ミスが頻発すれば、それだけで物流コスト全体を圧迫する要因になりかねません。
|
当メディアを運営する富士ロジテックホールディングスは、創業から100年以上にわたり物流業務を支えてきました。物流トラブルは、物流会社への委託や物流会社の見直しで改善するかもしれません。お困りの方はぜひ、ご相談ください。 |
テレコが起こる4つの原因

テレコを発生させないために、まずは原因を知りましょう。
なぜミスが発生してしまうのか、突き詰めて考えることで、適切な対処法が見えてくるはずです。テレコの主な原因は次の4つが挙げられます。
- 目視に頼った作業
- 思い込みによる確認ミス
- 作業環境の問題
- 「注意喚起だけ」の対策不足
テレコの原因1.目視に頼った作業
テレコの原因1つ目は、目視に依存した帳票のつきあわせ作業です。出荷指示書、送り状、納品書などを人の目だけで照合し、セットしている場合、「6」と「9」、「8」と「3」のような数字の見間違いが発生しやすくなります。
また視力や集中力、疲労度など、作業者のコンディションにも左右されるため、安定的な品質の確保が困難です。
テレコの原因2.思い込みによる確認ミス
テレコの原因2つ目は、長時間のルーチン作業の中で生まれる「きっと合っているだろう」という思い込みです。数十件、数百件と出荷の処理を進めるうちに、出荷指示書、送り状、納品書を照合したつもりになってしまうケースも考えられます。
たとえば、ダブルチェックの体制を敷いていたとしても、2人目の確認者が流れ作業的に照合を行えば、エラーが見逃されてしまいます。
人の感覚に依存する仕組みでは、「チェックしているつもり」のミスが起こりやすくなるでしょう。
テレコの原因3.作業環境の問題
テレコが発生する原因の3つ目は、梱包や出荷に十分なスペースが確保できていないことです。
オーダーを並行して処理している際、作業台が狭く乱雑になっていると、別の注文に使う帳票や商品を誤って手に取ってしまうリスクが高まります。
特に繁忙期や複数人での同時作業時には、スペースとオペレーションの設計がミス防止に直結します。
テレコの原因4.「注意喚起だけ」の対策不足
ここまで紹介したようなテレコの原因を「注意不足」のみとして捉えてしまうことは、テレコが再発してしまう原因となります。
「責任者から注意喚起を行う」といった対策では根本的な改善は見込めません。たとえヒューマンエラーだとしても、なぜヒューマンエラーが発生したのか、突き詰めて考える必要があります。つまり、「人に気をつけさせる」よりも、「ミスを防げる仕組み」をつくることが再発防止の本質です。
<関連記事>「誤出荷が起こる4つの要因と発生リスク、5つのミス防止対策を解説!」
テレコ出荷を防ぐには?物流現場でできる5つの対策
では、具体的にテレコを防ぐにはどのような対策を講じればよいのでしょうか。次の5つの対策が挙げられます。
- ピッキング〜梱包〜帳票添付の業務フローを見直す
- 帳票の扱いにルールを設ける
- 出荷・梱包スペースの確保
- ダブルチェックのタイミングと担当を明確にする
- WMS(倉庫管理システム)とハンディーターミナルの活用
以下で詳しく解説します。
テレコを防ぐ対策1.ピッキング〜梱包〜帳票添付の業務フローを見直す
テレコの多くは、送り状や納品書などの帳票を誤って添付してしまうことによって発生します。帳票の準備と梱包が同時並行で行われている現場では、作業台上で混在するリスクが高まります。
この対策として有効なのが、梱包完了後に帳票を発行・添付する運用に切り替えることです。作業順を「ピッキング → 梱包 → 帳票添付」と明確に分けることで、帳票の取り違えを防ぎやすくなります。
テレコを防ぐ対策2.帳票の扱いにルールを設ける
帳票類の取り扱いも、テレコ出荷防止には欠かせないポイントです。たとえば、納品書や送り状をオーダーごとにクリアファイルで管理し、作業中に混ざらないようにするだけでも効果があります。
伝票類をオーダーごとにクリアファイルにまとめる際には、オーダー番号や住所の読み上げ、ダブルチェックを行い、誤りのないように細心の注意を払います。
テレコを防ぐ対策3.出荷・梱包スペースの確保
テレコを発生させないためには、整理整頓された環境作りも重要です。日々、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を意識しましょう。
- 道具は定位置に片付ける
- 決まった時間に清掃する
- 不要なものは破棄する
整然と作業できる十分なスペースが確保できれば、納品書や送り状をあべこべにしてしまうミスは減少するでしょう。
テレコを防ぐ対策4.ダブルチェックのタイミングと担当を明確にする
ダブルチェックの運用をしていても、「誰が・いつ・何を」チェックしたかが曖昧では意味がありません。ダブルチェックの責任者とタイミングを明確に決め、作業記録として残す運用にすれば、確認の抜けを防ぐことができます。
「確認したつもり」が最大の落とし穴です。責任の所在を明確にし、ダブルチェックも機能しやすくしましょう。
<関連記事>「検品作業とは?仕事内容と問題点・ミスなく効率化するコツを紹介」
テレコを防ぐ対策5.WMS(倉庫管理システム)とハンディーターミナルの活用
可能であれば、ハンディーターミナルとWMS(倉庫管理システム)の導入を検討すべきです。商品・納品書・送り状それぞれにバーコードを付け、ハンディーターミナルでスキャン照合を必須とすることで、人為的ミスの発生を大幅に抑えられます。
目視や手作業が残る場合は、「スキャンが完了しないと次工程に進めない」というような業務設計にすれば、チェックの強制力を高めることができます。
<関連記事>「ピッキング作業ミスをなくす10の方法!【倉庫従事者がコツを直伝】」
アウトソーシングや物流会社の見直しも選択肢

テレコが慢性化してしまい、改善にあたっても効果が出ない場合は、物流のアウトソーシングも選択肢のひとつです。
<関連記事>「EC物流アウトソーシングのメリット・デメリット!おすすめ企業3選も紹介」
物流を外注することで品質の改善と並行して、作業スタッフや保管スペースにかかる固定費を見直すチャンスです。事業拡大に伴い出荷ミスや納品遅延が目立つように感じてきたときが、発送代行サービスを検討するタイミングともいえます。
また、なかには委託先の物流会社によるテレコに悩んでいらっしゃるケースもあるでしょう。物流会社といえども、品質は一様ではありません。委託倉庫の見直しを行い物流改善をした事業者様の声も聞きます。
当メディアを運営する富士ロジテックホールディングスでは、ハンディターミナルの他、ロボティクスやOMS(受注管理システム)一体型のWMSを導入し、高品質な物流を提供しています。
この機会にぜひお問い合わせください。
さまざまな業界で使われる「テレコ」の意味
「テレコ」は、業界によって少しずつ異なる意味で使われています。
アパレル業界での「テレコ」
アパレル業界において「テレコ」とは、リブ編みの一種である「テレコ生地(テレコニット)」を指します。表と裏に凹凸のある編み目が交互に現れるため、伸縮性に富み、肌あたりも柔らかい素材です。
アパレルでは、「交互」の意味を持ちながらも、素材の名称として使われている点が特徴です。
映像・放送業界での「テレコ」
映像編集や放送業界では、「テレコ」は2つ以上の音声・映像素材を交互に切り替える演出や編集手法を指すことがあります。
また、セリフの順番が入れ替わったときなどに「テレコになっている」と使われるケースも見られます。
ビジネスシーンや日常会話での「テレコ」
一般的なビジネスの場面や日常会話における「テレコ」は、「あべこべ」「順番違い」といった意味で用いられます。
たとえば以下のような言い回しがよく使われます。
- 「この資料、順番がテレコになってるよ」
- 「請求書の送付先、テレコになっていませんか?」
業界によって使われ方に違いはあるものの、いずれも「交互」や「取り違い」といったニュアンスで使われている点は共通しています。
テレコ出荷による「あべこべ」には対策を!
テレコは主に「あべこべ」「交互」の意味を持つ言葉として、さまざまなビジネスシーンで使われています。
その中でも物流業界では、クレームを招く出荷ミスを表します。言葉の意味を理解したうえで原因の究明と改善に取り組むべき事象です。業務フローや作業場の見直し、システムや発送代行の導入を検討してみてください。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
田中なお
物流ライター。青山女史短期大学を卒業後、物流会社に14年間勤務。現場管理を伴う、事務職に従事する。その後、2022年にフリーライターとして独立し、物流やECにまつわるメディアで発信。わかりやすく「おもしろい物流」を伝える。
タグ一覧
カテゴリー







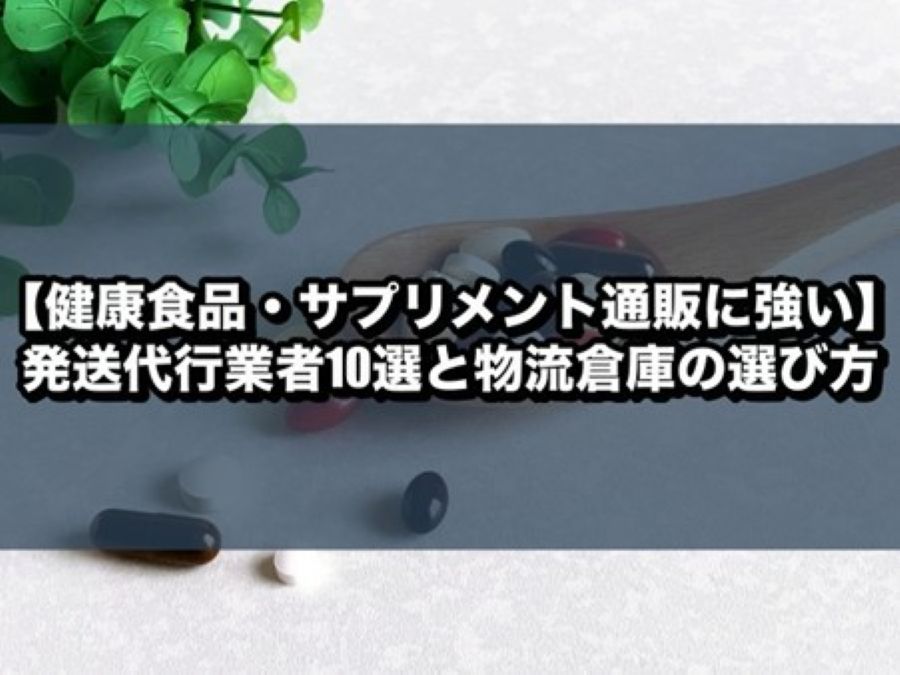
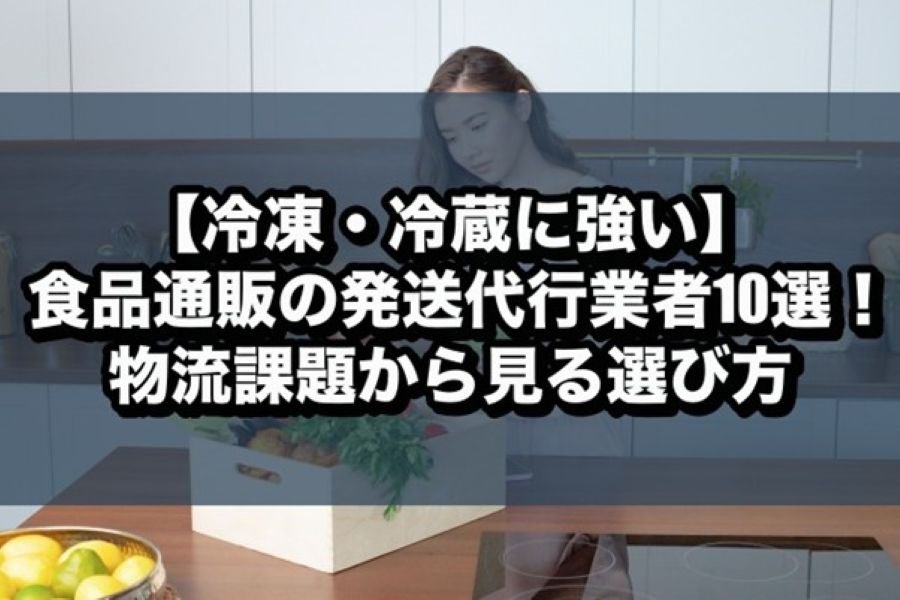

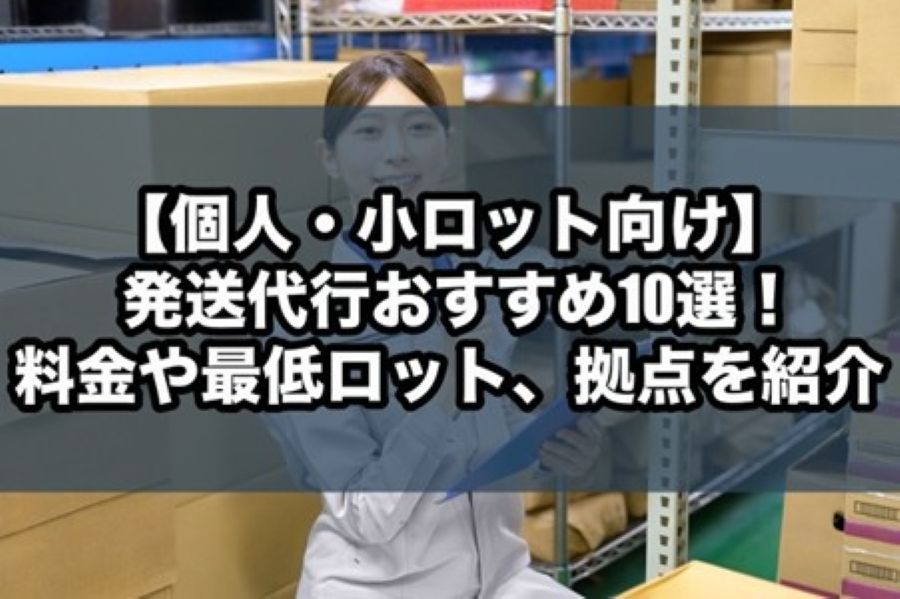
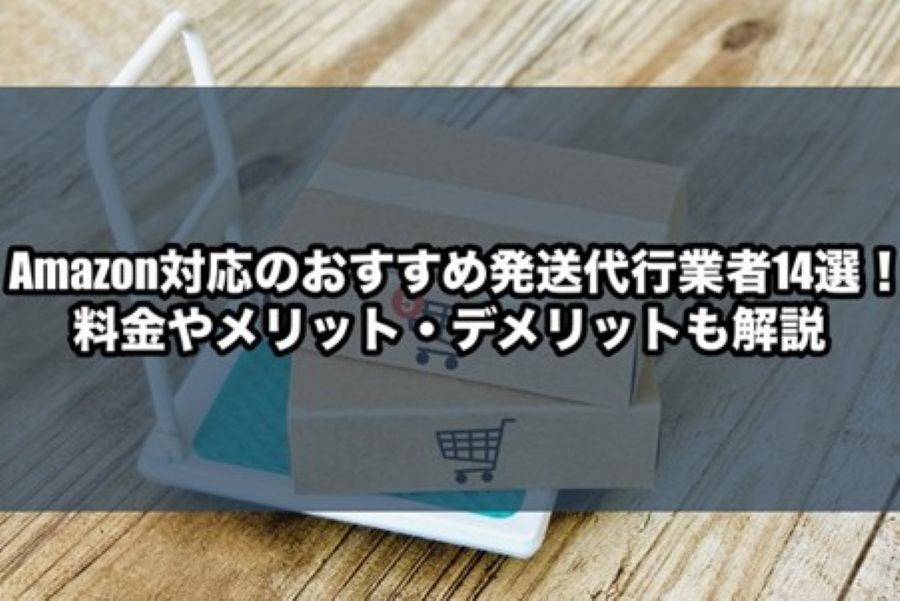
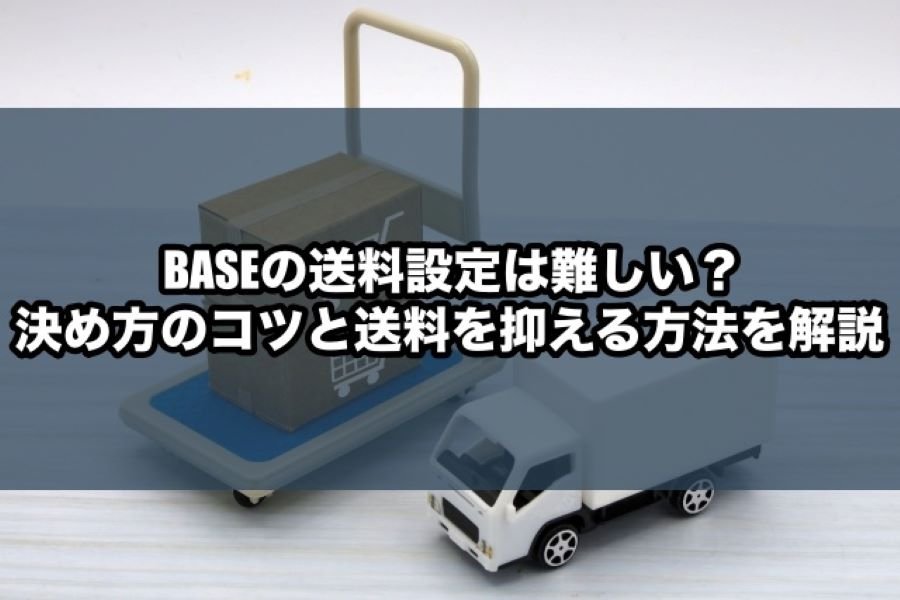
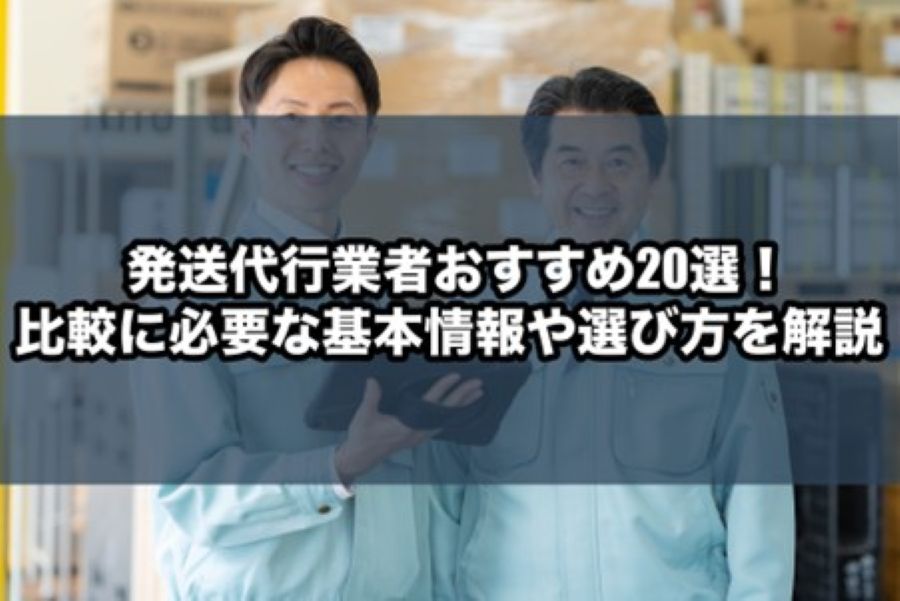







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)