
物流ライター。青山女史短期大学を卒業後、物流会社に14年間勤務。現場管理を伴う、事務職に従事する。その後、2022年にフリーライターとして独立し、物流やECにまつわるメディアで発信。わかりやすく「おもしろい物流」を伝える。

物流業界の人手不足が深刻さを増しています。
背景には、EC市場の拡大による取扱量の増加や、トラックドライバーの高齢化、そして「2024年問題」と呼ばれる労働時間規制の強化があります。
この課題は物流業界だけでなく、荷主企業にとっても無視できないリスクとなりかねません。
この記事では、物流業界における人手不足の現状と原因を整理し、その解決策として注目される物流の効率化について解説します。物流業界の人手不足の現状
物流業界の人手不足は、求職者1人あたりに対し何件の求人があるかを示す「有効求人倍率」に表れています。
厚生労働省の統計によると、自動車運転従事者(トラックドライバーを含む)の有効求人倍率は2025年7月時点で2.78倍に達し、年々上昇しています。全産業平均の1.19倍の2倍以上にあたる数値です。企業が求人を出しても、採用しづらい状況が続いています。
|
職業 |
有効求人倍率 |
|
自動車運転従事者 |
2.78 |
|
全産業平均 |
1.19 |
出典:一般職業紹介状況(令和7年7月分)について_厚生労働省
一方で、国内の輸送取扱量は微増傾向が続いています。特に宅配便の取扱個数は2024年度に50.3億個を突破しました。これは10年前と比べると約1.4倍の水準です。

出典:令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について_令和6年度宅配便等取扱実績関係資料_国土交通省
つまり、物流需要と輸送力のギャップが広がり、輸送力不足が社会的課題になっているのです。多くの企業で従業員が足りておらず、現場が疲弊している状況ともいえるでしょう。
<関連記事>「なぜドライバー不足が加速しているのか、物流崩壊危機の現状と対策」
なぜ物流業界は人手不足なのか

物流業界が慢性的な人手不足に陥っている背景には、いくつかの要因があります。その主な原因は以下の5つです。
- 働き手の高齢化
- 労働生産性の低さ
- 長時間労働と賃金水準の低さ
- 力仕事への懸念
- 2024年問題
働き手の高齢化

日本の社会問題である少子高齢化により、生産年齢人口が年々減少している状況です。人口減少により、新たな働き手の確保が難しく、既存従業員の高齢化が人手不足に陥る原因の一つに挙げられます。
国土交通省の資料によると、現行ドライバーの年齢層の10%が65歳以上、39.8%が50歳〜64歳の年齢構成比となっています。一方、20代以下の若年層は全体の10.5%という結果です。
若手の採用が追いついておらず、現行ドライバーが定年するにつれて、人手不足はさらに深刻化します。
労働生産性の低さ

人手不足の原因の一つに、労働生産性が低いことも挙げられます。物流業界では、空車回送を始めとする積載率の低さが課題のひとつです。
2010年度以降、積載率は40%以下の水準で推移してきました。いわば、トラックの半分以上が空気を運んでいる状態です。ドライバー一人あたりが運ぶ物量を増やし、効率化する取り組みが求められています。
長時間労働と賃金水準の低さ
長時間労働と賃金水準の低さも、物流業界が人手不足に陥っている原因のひとつです。
トラックドライバーの賃金は全産業平均よりも大型トラック運転手で約4%低く、中小型トラック運転手で約14%低い現状にあります。
一方で、労働時間は全職業平均と比較して、大型トラック運転手で月34時間長く、中小型トラック運転手で月31時間長いといわれています。
人手不足を補うためには、労働環境の改善と賃金の向上、ひいては運賃の適正化が欠かせません。
出典:日本のトラック輸送産業の現状と課題2024_全日本トラック協会
力仕事への懸念
物流業界の仕事は、商品の保管〜入出荷準備・配送・荷受け・荷下ろしなどさまざまです。業務のなかには、大量の荷物の積みおろしや長距離運転もあり、体力面で負担が大きい場面は少なくありません。
そのため、体力に自信がない人や女性の場合、物流業へチャレンジしたくとも躊躇してしまうため、新たな働き手の確保が難しい点が挙げられます。
働き手を増やすためには、力仕事をサポートする自動化・機械化へ向けた取り組みを積極的に検討することも大切でしょう。
物流の2024年問題
2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの時間外労働は年間960時間までに制限されました。これにより輸送力はさらに圧迫され、人員不足を補うことが難しくなっています。
従来は長時間労働で支えられていた輸送体制が制度的に維持できなくなり、抜本的な効率化が求められています。詳しくは「2024年問題とは?物流業界の課題に挑む働き方改革とその対応策を解説」の記事をご参照ください。
\富士ロジテックホールディングスは物流の効率化に取り組んでいます/
物流業界の人手不足がもたらす影響
物流業界の人手不足は、物流事業者だけの問題ではありません。輸送が滞れば、私たちの身近な買い物から荷主企業の事業運営まで、あらゆる場面で影響が出てきます。ここでは代表的な2つの影響を見ていきましょう。
- リードタイムの延長
- 物流コストの上昇
リードタイムの延長
時間外労働規制を含む人手不足の影響により、輸送リードタイムが従来より長く設定される傾向にあります。
「翌日配送」が難しくなると、販売機会の損失につながるのはもちろん、在庫を厚めに持たざるを得ず、在庫回転率の悪化によって資金繰りや収益性にも影響が及びます。つまり、物流業界の人手不足は、荷主企業の経営全体に悪影響を及ぼす要因となりえるのです。
<関連記事>「物流業におけるリードタイムとは?短縮のメリットや注意点、方法を解説」
物流コストの上昇
ドライバー確保のための人件費上昇に加え、中継輸送や中継拠点の利用による効率低下が物流コストを押し上げています。
実際に、2024年度の売上高に占める物流コスト比率は5.44%と前年から0.44ポイント上昇しました。荷主企業の利益を圧迫するにとどまらず、商品価格に反映する企業も多く見られるようになってきました。
出典:2024年度物流コスト調査報告書(概要版)の公表 ~売上高物流コスト比率は5.44%~_公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
<関連記事>「物流コストとは?内訳と推移、削減への6つのアイデアを解説」
物流業界全体で進む人手不足の解決策
こうした人手不足の深刻化を受け、物流業界全体ではさまざまな取り組みが進んでいます。
例えば、共同配送やモーダルシフト(トラックから鉄道・船舶へ輸送手段の転換)は、輸送効率を高め、ドライバー1人あたりの負担を減らす取り組みです。
また、女性ドライバーや外国人材の積極採用など、多様な人材の活用も拡大しています。これと並行し、ドライバーの賃金を向上する取り組みも盛んです。
こうした取り組みは中長期的な効果が期待される一方で、物流現場では荷待ちや荷役の非効率さが依然として大きな課題として残っています。
物流業界の人手不足と荷待ち・荷役時間の課題
国土交通省のデータによると、荷待ちがある1運行の平均拘束時間の内訳のうち、約3割が待機や荷役作業に費やされています。倉庫での入出荷処理が滞ることで、ドライバーが運転以外の業務に時間を取られてしまい、走行できる時間が制約を受けています。
2024年問題によって労働時間の上限規制が始まった今、こうした「非効率な待ち時間」を放置すれば、輸送力不足は加速しかねません。国も「荷待ち時間の削減」を重点施策に掲げており、荷主や倉庫に対しても改善責任が課せられています。
このことからもわかるように、物流業界の人手不足問題は運送業界単独では解決が不可能です。倉庫業務の効率化が物流全体のボトルネックを解消するカギとなっています。
人手不足問題を改善する倉庫効率化対策

物流業界の人手不足は、運送会社だけの努力で解決できるものではありません。
とりわけEC市場の拡大により、小口多品種・短納期の出荷が急増しており、倉庫内の荷物を効率的にさばく体制が不可欠です。
倉庫の処理速度が上がれば、限られたトラックバース(積み下ろしをするために倉庫に接車するスペース)を有効活用できるため、トラックの待機時間が減り、物流業界全体の人手不足リスクを和らげることにつながります。
ここでは、そんな倉庫効率化を促進する3つのソリューションを紹介します。
- トラックバース予約システムによる入場予約
- 自動化ロボット・マテハンによる省人化とスループット向上
- WMSによる在庫・出荷管理の自動化
トラックバース予約システムによる荷待ち削減
トラックバース予約システムは、トラックの到着時間をあらかじめ調整・予約できるシステムです。このシステムを導入すれば、ドライバーは倉庫で長時間待機する必要がありません。
荷積み・荷降ろしが計画的に進み、ドライバーの拘束時間を短縮できます。限られた人員でも効率よく便を回せるようになり、人手不足の現場を支える仕組みとして効果的です。
自動化ロボット・マテハンによる省人化とスループット向上
AMR(自律走行ロボット)やAGV(無人搬送車)、自動仕分けシステム、自動倉庫を活用する倉庫が増加しています。ピッキング、搬送、仕分けを自動化し、倉庫内のスループットを向上。荷役時間の短縮が期待できます。
WMSによる在庫管理の自動化
倉庫管理システム(WMS)は、従来はエクセルなどのアナログな手法で行っていた在庫確認やピッキングリストの作成をデジタル化できるシステムです。
在庫状況のリアルタイム把握や、出荷指示の自動化が可能になり、出荷までのリードタイム短縮と作業精度の向上を同時に実現できます。
<関連記事>「物流システムの定義とは?種類や導入メリット、課題を解説」
富士ロジテックの取り組みとEC発送代行
当メディアを運営する富士ロジテックホールディングスは、倉庫業務の効率化に積極的に取り組んでいます。
当社のECセンターでは、自動仕分けシステムT-Sortを導入。また、同システムをピッキングにも活用し、ある現場では10名で行っていた作業が5〜6名で対応可能になりました。
また、自社開発のWMSとクラウドWMSを柔軟に活用し、ECの受注から出荷までを自動化する取り組みも行っています。リアルタイムで出荷指示として取り込み、倉庫の待機時間を減らすことで、出荷準備も迅速に進められる仕組みです。
こうした自動化は、繁閑差にも対応できる体制を実現するだけでなく、ドライバーの待機時間削減や輸送効率の向上にも寄与します。また、荷主企業にとっても、人手不足やコスト上昇リスクを抑えつつ、安定した出荷体制を維持できるという大きなメリットがあります。
富士ロジテックホールディングスのEC発送代行サービスでは、在庫保管から出荷、流通加工、返品対応までを一気通貫で支援が可能です。物流の人手不足に課題を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
FAQ|物流業界の人手不足に関するよくある質問
Q1. 物流業界の人手不足は、いつまで続くのでしょうか?
A. 国土交通省の「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」では、「当面、需要よりも急速に担い手が減少し、「供給制約」への対応が課題」と議論が行われています。
ドライバーの高齢化が進む一方、若手の就業者が増えておらず、労働人口の減少も止まっていません。効率化・省人化への投資が不可欠です。
Q2. 倉庫業界も人手不足といわれますが、本当ですか?
A. 厚生労働省の「職業情報提供サイト(Job Tag)」によると、倉庫作業員(職業コード485)の有効求人倍率は 0.83倍(2025年時点) と、求職者の方が多い状況です。
全国的には「人手不足」とは言い切れませんが、ECの拡大により繁忙期の人員確保が難しいケースもあります。また、業界を問わず日本全体の生産年齢人口が減少する見込みであり、時給も高騰傾向です。倉庫現場でも安定的な人材確保が課題となる可能性があります。
出典:職業情報提供サイト(Job Tag)|倉庫作業員_厚生労働省
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
田中なお
物流ライター。青山女史短期大学を卒業後、物流会社に14年間勤務。現場管理を伴う、事務職に従事する。その後、2022年にフリーライターとして独立し、物流やECにまつわるメディアで発信。わかりやすく「おもしろい物流」を伝える。
タグ一覧
カテゴリー









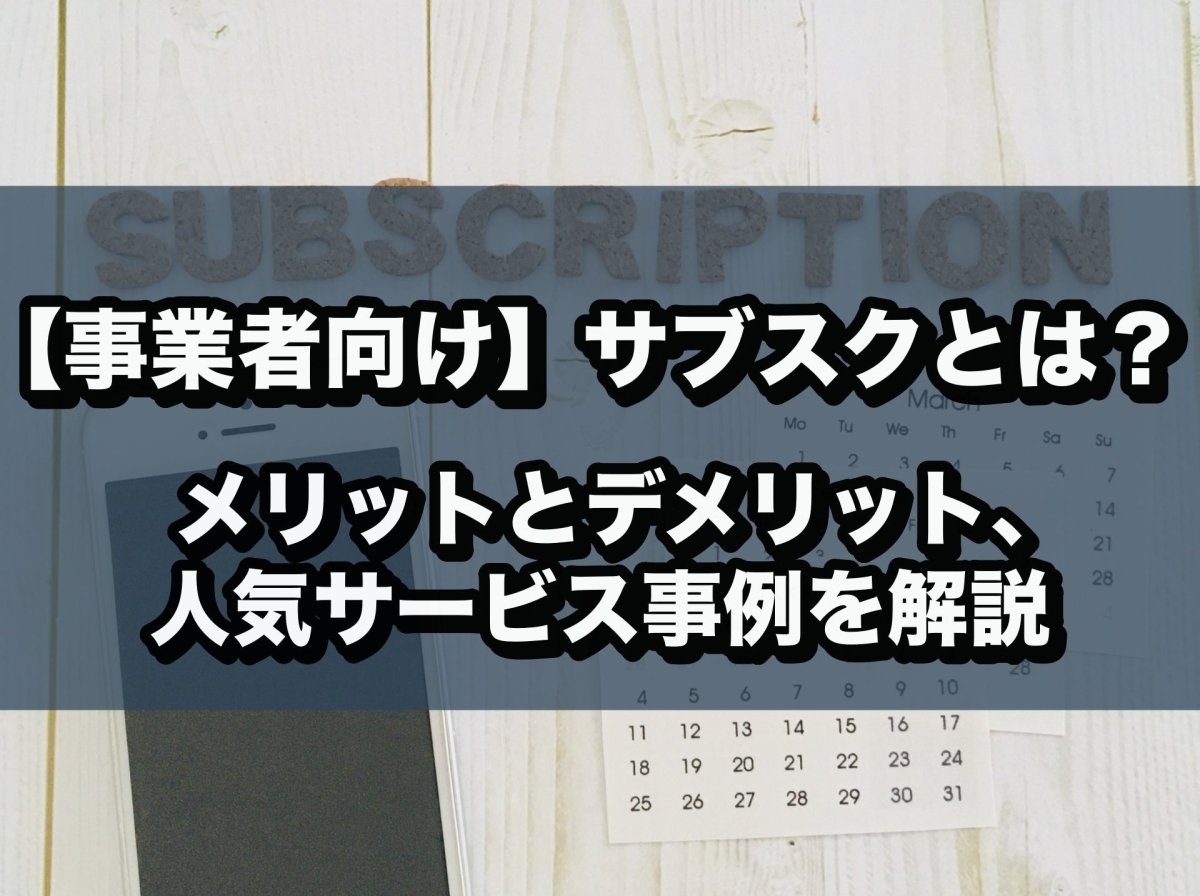
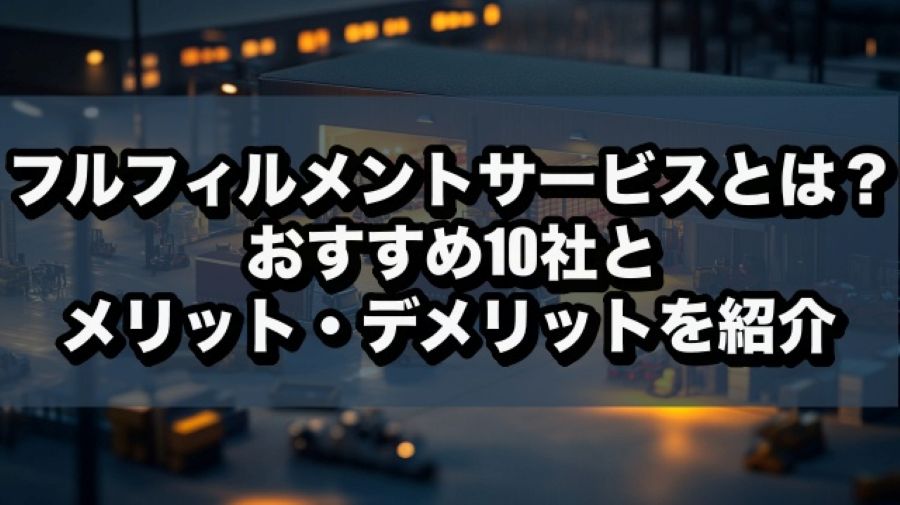
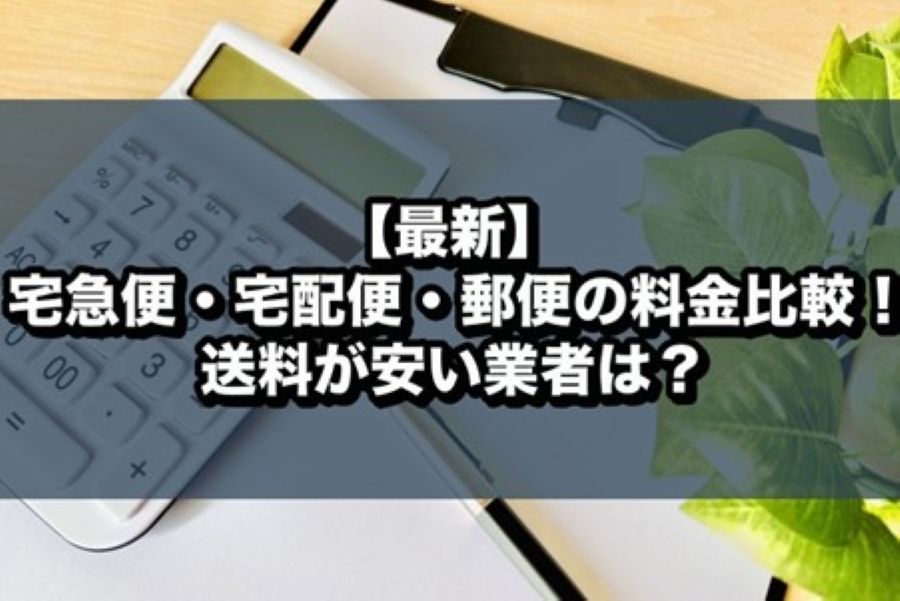
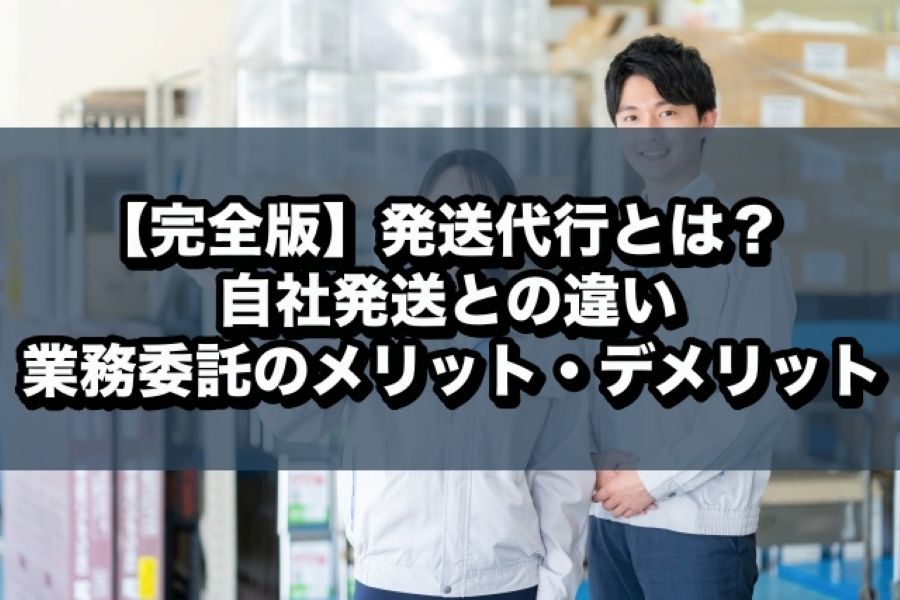

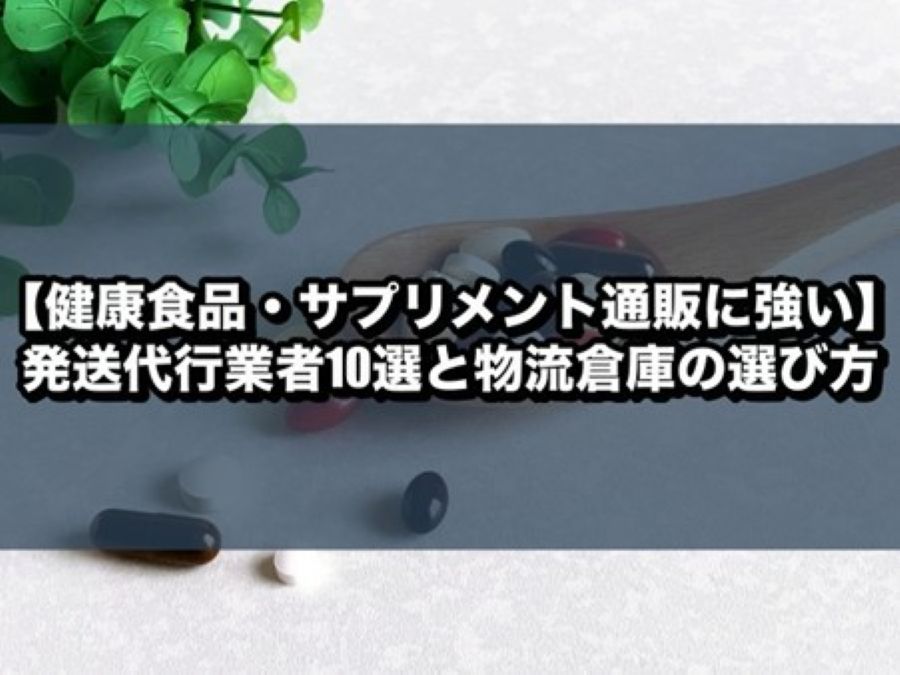
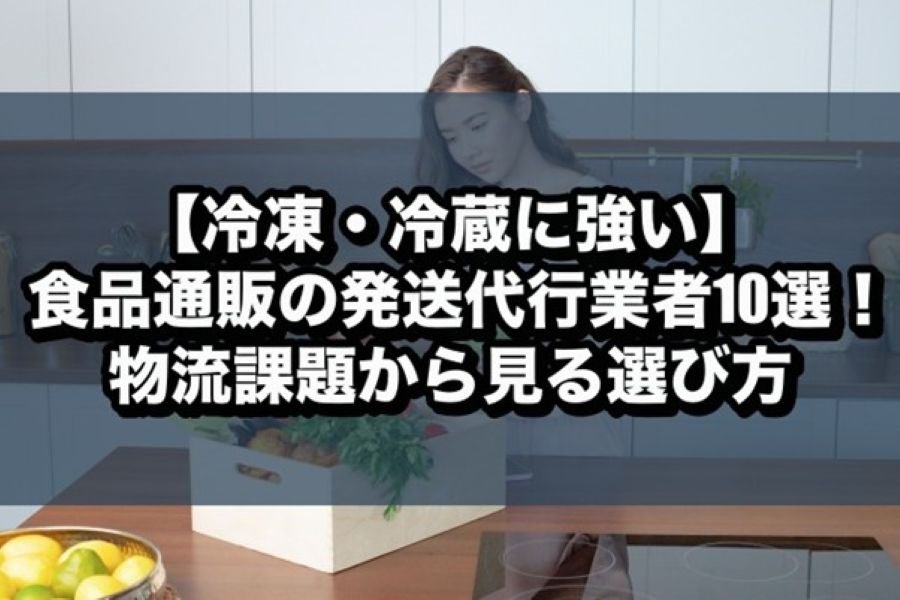








![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)