
物流会社でEC発送代行のバックオフィス業務に従事する複業ライター。好奇心旺盛な性格で、過去に営業職や販売職、医療ソーシャルワーカーなどを経験。豊富な経験を活かして物流、医療・福祉、資格、ライフスタイル記事など幅広い分野の執筆を担当する。カテゴリー問わず、便利で使いやすい商品やサービスを求めて、ネットサーフィンを繰り返す日常を送る。趣味は旅行とレトロモダンなカフェ巡り。

誤出荷は、顧客からの信用を失う要因のひとつです。
「頼んでいない商品が届いた」「商品の賞味期限が切れていた」など、商品の到着を心待ちにしていた顧客の期待を裏切ることになるためです。
誤出荷が起こる要因にはさまざまなケースがあり、発生要因に合わせて対策を行う必要があります。人が担う業務のため、ミスを「0件」にするのは難しいかもしれません。とはいえ、1件でも誤出荷を減らす企業努力は重要な取り組みといえるでしょう。
本記事では、誤出荷が起こる要因や発生リスク、ミスの対策をわかりやすく解説します。
誤出荷のパターン

誤出荷とは、出荷工程にてミスが起こると発生するものです。誤出荷には、次のようにさまざまなパターンがあります。
- 商品間違い
- 数量間違い
- 宛先間違い
- 同梱間違い
1.商品間違い
誤出荷のなかで多くを占めるのが、出荷した商品が受注内容と相違している「商品間違い」です。
単純な商品間違いだけでなく、賞味期限切れ商品・不良品など、出荷基準に満たない商品を発送したケースも含まれます。
また商品間違いは、同一商品内で「カラー」「サイズ」を複数展開している場合に起こりやすいといわれています。
具体的には、ベージュやアイボリーのような、一目で判別できない曖昧なカラーバリエーションの展開をしている場合に取り間違いが起こる可能性が高いため、注意が必要です。
2.数量間違い
顧客が注文した数よりも少なく、もしくは多く出荷してしまう数量間違いも誤出荷のパターンとして挙げられます。発生要因はさまざまで、ピッキングリストの見間違いや数量の思い込みなど、ヒューマンエラーが多い傾向にあります。
特にハンディ―ターミナルを使用していない場合、目視チェックのみとなり、間違いに気付くことが難しいでしょう。
3.宛先間違い
住所を記載した伝票の貼り間違い・作成間違いによって商品が別の住所に届いてしまう宛先の間違いも誤出荷のひとつです。
宛先間違いの多くは「テレコ発送」と呼ばれる2か所の配送先を入れ違うことで起こります。
<関連記事>「テレコの意味とは?物流業界におけるリスクと原因、改善方法も解説」
4.同梱間違い
商品と一緒に入れる同梱物を間違えてしまう誤出荷も発生しやすい事象です。同梱物には商品の付属品やノベルティ、ショップ袋、販促物、プチギフトなど、さまざまな種類が存在します。
同梱物は、注文時期や購入条件によって同梱パターンが変化するため、入れ間違いや入れ忘れが起こりやすいミスのひとつです。
誤出荷が起こる4つの要因
誤出荷は、物流におけるさまざまな工程で起こるミスが要因です。ここからはミスが多く発生するケースを解説します。
- 入荷検品・加工ミス
- ピッキングミス
- 出荷指示ミス
- 梱包ミス
入荷検品・加工ミス
入荷検品・加工ミスとは、商品の入荷時にバーコードの貼り間違いや色間違い、入庫先のロケ番・棚番間違いによって起こるミスです。
たとえば、入庫処理でバーコードの貼り付け作業を行うケースで考えてみましょう。
A商品のバーコードを誤ってB商品に貼り付けた場合、B商品はA商品として管理されます。誤ってA商品と認識されたままロケに入庫されるため、ピッキング作業者が誤りに気付くことは難しくなります。
このように、入荷時点で処理を間違えた場合、商品の管理段階で別の商品と認識されるため、出荷時に誤った商品を発送するリスクが高まりやすくなるのです。
<関連記事>「流通加工とは?その種類と課題、物流倉庫に外注するメリット・デメリット」
ピッキングミス
ピッキングミスは、見た目や商品番号、商品名、サイズ表記が似ている商品があった場合に起こりやすいミスです。ピッキング時は目視確認で行うことが多いため、倉庫内が整理整頓されていない、品番が似ている場合は、特に注意が必要となります。
また、慣れた作業者が対応すると、経験による思い込みが要因となる場合も。ほかには、作業手順を守らない、情報確認を怠るなど、作業者の単独の判断がミスにつながるケースも少なくありません。
<関連記事>「ピッキング作業ミスをなくす10の方法!【倉庫従事者がコツを直伝】」
出荷指示ミス
手入力で出荷処理をしている場合に起こりやすいのが、出荷指示のミスです。いわゆるヒューマンエラーであり、商品コード・数量の入力ミス、特記事項の確認漏れ、ロケ・ロットの指定ミスなど、手作業による処理ミスが要因です。
通常の処理よりも、出荷内容の変更やキャンセルなどのイレギュラー対応時にミスが起こりやすい傾向にあります。
梱包ミス
梱包ミスは、商品梱包時に段ボールに貼り付ける伝票間違い、納品書の入れ間違い、同梱漏れ、同梱間違いによるミスが含まれます。
出荷件数が多いケースなど、伝票を一括で出力している場合、仕分け作業が必要となるため、ヒューマンエラーが起こりやすくなります。
ギフト商品の発送時は、ラッピング漏れや納品書を入れないなど、指定がある梱包を見逃してしまうケースもあるため、注意しましょう。
誤出荷によって生じるリスク

ここからは、誤出荷が起こることで生じるリスクを4つ解説します。
- 個人情報の漏洩リスク
- ブランドへの信用失墜リスク
- コストの増大リスク
- 在庫数の欠品リスク
個人情報の漏洩リスク
顧客の情報を入れ違うテレコ発送が起こった場合、個人情報の漏洩リスクが高まります。送り状・納品書には個人を特定できる氏名、住所、電話番号などの個人情報が記載されているためです。
第三者の手に渡ることで個人情報が悪用されるケースもあり、状況によっては訴訟などの大きなトラブルに発展するリスクがあります。
ブランドへの信用失墜リスク
誤出荷によって、顧客からの信用が低下するおそれがあります。届いた商品が注文と違っていた場合、顧客に返品の対応をしてもらうことになり、大きな負担をかけてしまうためです。
信頼できない企業から、今後商品を買わないと考える顧客も当然いるため、販売機会の損失につながります。誤出荷が続いてしまうと、口コミでの評価が下がり売上が低迷するなど、経営状況が悪化してしまうことも珍しくありません。
特にECサイトは、商品が実際に届いてからでないと商品を確認できないこともあり、届いた商品が異なっていた場合の、信用低下は著しいため注意が必要です。
コストの増大リスク
誤出荷が起こった場合、誤って届けた荷物の回収や再発送にかかる輸送コストが発生します。輸送コストだけでなく、顧客の問い合わせ対応や返品商品の状態確認、発生原因の究明によるコストもかかります。誤出荷によるコスト増加は、運営を続けるうえで軽視できない問題でしょう。
在庫の欠品リスク
受注内容と相違する商品や数量を発送した場合、在庫管理システムと実在庫の数量が異なるため、在庫が欠品するリスクがあります。
倉庫の在庫管理システムとECサイトを自動連携している場合、ECサイト上に反映される在庫数と実在庫数がズレてしまうため、顧客から受注を受けた際に在庫が足りなくなることも。
今後入荷しない商品だった場合、在庫がないことを理由にキャンセル依頼をしなければなりません。顧客に迷惑をかけるだけでなく、販売機会の損失などにつながる大きなリスクとなります。
誤出荷を防ぐ5つの対策

誤出荷の防止には、要因に合わせた対策が必要です。ここからは、誤出荷を防ぐ5つの対策を解説します。
- 誤出荷の原因究明
- マニュアルの見直し・更新
- 作業環境の整備
- システムの導入
- 物流業務のアウトソーシング
1.誤出荷の原因を究明
誤出荷を防ぐ有効な対策の一つ目は、誤出荷の原因究明です。誤出荷を起こった際に、原因を明確にしておくことで、適切な対策が立てられるため同様のミスを防げます。
誤出荷の根本原因の究明には「なぜなぜ分析」が有効です。なぜなぜ分析とは、問題の発生原因を見極める方法であり、原因に対して「なぜ?」の問いを繰り返し、原因の本質を探ります。
一般的には以下のように「なぜ?」を5回ほど繰り返すことで、根本的な原因を見つけられるといわれています。
(なぜなぜ分析:事例)
|
1.なぜ誤出荷したのか? →別の顧客と間違えて送り状を貼ってしまった
2.なぜ貼り間違えてしまったのか? →仕分けセット作業時に取り間違えてしまい、確認を怠ってしまった
3.なぜ確認を怠ったのか? →1人対応していたため、ダブルチェックができなかった
4.なぜ1人で対応しなければならなかったのか? →配置人数が1人だった
5.なぜ配置人数が1人だったのか? →繁忙期で人員が足りず、1人体制にしてしまった
<導き出された対策> →「人員を確保し、1人で行う作業をなくす」 「ダブルチェックが出来る体制を整える」などが考えられる |
なぜなぜ分析を行う場合、責任者だけで考えてしまうと、机上の空論になる可能性があります。実際に作業を行った従業員と一緒に考えることで、実情に合う改善策を検討できるでしょう。
2.マニュアルの見直し・更新
マニュアルの見直し・更新も有効な対策の一つに挙げられます。使用マニュアルが古い場合、実際の作業に見合っていないケースが多いためです。
ミスの発生を防ぐには、マニュアルの定期的な見直しが有効です。半年に一度、年に一度など定期的に作業内容を見直す機会を設け、誤出荷が起こる前に運用手順を整理しましょう。
ただし、適切なマニュアルの用意があっても従業員が手順を守らなければ意味がありません。ルール遵守の意味・必要性を理解してもらうために、従業員への定期的な教育を続けることも重要です。
<関連記事>コンプライアンス研修などの実施が有効です。
3.作業環境の整備
作業環境の整備は、テレコ発送などのミス防止に有効な対策です。倉庫内の作業スペースが狭い、モノで溢れているなど、作業環境が整理されていない状態は、商品の紛失や商品の取り間違いにつながりやすいためです。
整理整頓により、ピッキングした商品をわかりやすく一時保管できるため、商品や伝票が混ざるリスクが低下します。
また、作業環境が整っていると、在庫管理もスムーズになるため、作業効率向上にもつながるでしょう。
4.システムの導入
誤出荷防止をするためのシステム導入も有効な対策のひとつです。特に出荷指示を手作業で行っている場合には、大幅な業務改善ができる可能性があります。
たとえば、注文情報と連携できるWMS(在庫管理システム)を導入した場合、自動連携できるOMS(受注管理システム)を選択すれば、注文データを手作業で加工する必要がなく、ヒューマンエラーによる誤出荷のリスクが大幅に低下します。
誤出荷を防ぐだけでなく、在庫管理もシステム化できるため、作業効率の向上にもつながるでしょう。
5.物流業務の外部委託
自社物流で誤出荷が減らない場合、物流業務をまるっと外部に委託する手段も有効です。物流のプロが保有するノウハウや経験により、誤出荷の根本的な発生原因を見つけられ、適切な対策が取れるためです。
委託によって、EC事業の運営企業は誤出荷が発生する悩みから解放され、本来のコア業務に専念できるなどのメリットも。
ただし、アウトソーシング先を検討する際は、自社の取り扱う商品と相性のよい企業を選ぶことが大切です。経験や実績、拠点、対応力、金額などを複数社で検討するとよいでしょう。
<関連記事>「発送代行の選び方が5分でわかる!料金相場や個人で使えるサービスも紹介」
誤出荷への対策は物流アウトソーシングの利用が近道

誤出荷の発生は、企業の信用低下や個人情報の漏洩など、トラブルに発展するリスクが伴うなど、企業にとって解決すべき課題の一つです。
とはいえ、物流業務は手作業で担う部分も多く、出荷ミスを0件にするのは難しいでしょう。しかし、適切な対策によって発生件数は減らせます。原因を究明し対策を講じ続けることが重要です。
自社物流での対応に限界を感じている場合は、物流の専門家に委託する方法も有効です。
富士ロジテックホールディングスは100年以上の歴史を持つ総合物流会社です。10年以上のEC物流の実績があり、豊富なノウハウを保有しています。さまざまな課題解決の提案も行っており、業務効率化・コスト削減へ向けたサポートが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
梅山茜
物流会社でEC発送代行のバックオフィス業務に従事する複業ライター。好奇心旺盛な性格で、過去に営業職や販売職、医療ソーシャルワーカーなどを経験。豊富な経験を活かして物流、医療・福祉、資格、ライフスタイル記事など幅広い分野の執筆を担当する。カテゴリー問わず、便利で使いやすい商品やサービスを求めて、ネットサーフィンを繰り返す日常を送る。趣味は旅行とレトロモダンなカフェ巡り。
タグ一覧
カテゴリー


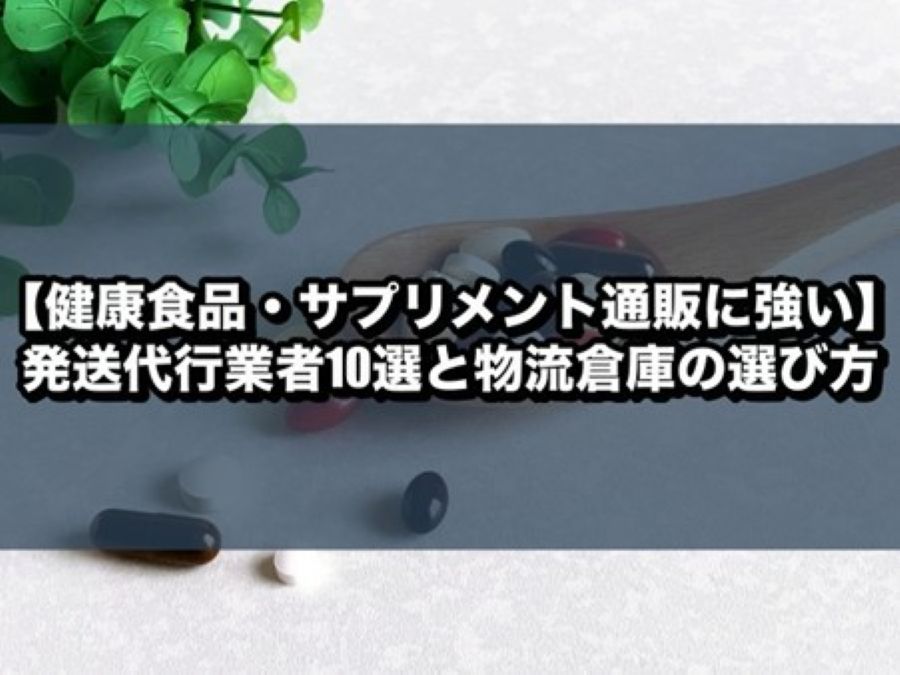
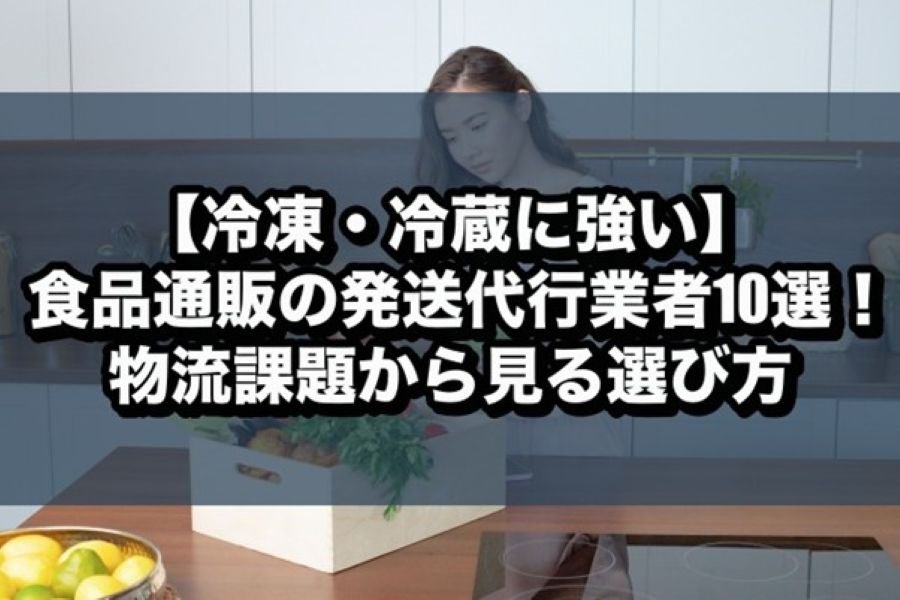

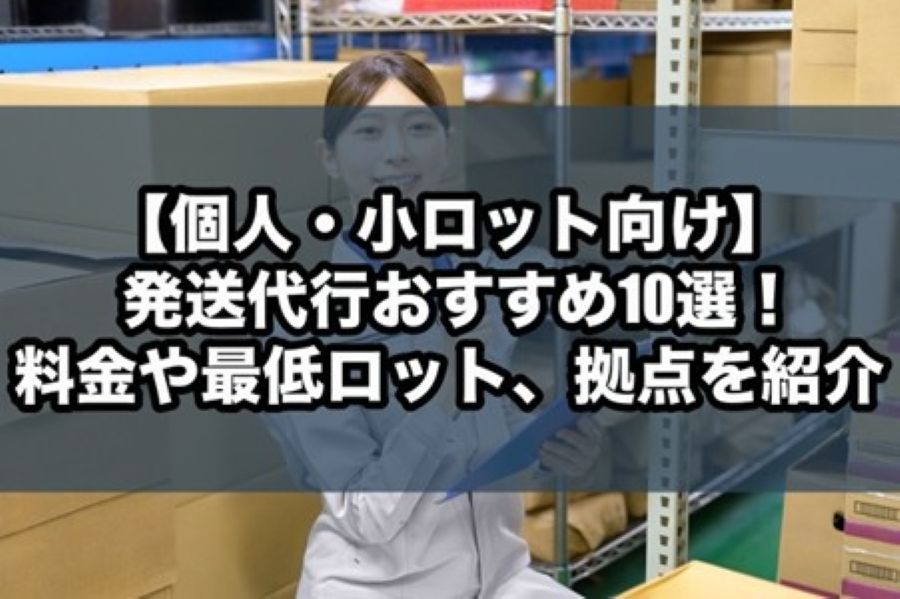
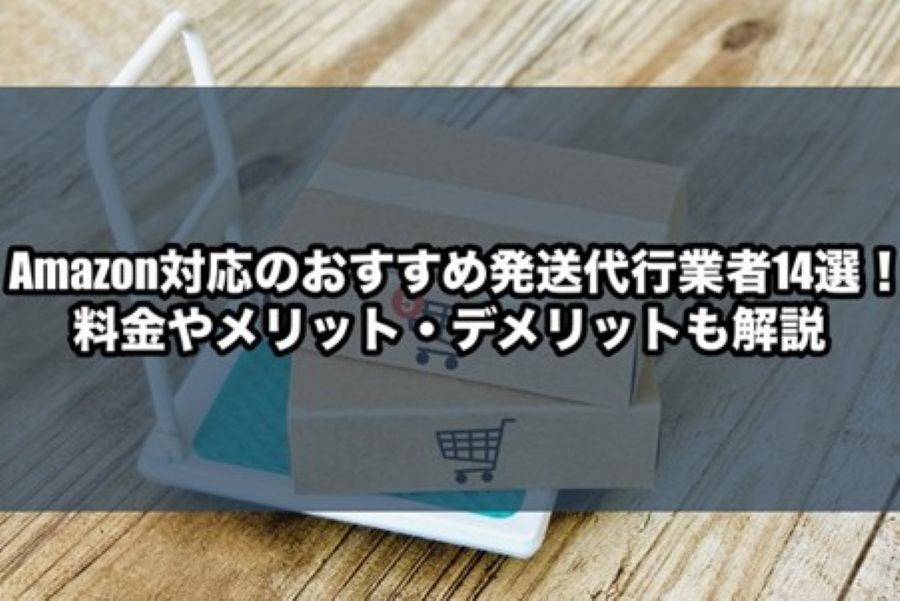
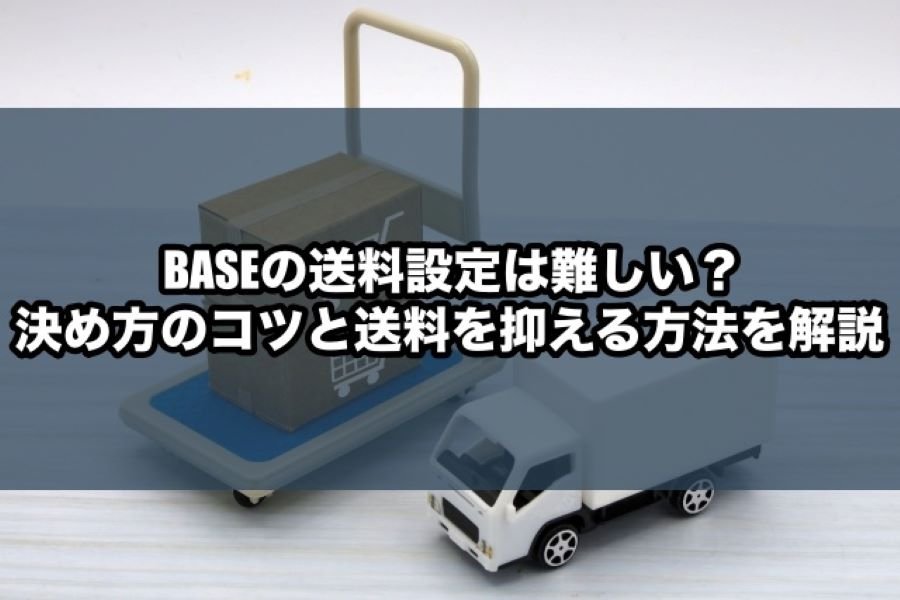
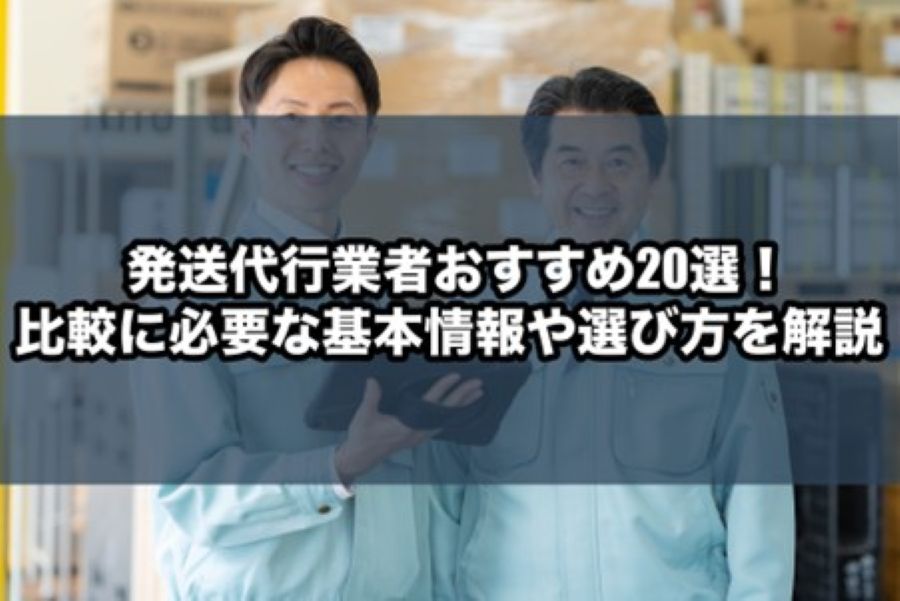








![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)