
物流業界歴15年以上。港湾の職業訓練校卒業後、港湾荷役作業会社にてRORO船等への本船荷役に従事。フォークリフト、クレーン運転士、大型特殊など現場必須の資格を多数所持。Amazonのセラーとして出品経験あり。長年の経験と専門知識を活かし、現場目線でのリアルな記事執筆が得意。物流以外に自動車関連の執筆実績も多数。

「物流業務委託先の選び方がわからない」「物流コストを削減したい」「季節波動などによる物量の変動に対応できる体制を整えたい」
これから事業をはじめるスタートアップの方や、現在の物流業務を改善したい企業の物流担当者の中には、上記のような悩みを持つ方も多いと思います。
ひとくちに物流倉庫と言っても、「立地」「機能」「サービスの範囲」など、それぞれ特性が異なるため、そう思うのは当然です。
そこでこの記事では、物流倉庫で10年以上実務に従事する筆者が、失敗しない物流倉庫の選び方を解説します。
あなたの企業やブランドにとって最適な物流倉庫がどういったものなのかを理解し、失敗のリスクを最小限に抑えましょう。
物流倉庫選びが重要な理由

令和3年に国土交通省より発表された『総合物流施策大綱(2021年~2025年)』では、「物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化(簡素で滑らかな物流)」として、国内における物流の進化を強く推進しています。
出典:総合物流施策大綱(2021年~2025年)概要|国土交通省
そのことからもわかるように、物流倉庫は単なる「保管場所」から、企業の競争力を左右する「サプライチェーンの戦略拠点」へと進化しました。
保管だけでなく、在庫管理、流通加工、迅速な配送といった機能は、顧客満足度や売上に直結します。
裏を返せば、物流倉庫選びに失敗すると、大きな損失を被る可能性があるということです。
例えば、コスト面のみで選定し委託した結果、「キャパシティが小さく繁忙期の保管、出荷が追いつかない」といった外注の失敗は少なくありません。それに伴い、出荷漏れや在庫ズレのミスが頻発し、販売機会損失や顧客満足度の低下、ブランドイメージの損失につながってしまうおそれがあります。
そうなれば倉庫移転をしなければならず、余計な出費と手間がかかり、事業発展の妨げとなることでしょう。適切な倉庫選びは、重要な経営判断なのです。
失敗しない物流倉庫の選び方|9つの比較ポイント

ここからは、実際に物流倉庫を選ぶ際、比較検討するうえで重要となる9つのポイントを紹介します。
- 選び方1.『商材特性と倉庫の物理的条件』
- 選び方2.『物量と変動性』
- 選び方3.『提供サービス』
- 選び方4.『立地』
- 選び方5.『料金体系とコスト構造』
- 選び方6.『自動化』
- 選び方7.『セキュリティ体制とリスク管理』
- 選び方8.『運用実績と専門性』
- 選び方9.『サポート体制と柔軟性』
選び方1.『商材特性と倉庫の条件』:保管・取り扱いの特殊要件を把握する
はじめに確認すべきは、自社の商材を保管や取り扱いの対象としている倉庫であるかどうかです。
いくら立地やコスト面で魅力的な倉庫でも、自社の商材を取り扱えなければそもそも委託できません。
商品にはそれぞれ適切な保管条件や法的な規制があり、それを満たせない倉庫では品質劣化や法令違反のリスクがあります。例えば、冷凍食品なら冷凍設備が、医薬品なら薬機法に準拠した管理体制と薬剤師の配置が必須です。
さらに、預ける商品の品質を維持するためには、倉庫内の環境が適切に保たれていることが大前提です。温度や湿度の管理はもちろん、清掃が行き届き、整理整頓されているか、害虫や埃などから商品を守る対策が取られているかを確認します。
特に食品や医薬品、精密機器などデリケートな商品を扱う場合、倉庫の環境が商品価値を損なうリスクがないか、厳しくチェックする必要があります。
自社の商材特性を正確に伝え、対応可能かしっかり見極めましょう。
【確認すべきポイント】
- 取り扱い可否:自社の商材カテゴリー(食品、アパレル、化粧品、危険物など)の取り扱い実績と受け入れ可能かどうか。
- 温度・湿度管理:必要な温湿度帯(常温、定温、冷蔵、冷凍、湿度管理)と、その管理体制は整っているか。
- 5S(整理・整頓・清潔・清掃・しつけ)の状況:倉庫内(床、棚、作業場、トイレ等)の清掃や、整理整頓が徹底されているか。
- 防塵・防虫・防鼠対策:具体的な対策(防虫灯、トラップ、駆除業者点検等)が実施されているか。
- 法的要件・特殊要件:関連法規(消防法、食品衛生法、薬機法等)に基づく許認可があるか。
<関連記事>「化粧品の在庫管理における5つの基本!課題解決に向けたシステムも解説」
選び方2.『物量と変動性』:波動への対応力を見極める
次に物流倉庫の選び方として重要なのは、自社の物量、特に季節やセール時期による「物量の変動(波動)」に倉庫が対応できるかです。
通常時の物量をさばけても、ピーク時に保管スペースや作業能力が不足すれば、出荷遅延や機会損失につながります。
年間を通じて安定した物流サービスを受けるためには、倉庫のキャパシティと波動への対応力を把握することが不可欠です。
事前に物量の現状と予測、変動パターンを具体的に伝えることが重要となります。
【確認すべきポイント】
- 設備、保管スペース:ピーク時の物量に対応可能な「設備やスペース」が備わっているか。
- 人員体制:ピーク時の物量をさばける「人材の確保」が可能か。
- 変動対応力:セールなどの短期的な変動だけでなく、事業成長も含めて柔軟に対応できるか。
- 対応実績:同様の物量変動を持つ企業の対応実績があるか。
選び方3.『提供サービス』:委託したい業務範囲を確認する
物流倉庫に委託できる業務は、基本的な入出荷・保管から、複雑な流通加工、システム連携、返品処理まで多岐にわたります。
自社がどの業務をどこまで委託したいのかを明確にし、倉庫側がその範囲を必要な品質レベルで提供できるかを確認することが重要です。
特にEC事業者にとっては、受注システムとの連携や、ギフトラッピングなどの流通加工、煩雑な返品処理への対応力が、業務効率と顧客満足度を左右します。
【確認すべきポイント】
- 基本業務の範囲と品質レベル:入庫、検品、保管、ピッキング、梱包、出庫、在庫管理、返品などの対応範囲と、その品質が自社のニーズに応えられるか。
- 流通加工の対応力:ラベル貼り、セット組、組立、ギフト対応など、必要な加工への対応範囲とその品質が自社のニーズに応えられるか。
- システム連携:自社システムと倉庫WMSとの連携は可能か。
<関連記事>「EC物流とは?仕組みや課題、解決策としておすすめの代行業者を10社紹介」
<関連記事>「発送代行サービスとは?依頼できる業務とおすすめ代行業者23選を解説【2025年版】」
選び方4.『立地』:輸送効率とコストを最適化する場所を選ぶ
倉庫の所在地は、顧客への配送リードタイムと輸送コストに直接的な影響を与えます。
主要な配送エリアや仕入れ先からの距離、高速道路ICや港湾・空港へのアクセスなどを考慮し、効率的でコストメリットのある立地を選ぶことが重要です。
|
「生産立地型」と「消費立地型」 ● 生産立地型:工場など製品を作る場所の近くに倉庫を置きます。メリットは原材料を効率よく集められることです。食品加工メーカーや製造業に多く選ばれます。 ● 消費立地型:お客様やお店など、製品が最終的に届けられる場所の近くに倉庫を置きます。メリットは、注文から配達までの時間を短縮できることです。リードタイムを短縮したいEC事業者や生鮮食品業者に選択されます。 |
また、近年注目されるBCP(事業継続計画)の観点からは、自然災害のリスクが低いエリアを選ぶ、あるいは複数拠点に分散するといった戦略も有効になります。
自社のサプライチェーン全体を見渡し、最適な場所を選定しましょう。
【確認すべきポイント】
- 配送エリアとの関係:主要顧客への配送リードタイム、時間指定などのサービスレベルに対応可能か。
- 輸送インフラへのアクセス:主要幹線道路、高速IC、港湾、空港、鉄道駅へのアクセス状況は自社流通に最適か。
- BCP(事業継続計画)観点:ハザードマップ等による自然災害リスクは許容し得る範囲か。
|
BCP(事業継続計画)とは 自然災害、感染症のパンデミック、大規模システム障害など、予期せぬ事態が発生した場合でも、事業を継続または早期に復旧させるための計画のことです。 具体的には、ハザードマップを活用した災害時避難経路の確保や、WMSなどの重要データのバックアップ、システム復旧手順などが挙げられます。 |
<関連記事>「物流拠点を最適化する方法とは? ポイントや取り組み事例を解説!」
選び方5.『料金体系とコスト構造』:透明性と費用対効果を比較検討する
おそらく物流倉庫を探している多くの荷主企業が「コスト」を最重要視して考えていると思います。物流倉庫を選ぶうえで、料金体系の透明性は不可欠です。
倉庫会社によって「坪貸し」「個建て」など料金体系はさまざまであり、保管料、荷役料、配送料など、多くの費用項目があります。
|
倉庫利用料の料金体系 ● 坪建て: 倉庫の利用スペース(坪または平米)に応じて賃料が設定されるモデル。 ● 個建て: 保管する商品やパレットの個数など、特定の単位ごとに料金が設定されるモデル。 ● 従量課金: 入庫件数、出庫件数、ピッキング件数、梱包箱数など、実際に行った作業量や物流量に応じて料金が変動するモデル。 |
見積もりを比較する際は、前提条件を揃え、全ての費用項目を含めたトータルコストで評価することが重要です。
また、単に安いだけでなく、提供されるサービス品質に見合った価格か、費用対効果を冷静に見極める必要があります。
【確認すべきポイント】
- 料金体系:「坪建て」「個建て」「従量課金」など、どの料金体系か。自社の商材とマッチするか。
- 見積もりの明確性:各項目が分かりやすく記載されているか。 不明瞭な点はないか。
- 隠れコスト:初期費用、最低保証料金、システム関連費、イレギュラー対応費、棚卸し費用等の説明はあるか。
- 費用対効果:トータルコストと、提供されるサービス品質(スピード、正確性、柔軟性等)のバランスは良いか。
<関連記事>「物流倉庫の費用を徹底解説!固定費・変動費の相場とコストを抑える5つの具体策」
選び方6.『自動化』:ロボットや自動化設備の導入に積極的か確認する
倉庫の自動化やロボットの導入が進んでいるかどうかも、重要な判断材料となります。
ロボットや自動化で効率化されている倉庫は、少ない人数で多くの物量をさばくことができるため、荷主のニーズに柔軟に対応できる可能性が高いからです。
例えば、自動化が進んだ物流倉庫を選んでおけば、将来人手不足が進んだ際、「人手が確保できず対応できない」「人件費が上がり、作業料も値上げしなければならない」などといった、リスクを回避できます。
また、ロボットの導入や自動化設備を導入している物流倉庫は24時間365日稼働しているところも多いことから、配送リードタイムの短縮や最大取り扱い物量の面でメリットが大きいです。
【確認すべきポイント】
- AGV(自律走行型運搬車両)やAMR(自律移動ロボット)などのロボットの導入:作業員の負担を軽減し、倉庫の効率化を実現しているか。
- WMS(倉庫管理システム)の導入:事務手続きやピッキングの作業効率の向上に加え、ヒューマンエラーを最小化できているか。
選び方7.『セキュリティ体制とリスク管理』:預けた商品を守る対策を確認する
預けた商品や顧客情報を盗難、破損、火災、情報漏洩といったさまざまなリスクから守るため、倉庫のセキュリティ体制を確認することは重要です。
侵入対策や監視体制、システムへのアクセス管理といった情報セキュリティ対策、そして火災や地震への備えである防災設備まで、多角的にチェックし、自社の求めるセキュリティレベルを満たしているかを確認する必要があります。
また、倉庫企業のBCP(事業継続計画)が、自社のBCPと整合性がとれているか確認しておくべきです。
【確認すべきポイント】
- セキュリティ対策:監視カメラ、入退室管理システム、警備体制(機械/有人)、施錠管理が徹底されているか。
- 情報セキュリティ:システムアクセス権限管理、不正アクセス対策、データバックアップは万全か。
- 防災設備:消火設備(スプリンクラー等)、火災報知器の設置・点検、建物の耐震性、水害対策ができているか。
- BCP(事業継続計画): 非常時の対応計画が用意されているか。
- 保険:万が一の場合の補償範囲と、倉庫側加入保険の内容は十分か。
選び方8.『運用実績と専門性』:信頼できる経験とノウハウの有無を確認する
物流業務は、業界や商材によって求められる知識やノウハウが異なります。
自社と類似する商材の運用実績が豊富な倉庫会社は、業務への理解が深く、的確な提案やスムーズな運用が期待できます。
例えば、アパレルを取り扱う場合には、検針や専門性の高い流通加工(セット組・プレス加工・補修等)、詳細な在庫管理、返品対応などが必要になります。実績があれば、安心して任せられるでしょう。
また、確立された品質管理体制や、継続的な改善活動(カイゼン)を行っているかどうかも、その倉庫の専門性と信頼性を測る上で重要な指標となります。
長期的なパートナーとして安心して任せられるかを見極めましょう。
<関連記事>「アパレル物流とは?特徴と課題、おすすめの物流会社3選」
【確認すべきポイント】
- 類似実績:自社の業界・商材での具体的な取り扱い実績(期間、規模、事例)があるか。
- 品質管理体制:品質目標(KPI)管理や、マニュアルが整備されているか。
- 改善活動:業務効率化や品質向上のための具体的な改善活動(5S、QCサークル等)の実績はあるか。
- 専門知識:商材や関連法規に関する専門知識を持つ担当者の在籍、教育体制は整っているか。
- 企業の安定性:創業年数、企業規模、財務状況(可能な範囲で)から安定感はありそうか。
選び方9.『サポート体制と柔軟性』:円滑な連携と緊急時への対応力を計る
物流業務を外部委託する上で、倉庫会社との日々のコミュニケーションが円滑に行えるかは非常に重要です。
報告・連絡・相談がスムーズにでき、問題発生時には迅速かつ的確に対応してくれる体制が整っているかを確認しましょう。
また、ビジネスの変化に応じて、緊急出荷やスポット的な依頼、業務プロセスの変更などに柔軟に対応してくれるかどうかも、長期的なパートナーシップを築くうえで欠かせない要素です。
【確認すべきポイント】
- コミュニケーション体制:専任窓口の有無、連絡手段とレスポンス速度、こまめに報告をくれるか。
- トラブル対応力:問題発生時の報告・対応フロー、原因究明・再発防止策の提案能力があるか。
- 柔軟性:緊急出荷、スポット作業、業務カスタマイズへの対応は可能か。また、スピ―感はあるか。
- 担当者の姿勢:相談のしやすさ、提案力、信頼感、相性。
ここまで物流倉庫選びで重要となる9つのポイントをご紹介しました。
数ある物流企業のなかでも、「富士ロジテックホールディングス」はこれらのポイントを押さえた総合物流企業です。
AGV(自律走行型運搬車両)を採用している最新の物流倉庫から、医薬品など専門的な知識と設備が必要な倉庫の運営など、荷主様のさまざまなニーズに応えます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
物流倉庫選定チェックリスト(10項目)

前項でお伝えした物流倉庫の選び方をまとめて、比較検討に役立つチェックリストを作成しました。
各項目を評価し、候補倉庫の比較にお役立てください。
□ 拠点は輸送ニーズ/顧客ベースに合致するか?(立地)
□ 必要な全サービス(特殊要件含む)を提供しているか?(サービス範囲)
□ 物量の波動に対応できるか?(キャパシティ)
□ 価格体系は透明かつ競争力があるか?(コスト)
□ 同様製品/業界での取り扱い経験はあるか?(経験・専門性)
□ 効率化のためのロボット技術(AGVなど)/システム(WMSなど)を活用しているか?(技術力)
□ サポート体制と対応速度は十分か?(サポート)
□ ビジネスの変動(成長/市場変化)に適応できるか?(柔軟性)
□ 十分なセキュリティ対策が講じられているか?(セキュリティ)
□ 具体的な品質管理プロセスが構築されているか?(品質)
物流倉庫を選ぶ3つのコツ

物流倉庫を選ぶ際、以下の3つのコツを意識すれば、失敗のリスクを減らすことができます。
- 『倉庫現場の見学』は必須
- 『複数社比較』と『相見積もり』の徹底
- 『契約内容』の細部確認と『担当者との連携』
コツ1:『倉庫現場の見学』は必須
大事な商品を任せられるかどうかは、比較対象の倉庫へ足を運び、現場の「空気感」を体感して確認しましょう。
資料やWebサイトだけでは、実際の雰囲気や状況は把握しきれません。
具体的なチェックポイントは以下の通りです。
- 5S(整理・整頓・清潔・清掃・しつけ)が徹底されているか:しっかりと整理整頓されていれば、管理が行き届いている証拠です。
- スタッフの雰囲気は良いか:スタッフの覇気や服装の乱れは現場に行かなければ知り得ません。
- 作業品質と管理のレベルは高いか:実際の作業を見て作業品質を確認します。(例:ピッキングの様子や検品の手順など)また、温度・湿度の管理体制も確かめておきましょう。
「百聞は一見に如かず」の精神で足を運び、自らの五感で確かめることが重要です。
コツ2:『複数社比較』と『相見積もり』の徹底
物流倉庫を選ぶ際は、必ず複数の倉庫を比較検討します。
比較対象がいないと、その倉庫のサービスや価格が適正なのか判断できません。
最低でも3社程度の倉庫から資料を取り寄せ、提案を受け、比較検討することをおすすめします。時間と手間はかかりますが、最適なパートナーを見つけるためには欠かせないプロセスです。
前項で提示した10項目のチェックリストを参考にしていただき、サービス、品質、コスト、担当者との相性などを総合的に評価し、最も費用対効果の高いパートナーを選びましょう。
コツ3:『契約内容』の細部確認と『担当者との連携』
契約を結ぶ前には、契約内容の隅々まで確認することが不可欠です。
また、契約後のスムーズな業務連携のため、担当者とのコミュニケーション体制を明確にしておく必要もあります。
具体的には、契約期間、料金詳細、免責事項、解約条件等は必ず確認してください。
他にも、日々連絡を取り合う方法(電話、メールなど)や定例会議の有無など、担当者との連系方法も合わせて確認しておくことをおすすめします。
物流を外部委託するメリットとデメリット

物流業務を外部委託することには、メリットとデメリットが存在します。
- 物流を外部委託する『メリット』
- 物流を外部委託する『デメリット』
それぞれを把握し、判断材料にしてください。
物流を外部委託する『メリット』
物流の外部委託は、あなたの企業やブランドにさまざまなメリットをもたらします。
- コスト最適化:初期投資を削減し、固定費の変動費化を実現する。
- コア業務へのリソース集中:営業や仕入れ、製造などに注力できる。
- 物流品質の向上:物流業者の専門ノウハウ活用で、結果的に顧客満足度向上につながる。
- 波動への柔軟な対応:物量の増減による在庫リスクや機会損失を防げる。
物流を外部委託する『デメリット』
物流の外部委託は多くのメリットがある一方で、一部の企業やブランドにとってデメリットとなるポイントも存在します。
- 情報漏洩リスク:商品や顧客の情報が漏洩する可能性があります。情報セキュリティを徹底している物流業者と契約することで、リスクを最小限に押さえることが可能です。
- 社内ノウハウ蓄積の停滞:物流業務に関する知識の積み上げができません。丸投げするのではなく、関心を持ち知識を深めることが重要です。
- 委託先への依存リスク:物流業務を外部委託に依存していると、委託先に問題があった際、即座に対応できなくなります。トラブルシューティングを徹底しましょう。
- コミュニケーションコストの発生:委託先担当者とのやり取りにリソースを使います。システムの活用などで対処可能です。
メリットとデメリットを考慮し、あなたの企業やブランドにとって最適な選択をしてください。
外部委託なら「富士ロジテックホールディングス」がおすすめ!

本記事では、物流業務の委託先をお探しの方に向けて、物流倉庫の選び方を解説しました。
失敗しない具体的な選び方のポイントは以下の9つです。
- 選び方1.『商材特性と倉庫の物理的条件』
- 選び方2.『物量と変動性』
- 選び方3.『提供サービス』
- 選び方4.『立地』
- 選び方5.『料金体系とコスト構造』
- 選び方6.『自動化』
- 選び方7.『セキュリティ体制』
- 選び方8.『運用実績と専門性』
- 選び方9.『サポート体制と柔軟性』
信頼できる物流パートナーをお探しなら、上記のポイントを押さえた富士ロジテックホールディングスにぜひ一度ご相談ください。
富士ロジテックホールディングスの強み
- 100年を超える歴史で培ったノウハウと実績
- 精密機器から医薬品、大型のアウトドア用品まで、さまざまな商材に対応可能
- さまざま波動に柔軟に対応
- 入庫からラストワンマイルまで一貫した物流業務の委託が可能
- 東京、神奈川、静岡、名古屋、大阪、奈良、福岡のエリアを中心に全国対応可能
- 「AMR(自立走行搬送ロボット)」など最新のテクノロジーを活用
- 地域と空き状況によっては最新の物流施設にも入居可能(アルファリンク相模原、DPL福岡など)
適切な物流パートナー選びは、企業やブランドの収支や顧客満足度、ブランドイメージに直結します。
本記事で解説したポイントを押さえて、あなたの企業やブランドにとって最適な選択をしてください。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
イノウエ
物流業界歴15年以上。港湾の職業訓練校卒業後、港湾荷役作業会社にてRORO船等への本船荷役に従事。フォークリフト、クレーン運転士、大型特殊など現場必須の資格を多数所持。Amazonのセラーとして出品経験あり。長年の経験と専門知識を活かし、現場目線でのリアルな記事執筆が得意。物流以外に自動車関連の執筆実績も多数。
タグ一覧
カテゴリー


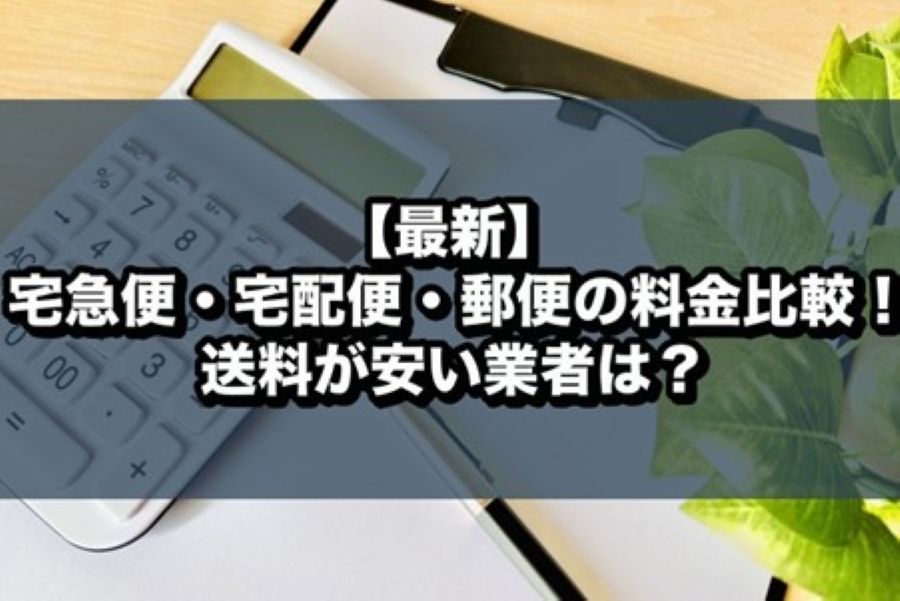
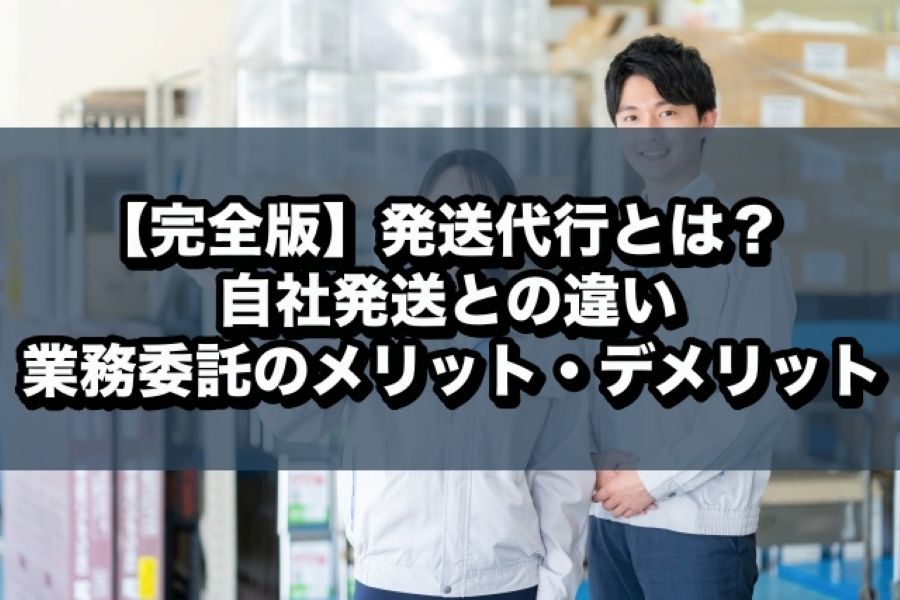

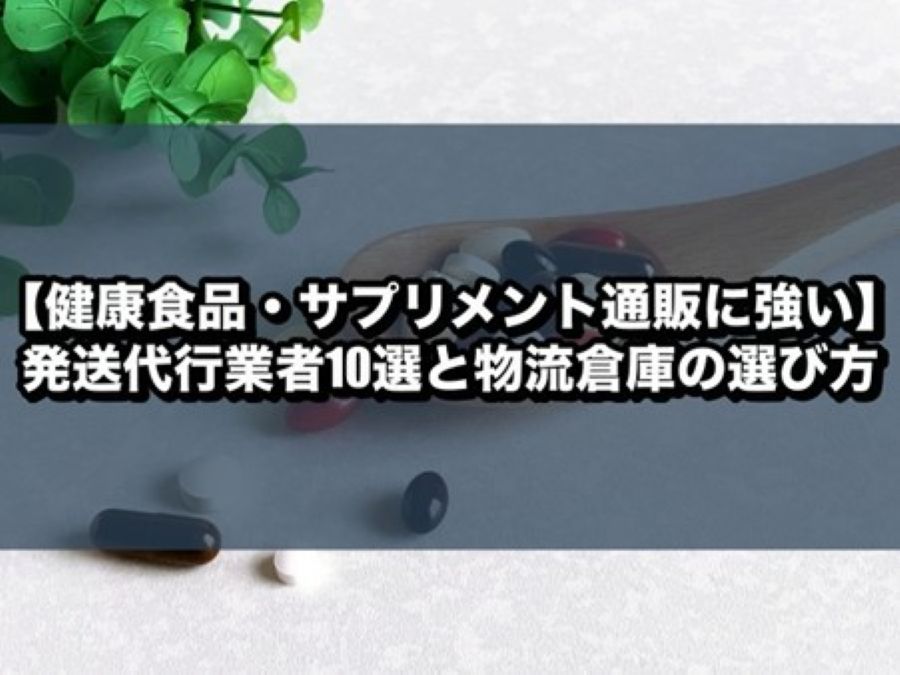
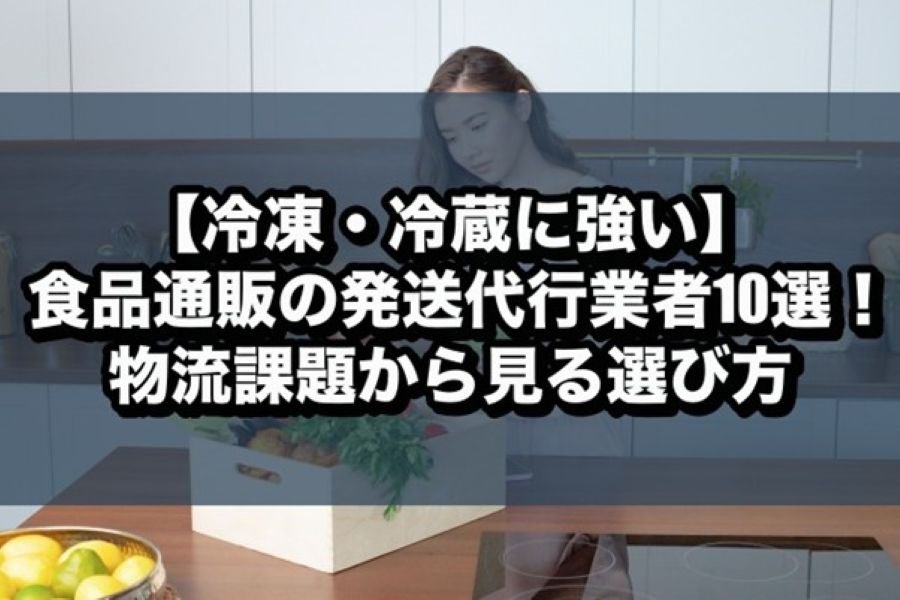

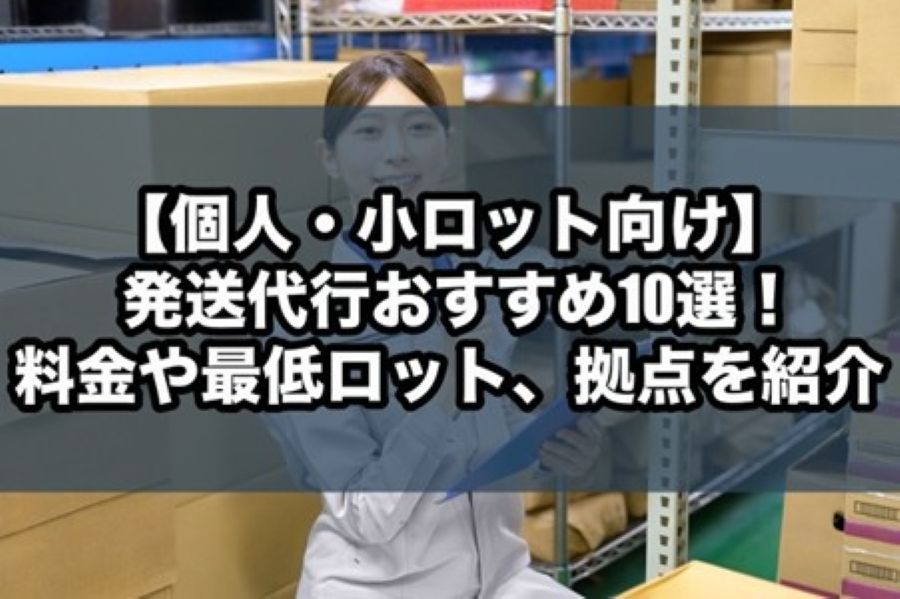
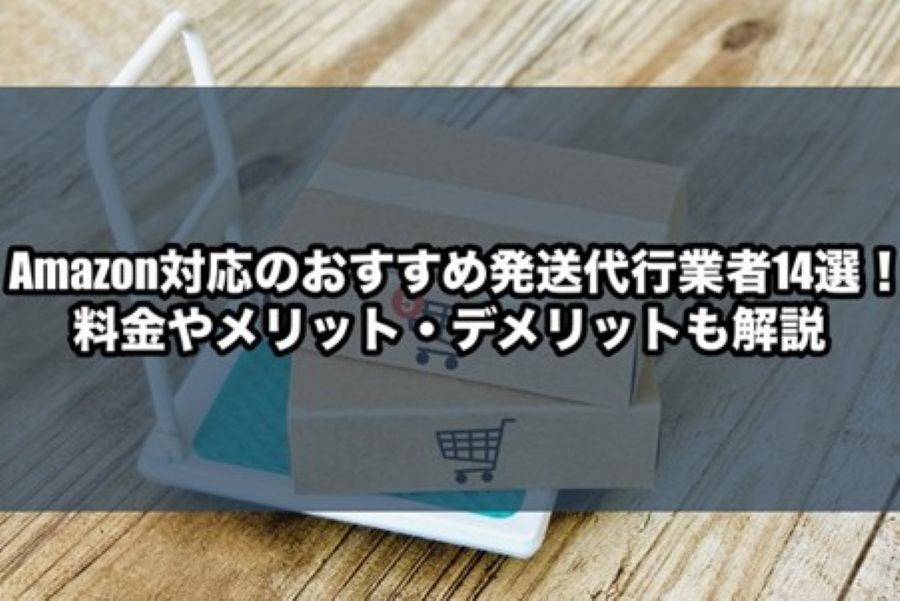







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)