
国内外のECをはじめ、リユース、美容・健康、音楽などあらゆるジャンルで執筆中のフリーランスライター。中国への留学経験を生かし、13年間、繊維製品や楽器、雑貨の輸入業務に携わる。現在はライター業のかたわら、個人で越境ECのセラーとしても活動中。

レンタルビジネスについて「どのように収益が出せるのか?」「他社はどのような戦略で成功しているのか」など、疑問にお思いの方も多いかと思います。
結論から言うとレンタルビジネスで成功するポイントは、長期にわたり回転できる商材の選定と、自社独自のサービスを見つけることです。回転率が上がれば、継続的な収益が見込めます。
本記事では、これからレンタルビジネスへの参入を検討している方に向け、基礎からメリット・デメリット、実際の成功事例までご紹介します。
ぜひ記事を読み、レンタルビジネスを成功に導く自社の戦略を洗い出してみてください。
レンタルビジネスとは?リース、サブスクとの違い

まずはレンタルビジネスの概要を理解しましょう。リースやサブスクリプションなど、混同しやすいビジネス形態との違いについても解説します。
レンタルビジネスの概要と収益モデル
レンタルビジネスとは、商品を販売せずに貸し出し、契約期間に応じて使用料を課金するビジネスモデルです。商材は、DVD、アパレル、家電、車や自転車などの「モノ」から、空き家などの「スペース」にいたるまで多様化しています。
収益の仕組みについては、具体的な数字に置き換えて見てみましょう。以下は、仕入れ原価20,000円の家電をレンタル料10,000円に設定した場合の収益計算の例です。
例)
仕入れ原価:20,000円
レンタル料:10,000円
諸経費(送料や維持管理費など):5,000円
1回目のレンタルでの利益:10,000-5,000-20,000=△15,000円
4回目で原価を回収:(10,000-5,000)✕4-20,000=0円
5回目:(10,000-5,000)✕5-20,000=5,000円
6回目:(10,000-5,000)✕6=20,000=10,000円......
※5回目以降は1回につき、5,000円の利益が累積しつづける
このように、レンタルビジネスはレンタル回数が多いほど利益が増えます。月や年単位で時間をかけて利益を生み出すビジネスモデルです。
リース、サブスクリプションサービスとの違い
近年ではレンタルとリース、サブスクリプションサービスそれぞれのビジネスモデルが発展し多様化しているため、明確な定義が難しいでしょう。
あえて定義付けするなら、以下の表のような違いがあります。
大きな違いは、契約期間です。レンタルビジネスは、一定の短期間に特定の商品を貸し出すのが一般的です。中・長期の貸し出しはリースに分類され、途中解約すると違約金が発生します。
サブスクリプションの場合は、解約するまで毎月決まった額の料金を支払います。一方レンタルは返却した時点で契約が終わるため、継続して料金を支払う必要がありません。
レンタルに近いサブスクリプションサービスはレンタル型サブスクリプションともいいます。
一例として、月額の定額料金で好きな洋服を選んで借りられる、メチャカリなどが挙げられます。
|
|
リース |
サブスク |
レンタル |
|
料金 |
定額(月額) |
定額(月額や年額) |
定額(1泊〜1週間、1ヶ月など) |
|
期間 |
中長期(途中解約は不可) |
解約するまで継続 |
1契約ごとに終了 |
|
商材 |
有形の高額な設備や製品 |
有形の商品や無形の コンテンツ、サービス |
有形の商品やスペース |
|
商品の状態 |
基本的に新品 |
中古か新品 |
基本的に中古 |
|
期間終了後 |
返却 |
交換、返却、購入 |
返却 |
<関連記事>
「サブスクとレンタルの違い|ビジネスモデル3つの分類と事例を解説」
「サブスクビジネスの始め方7STEPと成功のコツ!【個人でもできる】」
レンタルビジネスのメリット

レンタルビジネスの概要がわかったところで、次にメリットについても見ていきましょう。以下の順に解説します。
- 継続的に収入を得られる
- 環境問題に貢献できる
- 潜在的な顧客を獲得できる
- 新規参入のハードルが低い
継続的に収入を得られる
レンタルビジネスは、継続的な収益化が可能です。
レンタル料金は仕入れ原価より大幅に低く設定するのが一般的です。そのため、初期投資額の回収までには一定の時間がかかります。しかし資金回収後は、1商品につき何度も利益が発生する仕組みです。
商品のレンタル回転数を上げることで継続的な収益を確保できるのが、一番のメリットだといえるでしょう。
環境問題に貢献できる
レンタルビジネスは、CO2の削減にも効果があることが報告されています。
以下の報告は、2030年のシェアリングエコノミー市場規模が14兆2,799億円まで拡大すると想定した場合の予測です。
例えばレンタルビジネスの普及により「モノ」の新品購入が減少し、同時に家庭ごみの減少が期待できます。「スペース」のレンタルでは、使われていない遊休資産を活用することで新築の建設と、建設物の解体を減らせます。
その結果、CO2の排出量がおよそ7.3%削減できるという試算です。
参照:株式会社情報通信総合研究所「シェアリングエコノミー関連調査2021年度調査結果」
潜在的な顧客を獲得できる
レンタルビジネスには、潜在的な需要を表面化する効果があります。
消費者が商品を購入するとき、価格や機能面で失敗したくないという心理が働きます。レンタルビジネスでは安価で気軽に商品を試せるので、商品を手にとる障壁が下がります。レンタルで実際に製品を使い、満足度が高い場合は購入の促進に効果的です。
これまで製品に興味があるものの利用に至っていない顧客を獲得するのに、レンタルは有効なビジネスモデルだといえるでしょう。
新規参入のハードルが低い
レンタルビジネスは、通常の売り切り型のビジネスに比べ、参入のハードルが低い特長があります。
なぜなら、店舗が不要かつ最小限の人員と在庫で始められるからです。また例外を除いては、開業するのに許認可や資格が必要ありません。ただしレンタカーを始める場合は、自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。DVDやCDは著作権が絡むので、注意しましょう。
<関連記事>「レンタルビジネス 始め方」(公開予定)
レンタルビジネスのデメリット

次に、レンタルビジネスのデメリットについても触れておきます。
大きくわけて、以下の3点です。
- 初期投資の回収ができないリスクがある
- 商品のメンテナンス、管理が負担になることも
- 競合他社が増えやすい
初期投資の回収ができないリスクがある
レンタルの商材によっては、初期投資の金額が回収できないリスクがあります。
レンタルビジネスは仕入れ原価の支払いが先に発生する一方、収益は長期にわたり少額ずつ得られる仕組みです。収益があがるまでに時間差があるため、キャッシュフローが悪化しがちなデメリットがあります。
とくに新製品がすぐに出るような商材は、原価の回収ができないリスクもあります。商品が型落ちするまでに回転率を上げ、早めに資金を回収しなければなりません。
この点を踏まえると、レンタルビジネスにおいて商材の選定は非常に重要だと言えるでしょう。
商品のメンテナンス、管理が負担になることも
レンタルビジネスでは商品が返却されたら次の貸し出しまでに、メンテナンスやクリーニングを実施します。
細かいパーツで構成される商品は、いちど解体して洗浄や消毒が必要です。たとえば車のチャイルドシートは、赤ちゃんの食べこぼしや汗が小さなすき間に入り込みやすいためパーツの解体とクリーニングを手作業で行うこともあります。
またメンテナンス中は次の顧客にすぐ貸し出しが出来ないため、商材ごとのステータスを記録、管理する作業が重要です。
競合他社が増えやすい
レンタルビジネスは新規で参入しやすい一方、競合他社が増えやすい負の側面もあります。
大手企業が同じ商材で参入した場合、資金力があるため、大幅に低い金額設定や無料期間の設定により容易に優位に立てます。
中小企業でレンタルビジネスを運営するには、自社独自の戦略を打ち出すのが成功のポイントです。価格競争に巻き込まれても、資金力では大企業に劣るからです。
自社の独自戦略の一例としては、接客や営業力、販促力、商品力、立地などで差別化を図る施策が挙げられます。
物流面の管理が煩雑になりがち
レンタルビジネスのデメリットとして、商品の入出庫や在庫管理が複雑な面があります。
貸し出した商品の返却、メンテナンス中のステータス管理など状況に応じた細かい管理が求められます。発送と返却が確認できてはじめて在庫情報を更新するため、リアルタイムの在庫把握が難しい点もデメリットです。
ほかにも商品が期間内に返却されているかどうかの確認、および未返却商品への対応も発生します。これらをエクセルなどの手作業で管理する場合、レンタル回数の増加にともない人的ミスが発生しやすくなります。
結果的にレンタルスケジュールが適切に管理できなくなり、機会損失にもつながるでしょう。
自社での物流管理が煩雑化する前に、物流代行サービスを利用するのも一つの解決策です。
物流代行会社でも、レンタルビジネスの対応実績がある業者を選ぶのがポイントです。
<関連記事>「リバースロジスティクスとは?ECで返品物流に取り組む重要性を解説」
レンタルビジネスの成功事例4選

ここからは実際に、レンタルビジネスで成功している企業の事例を4つご紹介します。
それぞれの成功事例をヒントに、ご自身のレンタルビジネスでも競合と差別化できるポイントを探ってみてください。
- 【サブスクに近い腕時計のレンタル】KARITOKE
- 【観葉植物レンタルのフランチャイズ】グリーン・ポケット
- 【フォトスタジオ併設の着物レンタル】株式会社 川平屋
- 【家庭菜園ユーザーも利用する農器具レンタル】アグリズ
【サブスクに近い腕時計のレンタル】KARITOKE
KARITOKEは、ゲームアプリの開発・運営会社クローバーラボが展開する腕時計のレンタルサービスです。
料金プランによって月額が決まっており、同プラン内の高級腕時計から借りたい商品を選べるシステムです。プラン内での商品交換や、プランのアップグレードにも柔軟に対応しています。
ここまではサブスクリプションサービスとほぼ同じですが、大きく異なるのは腕時計を借りない時は利用料がかからない点です。次月にレンタルしない場合は返却し、支払い。
【観葉植物レンタルのフランチャイズ】グリーン・ポケット
グリーン・ポケットは、オフィスや店舗向けの観葉植物や植木のレンタルサービスです。国土緑化株式会社が運営しています。グリーンレンタルとしては国内で唯一フランチャイズ展開を行っており、大手を含む1万社以上の顧客と契約しています。
企業の戦略として、定期的なグリーンの交換やメンテナンス(給水や手入れなど)をサービスの一部として実施。代表取締役の話によると、笑顔やあいさつ、身だしなみまでを商品の一部としてとらえ、社員教育を徹底し植木レンタルのマイナスイメージを払拭することに注力したそうです。
結果的に99%のレンタル継続率を達成、リピート客の獲得に成功しました。
サービス力により差別化を図った結果、成功した事例です。
【フォトスタジオ併設の着物レンタル】株式会社 川平屋
株式会社川平屋は、1895(明治28)年創業の老舗呉服店です。
着物ユーザーの減少や少子化の影響で着物の需要が縮小を続けるなか、行政の商店街整備に関連する支援制度を活用し、フォトスタジオ「桜工房」をオープン。
和服や関連小物のレンタル・販売から着付け、ヘアメイク、撮影までトータルでサービスできるビジネスモデルを開始しました。撮影だけでなくお出かけにも気軽に着物を利用するサービスとして川平屋の認知度が向上し、年平均15%前後で急成長しています。
「モノ」だけだった商材に、体験する「コト」の付加価値を提供することで成功した事例です。
振袖・着物専門店川平屋。振袖レンタルも愛知県豊田市の川平屋へ|川平屋公式ホームページ
【家庭菜園ユーザーも利用する農器具レンタル】アグリズ
アグリズは、農機具販売や修理・点検をおこなう藤原農機株式会社が展開する農機具レンタルビジネスです。創業は昭和22年と長い歴史があります。
2017年に農機具のレンタル事業を開始しました。アメリカの農機具シェアリングのビジネス形態を一部参考にしたそうです。顧客は地元の和歌山から全国各地に拡大し、成長を続けています。
利用者は家庭菜園を営むユーザーが中心で、プロの農家は年に数回しか使用しない器具のみレンタルするケースが多いといいます。家庭菜園を営む人の中には器具の使い方がわからない初心者が多いため、電話やメールでのフォロー体制を万全に整えています。
レンタルに加え、修理や点検、フォロー体制など自社の強みを生かしたサービスにより成功した事例です。
富士ロジテックホールディングスでは高額・リユース品レンタルの物流もお受けします!
富士ロジテックホールディングスは物流代行会社として、レンタル型サブスクリプションやレンタル品の取り扱い実績があります。商材を個体管理し、バーコードでステータスをひも付けできるレンタル商材特有の管理体制を整えております。
また取り扱い不可の業者が多いリユース品や高額商品も、弊社ではお預かり可能です。他社で代行を断られたという方も、お気軽にご相談ください。
サービスの概要は以下からご確認いただけます。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
オガミキヨ
国内外のECをはじめ、リユース、美容・健康、音楽などあらゆるジャンルで執筆中のフリーランスライター。中国への留学経験を生かし、13年間、繊維製品や楽器、雑貨の輸入業務に携わる。現在はライター業のかたわら、個人で越境ECのセラーとしても活動中。
タグ一覧
カテゴリー



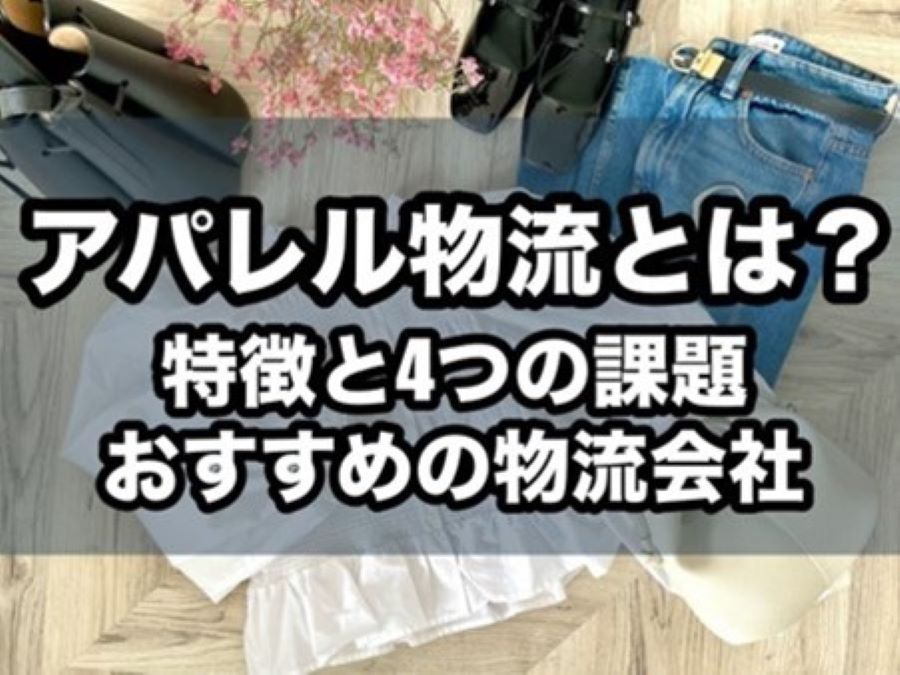
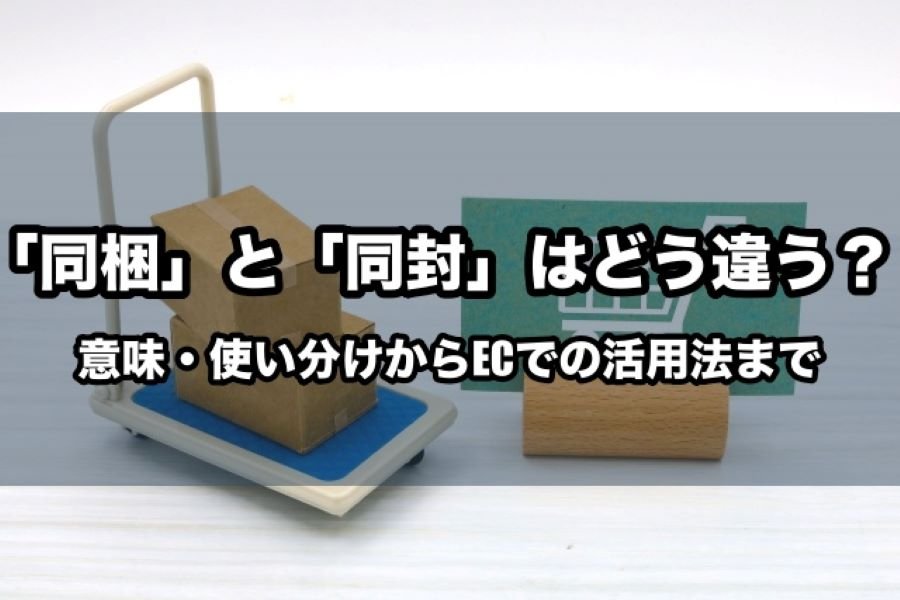
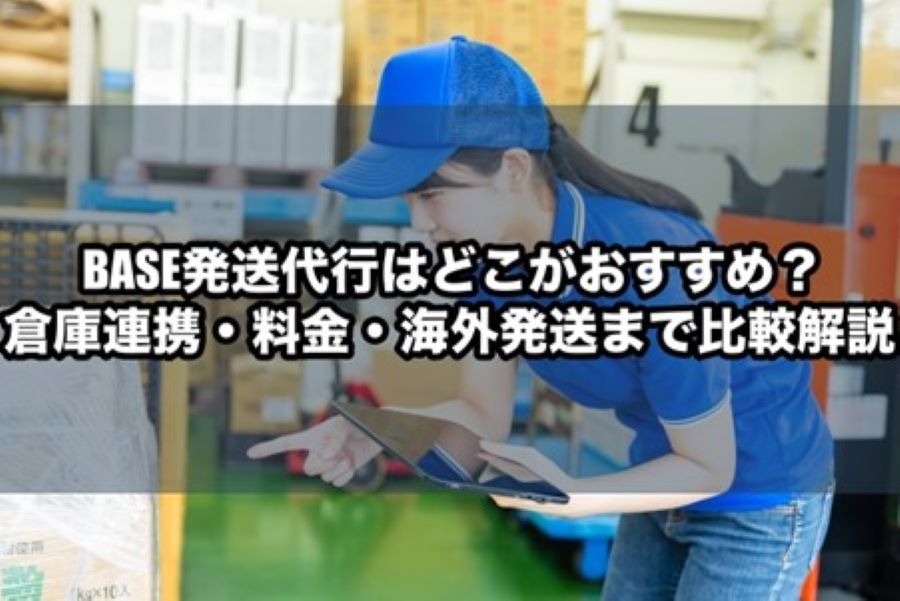
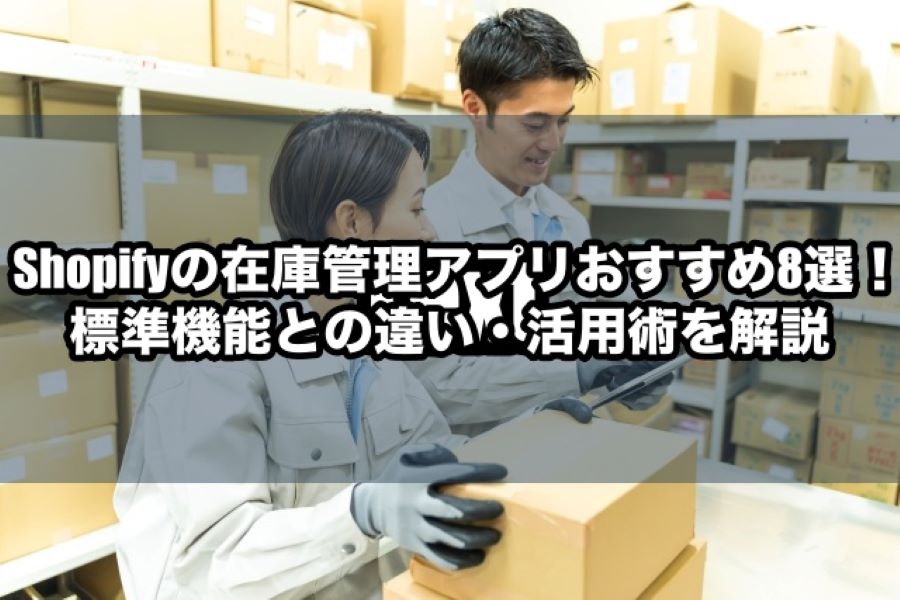
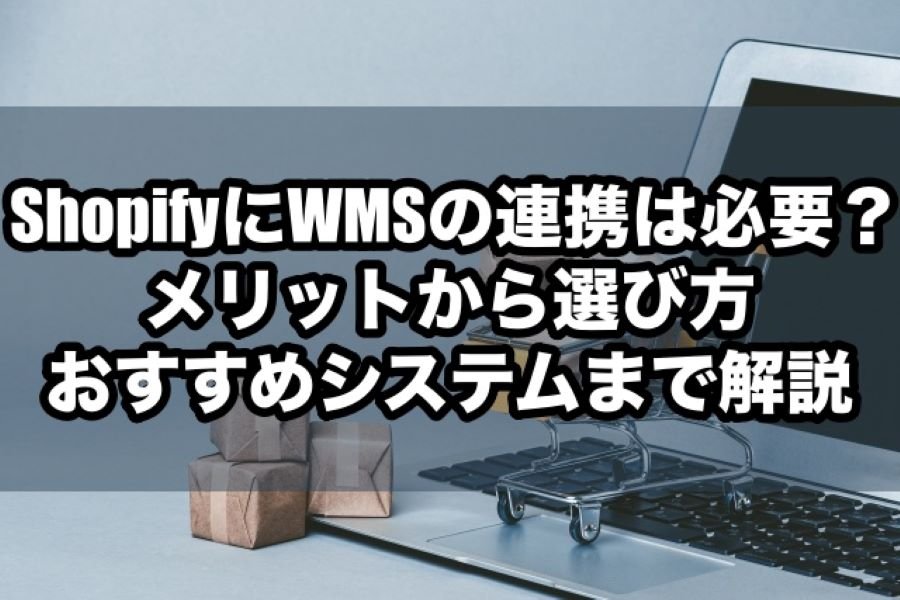
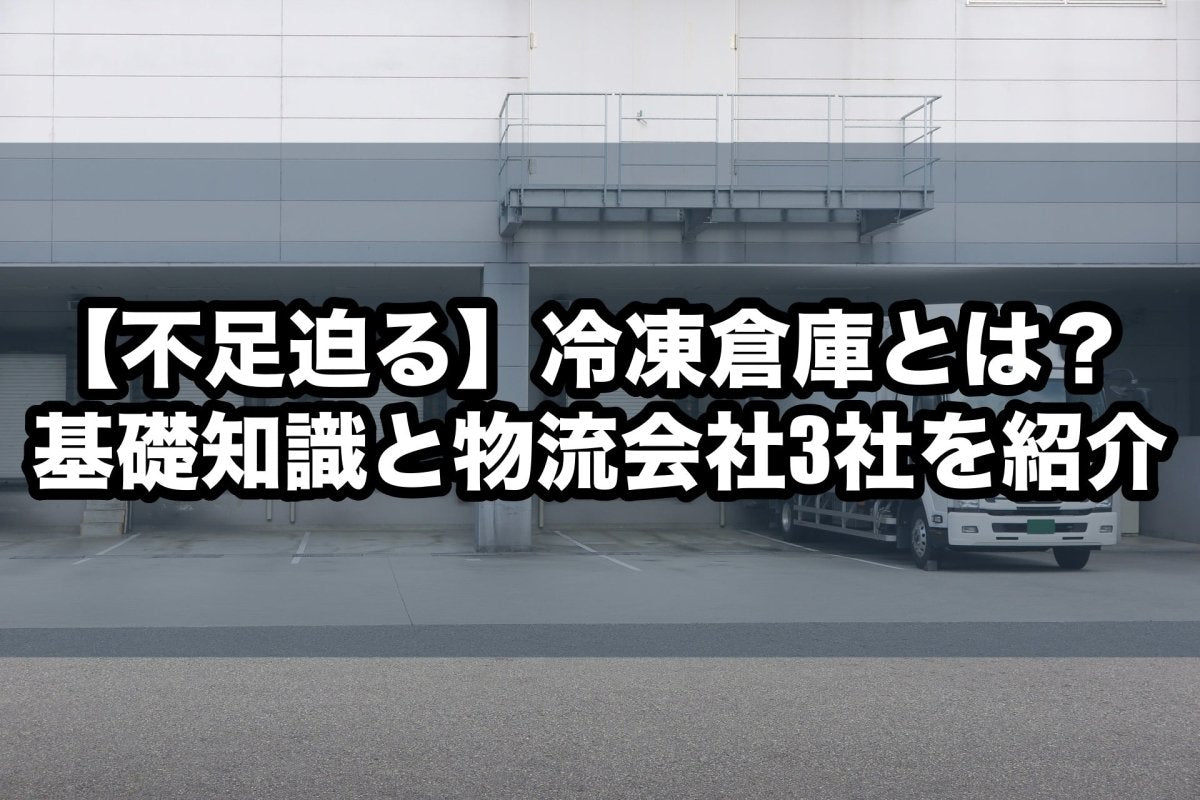
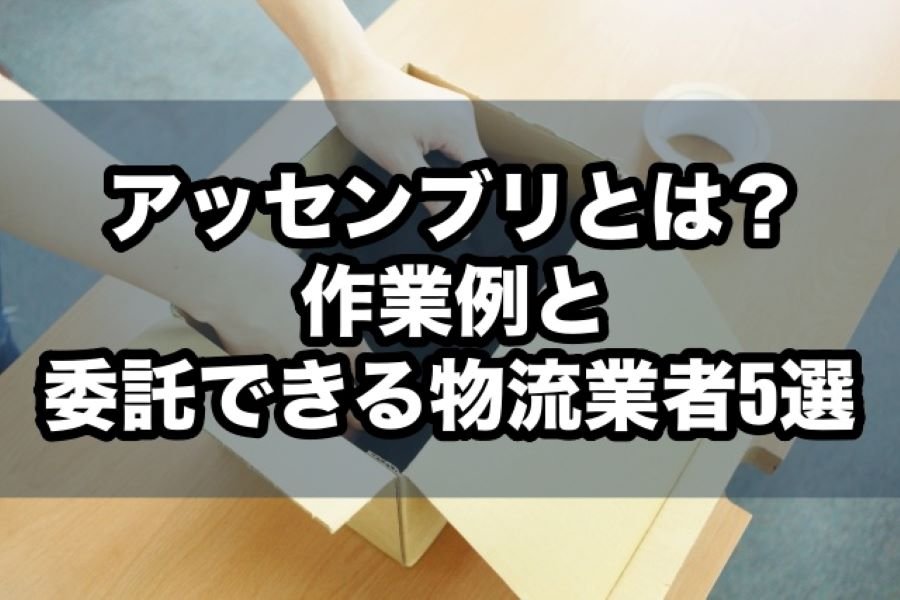







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)