
物流会社で20年経験しD2C EC スタートアップから中規模、大規模のeコマース事業者へフルフィルメントサービスの提供や物流の見直し・改善、スピード配送、複数拠点展開を設計して提唱している。 事業者様の売上貢献するために 「購買体験」 「リピート施策」 「Unboxing」 やOMO対応での「オムニチャネル」 「返品交換物流」 を提案し、事業者と常に伴走して最新の物流設計を試みる。

サプライチェーンとは、原材料の調達から生産、販売によりエンドユーザーに届くまでの流れを指します。サプライチェーンは従来経営用語として使われていましたが、近年はビジネスでも使われている言葉です。サプライチェーンマネジメントにより情報を共有することでサプライチェーンの最適化を実現できるようになります。
サプライチェーンの最適化をすることで、コスト削減や生産性向上が見込めます。さらに、一部の拠点で業務が止まることにより全体の供給に影響するサプライチェーンリスクの防止も可能です。商品や市場が多様化した現在において、サプライチェーンマネジメントの需要度が年々増しています。
サプライチェーンとは
サプライチェーン(Supply Chain、供給連鎖)は、商品がエンドユーザーに届くまでの物流のことです。原材料の仕入れから在庫管理、販売まで1つの流れでつながっており、サプライチェーンがスムーズに進まないと、商品がエンドユーザーに届かなくなります。
サプライチェーンリスクとは
サプライチェーンリスクとは、サプライチェーンに関わっている一部の拠点において業務が止まることによって全体的な供給の流れが稼働しなくなることです。サプライチェーンリスクが発生する要因として、市場の多様化や自然災害、感染症の拡大などが挙げられます。
近年では製造技術やIT技術が向上したことによって、ユーザーごとのニーズに合わせた商品の展開が一般的となっています。製品や市場のバリエーションが増えることにより、取引する企業が増える結果となり管理がむずかしくなり、サプライチェーンリスクにつながります。さらには、台風や大雨などの自然災害や感染症の拡大も生産体制の停止につながる要因です。
バリューチェーンとの違い
バリューチェーン(Value Chain、価値連鎖)とは、エンドユーザーが商品を受け取るまでのプロセスにおいて付与される価値のことです。サプライチェーンのプロセスにおいて、どの部分で利益につながる付加価値が生まれているかを判断するために活用されます。
サプライチェーンは調達から消費までの流れを見直す必要がありますが、バリューチェーンで分析をする場合は事業活動全体的に掘り下げることが求められます。そのため、バリューチェーンには、製造や購買物流、販売が含まれていることからサプライチェーンの要素も必要です。
サプライチェーンマネジメントとは
サプライチェーンマネジメント(SCM)とは、サプライチェーンのそれぞれのプロセスにおいてリスクや運用方法を管理することで流れを最適化することです。サプライチェーンマネジメントをすることで、それぞれのプロセスをスムーズにまた効率的に運用でき、業務効率化やコスト削減につなげられます。
サプライチェーンマネジメントが注目された理由
サプライチェーンマネジメントが注目された理由として、次の2点が挙げられます。
- 物流といった概念
- 物流コストの向上
日本では1960年以降大量生産や大量消費が始まったことにより自動車輸送の需要が高まり、物流には多品種大量輸送が求められたことにより効率的な運用が必要になり物流の概念が取り入れられるようになりました。
さらに、1980年代後半に入り大量生産や大量消費から量より質の時代に変わり、このタイミングから多品種小ロット生産時代が始まりました。多品種小ロット生産時代の特徴として多頻度小口配送があり、制裁効率が悪化したことから物流コストが上がるようになりました。
サプライチェーンマネジメントの需要が高まった理由
サプライチェーンマネジメントの需要が高まった理由として、情報技術革新や市場のグローバル化が挙げられます。市場がグローバル化したことにより、サプライチェーンが全世界規模に拡大し、地政学的リスクや運用コストが売上に大きく影響するようになりました。
さらに、情報技術革新が進むことによりユーザーの行動が多様化しました。そのため、販売状況や需要などにおけるビッグデータの分析が必要になり、サプライチェーンマネジメントの需要が高まる要因となりました。
サプライチェーンマネジメントとERPの違い
サプライチェーンマネジメントとERP(Enterprise Resource Planning、企業資源計画)は混合されることがよくあります。サプライチェーンマネジメントは、原材料の調達からエンドユーザーに商品が渡るまでのサプライチェーンの最適化です。それぞれのプロセスを最適化することによって、生産性の向上やコスト削減を目指します。
ERPとは、資産や製品やサービス、人材、情報といった経営資源を最低限に有効活用することが目的です。ERPはサプライチェーンマネジメントを含めて効率化します。企業に必要な資源要素を有効活用するためにERPシステムを活用することが一般的です。
サプライチェーンマネジメントを導入するメリット
サプライチェーンマネジメントを導入するメリットとして、次の点が挙げられます。
- コスト削減
- 生産性の向上
- 収益性の向上
- 在庫を最適化
コスト削減
サプライチェーンマネジメントを進めることによって、各プロセスにおいて在庫管理や需要量などを共有することによってコスト削減につながります。需要予測が共有されていない状況では在庫を過剰に抱える場合がありますが、最終的に必要な量を前のプロセスに共有することによって資材の購入量やリードタイムをコントロールすることが可能です。
生産性の向上
それぞれのプロセスをリアルタイムで管理し、状況を把握することで個別に管理するといったプロセスを省けます。従来のサプライチェーンでは、管理作業に手間や時間をかけていることがありましたが、サプライチェーンマネジメントを導入することで手間を減らし生産性の向上が期待できます。
収益性の向上
サプライチェーンマネジメントを目的として、流通管理システムの導入で需要予測の精度を高めることができ、需要予測の精度を高めることで最適な流通量を管理することが可能です。ほかにも、流通管理システムを導入することで仕入計画の修正ができたり、業務プロセスの改善をしたりするなど収益性の向上が期待できます。
在庫を最適化
サプライチェーンマネジメントの導入により、在庫の最適化を実現できます。サプライチェーンの川上企業であれば、ユーザーのニーズをつかみづらいため流通段階の直前の業者から情報を得ることが重要です。小売業者は欠品をしないように卸業者に多めに発注して、卸業者はメーカーに対してさらに多めの発注をするなどサプライチェーンでは余剰在庫が発生しがちです。そこで、サプライチェーンマネジメントをすることで川上から川下の企業まで情報共有でき、無駄な在庫を防止できます。
富士ロジテックホールディングスのサプライチェーンマネジメント
富士ロジテックではサプライチェーンマネジメントを、「お客様のサプライチェーンを、お客様の目線で捉え、サプライチェーンの管理者として一括した最適化を実現し、継続すること」と掲げています。顧客ごとのサプライチェーンマネジメント部門として機能することが目的です。
GSE
富士ロジテックでは、GSE(グローバル・サプライチェーン・エンジニアリング)を目指しています。顧客にとって最適で効率的なサービスを提供しています。顧客が抱えているサプライチェーンの特徴やビジネスモデルなどを把握したうえで、現状の課題をつかみ課題を解決できるようなソリューションを提案することが特徴です。

リーン・ロジスティクス
サプライチェーンを最適化することで、持続的に効率化できるリーン・ロジスティクス(無駄のない物流システムのこと)に進化します。富士ロジテックでは、ビジネスモデルやマーケット、社会構造などの変化に伴いGSEのもとに顧客の継続的な全体最適化を目指しています。
まとめ
サプライチェーンとは、原材料の調達から商品がエンドユーザーに届くまでの流れのことです。サプライチェーンには複数の企業や拠点が関わっており、サプライチェーンの最適化をするサプライチェーンマネジメントが求められています。
富士ロジテックでは、顧客にとって最適なサービスを提供し続けるGSEを展開し、リーン・ロジスティクスへと進化へと進化させていきます。最適なサプライチェーンは日々変化するため、富士ロジテックでは継続的に全体最適化を提供し続けていきます。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

監修者
株式会社富士ロジテックホールディングス
西間木 智 / 通販営業部 部長
物流会社で20年経験しD2C EC スタートアップから中規模、大規模のeコマース事業者へフルフィルメントサービスの提供や物流の見直し・改善、スピード配送、複数拠点展開を設計して提唱している。 事業者様の売上貢献するために 「購買体験」 「リピート施策」 「Unboxing」 やOMO対応での「オムニチャネル」 「返品交換物流」 を提案し、事業者と常に伴走して最新の物流設計を試みる。
タグ一覧
カテゴリー


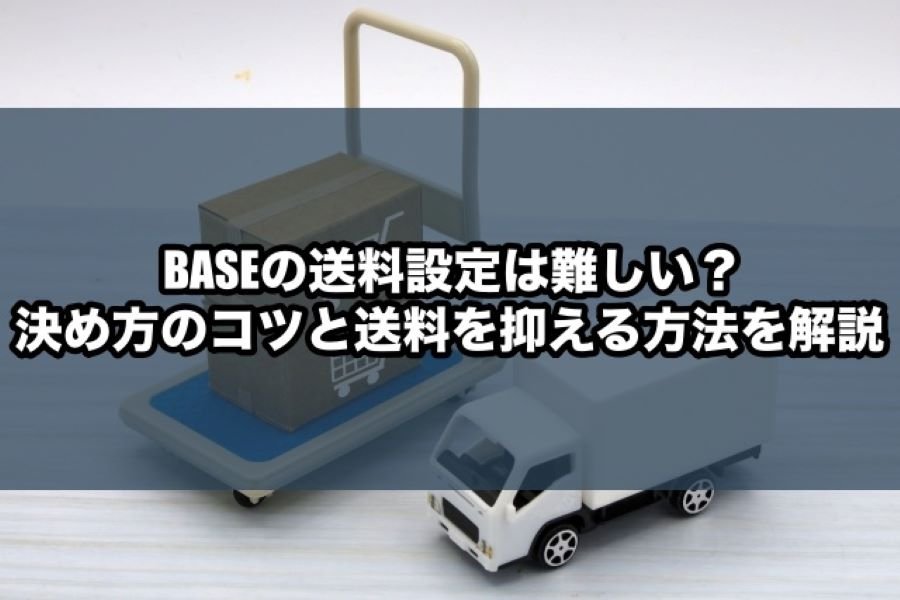
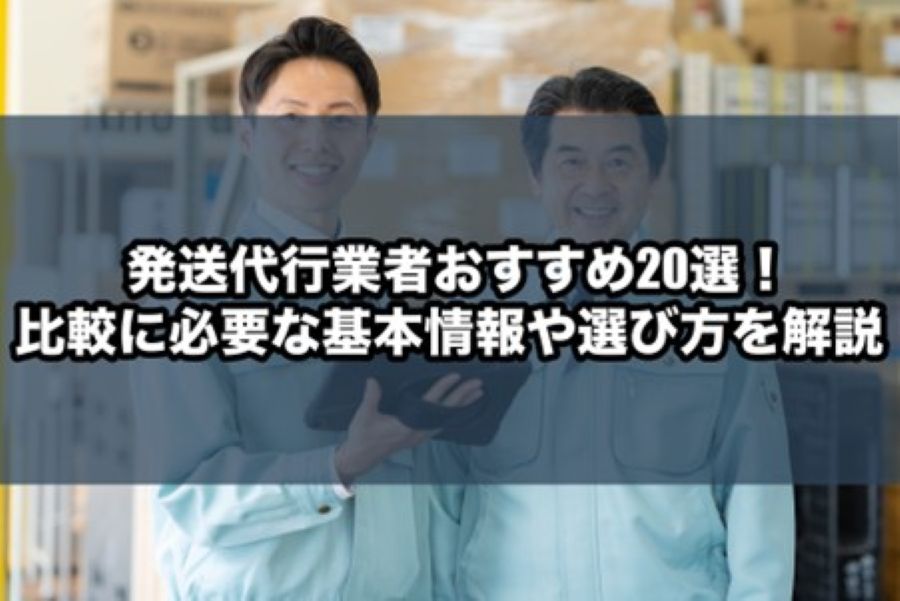


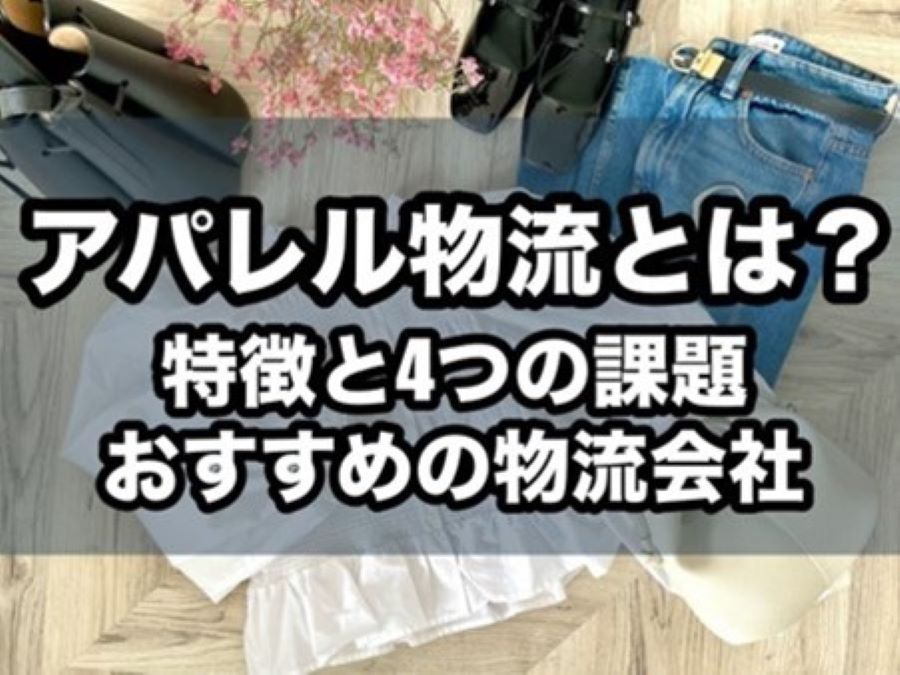
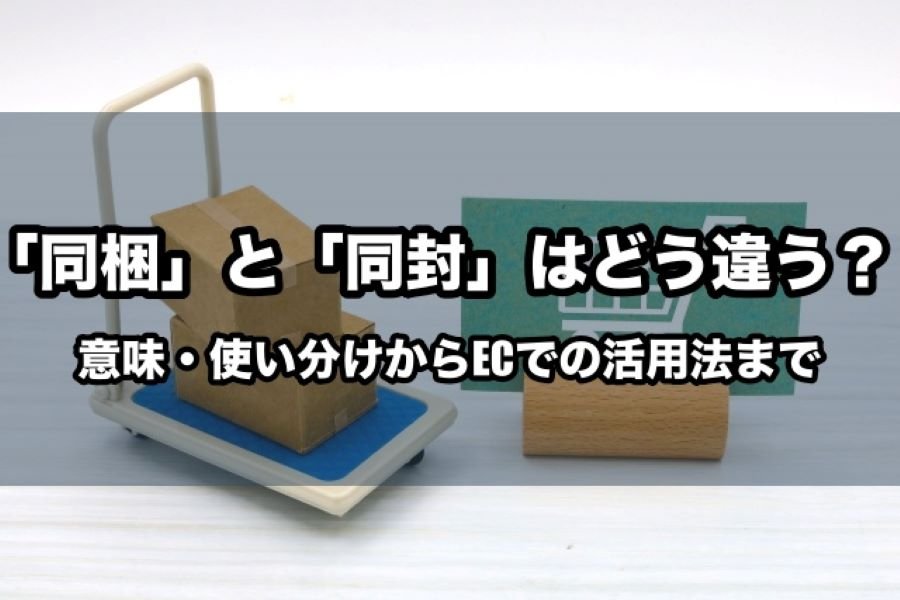
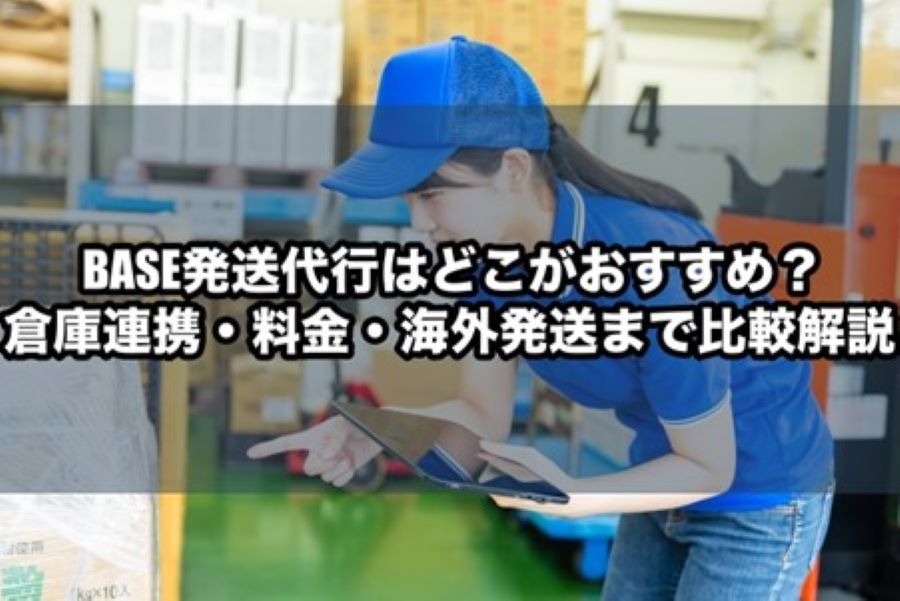
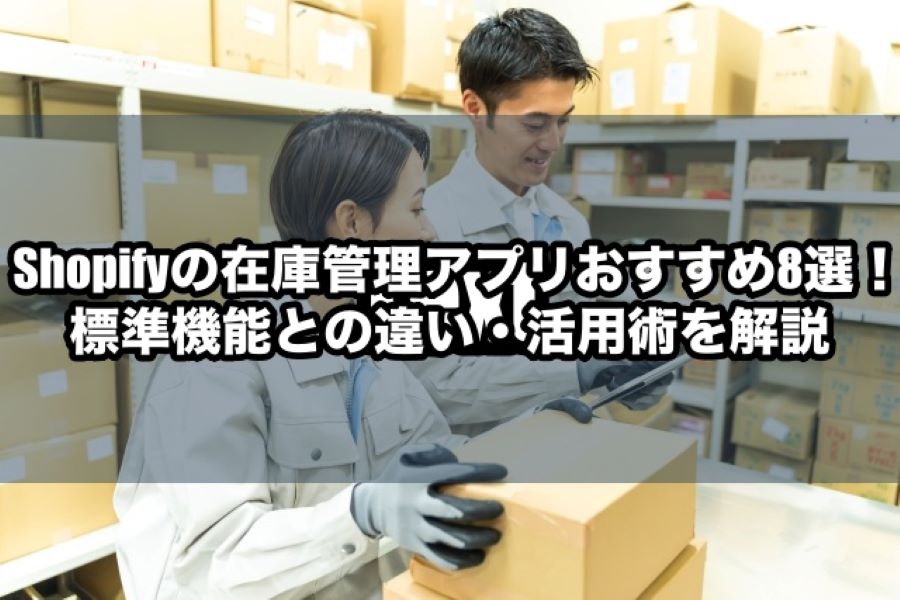







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)