
物流会社で20年経験しD2C EC スタートアップから中規模、大規模のeコマース事業者へフルフィルメントサービスの提供や物流の見直し・改善、スピード配送、複数拠点展開を設計して提唱している。 事業者様の売上貢献するために 「購買体験」 「リピート施策」 「Unboxing」 やOMO対応での「オムニチャネル」 「返品交換物流」 を提案し、事業者と常に伴走して最新の物流設計を試みる。

物流とは一体何でしょうか。誰もが一度はその言葉を聞いたことがあるでしょう。しかし、その細部まで理解している人は少ないかもしれません。物流の重要性やその基本について詳しく解説します。物流は私たちの生活や経済活動と密接な関係を持ち、それは生産物の輸送から販売までの一連の流れとなります。これらから物流の基本とその重要性を認識することができます。
物流の定義とは何か?
物流とは、商品が消費者のもとに届けられるまでの一連の工程のことを指します。主に生産、輸送、保管、配送といった一連の活動を含む概念です。
この物流には、輸送・保管・荷役・包装・流通加工・情報処理といった6つの機能が含まれています。近年では、ECサイトの運営企業が増加し、EC物流を意識することも大切になってきました。
EC物流では、商品の受注から配送までのプロセスを効率的に管理することが求められます。在庫管理や配送ルートの最適化など、様々な課題に取り組む必要があるでしょう。
EC物流の仕組みや課題について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。物流の理解は、ビジネスを効率化する上で欠かせない視点と言えます。
EC物流とは?仕組みや課題、解決策としておすすめの代行業者を10社紹介
物流の役割とは
物流の役割は非常に幅広く、単に製品を輸送するだけでなく、経済活動全体を支え、結びつける重要な作用を果たしています。例えば、生産地から消費地への製品の輸送は、需給ギャップを埋める役割を果たします。一方で、製品の保管や在庫管理は、製品供給を安定化させるために必要な作業です。また、物流は時間と場所のギャップを克服するための手段であり、適切な物流管理により、企業は顧客のニーズに応え、競争力を強化することができます。
物流がビジネスに与える影響
物流はビジネスに大きな影響を及ぼします。まず、効率的な物流は製品のコストを下げる役割を果たします。これは、製品の生産から消費者への配送までの過程で必要な時間とコストを減らすことで実現します。さらに、物流の質向上は顧客満足度の向上に繋がります。適切な時間と場所で製品を届けることで、顧客のニーズを満たし、顧客満足度を高めることが可能となります。これらは、企業の競争力を強化し、経済的な成果を生む重要な要素となります。
物流の主な目的
物流の主な目的は、商品とその商品を求める消費者との間にある時間的・空間的なギャップを埋めることです。
物流では、商品が注文されてから届けるまでの時間を短縮し、空間的な隔たりを解消することが重要視されています。
さらに、コストを抑えてできるだけ効率的に商品を消費者の元へ届けることも大切な目的の1つです。
近年では、物流をより効率化させるために、物流代行会社に業務を委託する企業も増加しています。
物流代行を活用すれば自社の物流業務を最適化でき、コスト削減や顧客満足度の向上を図れます。
物流とロジスティクスの違いとは?
物流とロジスティクスは、似た言葉であるため混同されやすいですが、その意味は大きく異なります。
物流とは、商品が消費者のもとに届けられるまでの一連の工程のことです。
一方、ロジスティクスとは、必要な商品を必要な時に必要な場所に必要な数量だけ供給する仕組みのことを指します。
また、物流を最適化するための仕組みでもあります。
ロジスティクスは、物流をより戦略的にとらえた概念です。
在庫管理や需要予測、輸配送ネットワークの最適化など、物流全体の効率化を図ることがロジスティクスの目的です。
ECロジスティクスの特徴や課題などを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。物流とロジスティクスの違いを理解することは、効率的なサプライチェーンの構築に役立ちます。
物流で抱えている主な3つの課題
物流業界では、以下の3つの課題を抱えています。
- 小口発送の増加による配送効率の低下
- 少子高齢化による人材不足
- 燃料費用の高騰によるコスト増加
上記の課題を理解し、改善できるように対策を練りましょう。
小口発送の増加による配送効率の低下
物流業界では、小口発送の増加による配送効率の低下が大きな課題となっています。
小口発送とは、文房具やアクセサリーなどの小物を単体で配送することです。
EC市場の拡大にともない、従来は店頭で購入していた小物の配送需要が増加しています。
その結果、トラックの積載量が低下し、配送効率も悪化しているのです。
小口発送の増加は、1回あたりの配送個数を減らし、配送ルートを複雑にするため、配送コストが増大し、環境負荷も高まることになります。
小口発送への対応は、物流業界にとって喫緊の課題の一つでもあります。
少子高齢化による人材不足
少子高齢化の進行により、物流業界では深刻な人材不足に直面しています。
倉庫や工場の現場スタッフ、トラックドライバーなど、物流を支える人材の確保が難しくなっているのです。
特に、トラックドライバーの不足は深刻で、長時間労働や休日出勤などの過酷な労働環境が常態化しています。
人材不足により、一人あたりの業務負担が増大し、ワークライフバランスの悪化につながっているのです。
物流業界では、働き方改革や生産性の向上に取り組むことが急務となっています。
自動化技術の導入や、効率的なオペレーションの設計など、さまざまな施策を通して人材不足の解消を図る必要があります。
同時に、物流業界のイメージアップを図り、若年層の人材を積極的に採用・育成していくことも重要です。
燃料費用の高騰によるコスト増加
物流業界では、燃料費の高騰がコスト増加の大きな要因の一つです。
トラックや船舶、航空機など、物流を支える輸送機器の多くは化石燃料を使用しており、燃料価格の変動が直接コストに影響します。
近年、原油価格の高止まりなどを背景に、燃料費が大幅に上昇しており、輸配送コストも増大し、物流会社の収益性が悪化する事態となっています。
燃料費の高騰は、荷主企業にも大きな影響を与える要因の一つです。
輸送コストの上昇により、商品価格の引き上げを余儀なくされるケースも考えられます。
物流業界では、燃料費の影響を最小限に抑えるため、輸配送ルートの最適化や、効率的な車両運用などに取り組んでいます。
また、電気自動車など、代替燃料を使用する車両の導入も進められています。
未来の物流に求められること
物流業界が取り組んできた課題解決だけでなく、未来の物流に求められることもあります。それは、地球環境への配慮です。物流業界はCO2排出量の多い産業の一つであり、環境負荷を軽減するための取り組みが必須です。例えば、電動トラックや燃料電池車を使用した環境配慮型物流の実現が求められます。また、循環型社会の実現に向けて、リユースやリサイクルによる物流も進化していくでしょう。このように、未来の物流は人間や環境への配慮を徹底しつつ、効率的な配送体制を築くことが求められます。
物流の主要なプロセス
物流の主要なプロセスは、以下の3つに分けられます。
- 物流プロセスの概要
- 入庫から出庫までのステップバイステップ
- 特別な状況下での物流プロセス
それぞれを詳しく解説していきます。
物流プロセスの概要
物流プロセスは大きく「供給源からの入庫」「保管」「出庫を経て顧客への運送」の3つのステップに分けられます。供給源からの入庫とは、製造工場やサプライヤーから商品を受け取り、自社の保管スペースへ運び込むことを指します。次に、保管とは商品のインベントリ管理を行いながら次のステップへの移動を待つことです。最後に、出庫を経て顧客への運送とは、顧客の注文に応じて商品を出庫し、運送会社や自社の運送手段を利用して顧客のもとへ届けるプロセスになります。
入庫から出庫までのステップバイステップ
入庫から出庫までのステップバイステップを詳細に見ていきましょう。まず最初に行うのは「受け取り」、供給元から商品を受け取ります。その後「検品」を行い、商品が適切な状態で受け取られたかを確認します。続いて商品は「保管」されます。保管期間中には、定期的な「在庫確認」が行われることで、必要な商品が適切な数量だけ確保されていることを保証します。次に「ピッキング」、つまり出庫前の商品の準備が行われます。これは顧客からの注文に基づくものです。ピッキングが終わったら、「梱包」が行われ、最後に「出庫」そして「配送」が行われるのです。
特別な状況下での物流プロセス
一方で、災害やパンデミック、サプライチェーンの混乱など特殊な状況下では、物流プロセスには柔軟な対応が求められます。例えば、供給源からの入庫が滞った場合、代替品の調達や在庫の見直しを早急に行う必要があります。また、大量の注文が一度に発生した場合、出庫作業の効率化や配送ルートの最適化を模索しなければなりません。そのため、特別な状況下での物流プロセスでは、通常時以上のスピードと正確さが求められるのです。一方、効果的なリスクマネジメントを行うことで、こうした特殊な状況への対応力を養うことも重要でしょう。
入庫プロセスの詳細

入庫プロセスは、以下の3つの工程に分けられます。
- 商品のチェックと整理
- 在庫数量の管理
- 在庫データの記録
それぞれを詳しく解説していきます。
商品のチェックと整理
商品が倉庫に到着したら、まず初めに商品のチェックと整理を行います。これは商品の状態を確認し、期待通りの品質を保証するための大切なプロセスです。商品のチェックでは、商品が適切に包装されているか、破損や不良がないか、などを確認します。これにより、出荷前の潜在的な問題を未然に防ぐことが可能になります。
次に商品の整理です。商品を適切な位置に保管するためには、商品の種類、形状、重さなどを考慮して配置を決定します。この整理作業により、効率的な倉庫運営が可能となり、迅速な出荷作業をサポートします。
在庫数量の管理
在庫数量の管理は、供給と需要のバランスを保つ上で重要な役割を果たします。具体的には、どの商品がいつ、どれくらい必要かを予測し、必要な数量を適時に補充します。在庫数量の適切な管理により、過度な在庫によるコスト増や、在庫切れによる顧客の不満を防ぐことができます。
また、在庫の状況により、商品の補充頻度や購入数量を調整することもあります。このようにして、在庫数量の管理により、効率的な資源の配分そして顧客満足度の向上につながります。
在庫データの記録
倉庫在庫の最終段階が在庫データの記録です。すべての商品情報を正確に記録・保存することで、現在の在庫状況を正確に把握し、必要なら即時に対応することが可能となります。データは電子的に保存され、必要に応じて分析するための情報源となります。
在庫データの記録には、商品の種類、数量、在庫位置など、商品毎の詳細な情報が含まれます。これらの情報は、適切な在庫管理をサポートし、透明性と効率性を確保します。もちろん、これらのデータは定期的に更新・チェックされ、常に正確かつ最新の情報を保持しています。これにより、ビジネス全体の効率性と顧客満足度の向上に直接貢献します。
保管プロセスの詳細

保管プロセスは、以下の3つの工程に分けられます。
- 物流センターでの商品の整理と配置
- 在庫管理システム(WMS)の活用
- 保管期間中の商品の管理
それぞれを詳しく解説していきます。
物流センターでの商品の整理と配置
物流センターにおいては、数多くの商品が収められています。そこで重要となるのが商品の整理と配置です。これにより、商品の取り出しや発送がスムーズに行え、効率的な業務運営が可能となります。商品は種類、形状、重さなどにより分類され、配置されます。さらに、在庫量に応じて商品の配置場所も変動し、在庫管理においても重要な側面を持っています。また、定期的な商品の点検も行われることにより、その状態を確認し、商品の質を維持していきます。
在庫管理システム(WMS)の活用
在庫管理システムとは、商品の在庫状況を一元管理できるシステムのことを指します。これにより、どの商品がどの程度の量で在庫されているのか、また、どの商品がいつ発送されたのかなどを把握することが可能です。従って、在庫切れや過剰在庫を防ぐための対策を適切に行うことが可能となります。また、需要予測も行いやすくなるため、未来の販売計画を立てる際にも有用です。
保管期間中の商品の管理
商品が保管されている期間の間も、一定の管理が求められます。それは、品質維持のためだけでなく、動きやすさやセキュリティ面でも大切な事項です。温度や湿度の管理はもちろんのこと、防犯対策も重要な項目となります。更に、消防法など法規制に対する準拠も確認し、定期的に監査を行うことで法的な問題を防ぎます。これらの管理が徹底されていることで、商品は適切に保管され、お客様には当然のことながらベストな状態で届けられるのです。
出庫プロセスの詳細

出庫プロセスは、以下の3つの工程に分けられます。
- 商品のピッキングと梱包
- 出庫データの記録
- 商品の配送
それぞれを詳しく解説していきます。
商品のピッキングと梱包
商品の出庫は、その最初のステップであるピッキングから始まります。ピッキングとは、倉庫内から発送するための商品を選び出す作業のことを指します。スタッフはピッキングリストをもとに、商品を探し出し、カートに積みます。この際に、商品の数量や状態などを確認し、正確にピッキングを行うことが重要となります。
次に、ピッキングされた商品は梱包エリアへ移送されます。梱包とは、商品を適切な包装材で包み、出荷の準備をする作業のことです。商品の種類や形状、サイズに応じて最適なパッケージング材を選び、商品が配送中に損傷を受けないように注意深く梱包します。
<関連記事>
梱包作業を簡単に効率化!改善のコツ8つと事例をECの現場から解説
出庫データの記録
出庫データの記録は出庫プロセスの重要な一部です。これには、出庫される商品の品名、数量、出庫日時など具体的な情報が含まれます。正確さと速度はこのプロセスにおいて不可欠で、ミスが発生すると在庫管理が乱れたり、出荷ミスが生じたりする可能性があります。
ほとんどの企業では現在、データ記録にはバーコードスキャナーやRFIDリーダーなどを使用し、出庫データを自動的に記録するシステムを採用しています。これにより人的なエラーを大幅に減らしたり、作業効率を向上させたりすることが可能です。
商品の配送
出庫プロセスの最後のステップは、商品の配送です。このプロセスは出庫作業が終了した商品を最終的な受取人へ届ける作業で、配送方式は商品の種類や量、配送先により異なります。小売業者やオンラインストアは、宅配便や郵送など個々の消費者へ配送することが一般的でしょう。
一方で多量の商品をまとめて、企業間で配送する場合はトラックや貨物列車、貨物船など大量輸送に適した手段が利用されます。いずれの場合も配送のスムーズさと正確さは極めて重要で、また配送状況のトラッキングや情報更新も定期的に行われます。
物流の効率化と最適化に関するよくある質問
物流の効率化と最適化に関するよくある質問は、以下の3つです。
- 効率的な在庫管理とは?
- 最新の物流技術トレンドとは?
- 物流最適化のためのベストプラクティスとは?
それぞれを詳しく解説していきます。
効率的な在庫管理とは?
効率的な在庫管理とは、適切な数量の商品を適切な時期に準備し、顧客の需要に応えることができる体制を作ることです。これにより、商品の過剰在庫や在庫切れによる機会損失を防ぐことができます。さらに、データ分析を行い、予測や統計をもとに在庫を管理することで、物流コストを抑制したり、収益を最大化することも可能です。インターネットの発達により、データ分析ツールはますます進化し、より細かい在庫管理が可能になります。企業がこれらの効率的な在庫管理技術を導入し、最適化を進めることが求められます。
物流業務を効率化する魅力や方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。在庫管理の効率化は、コスト削減や、顧客満足度の向上につながります。
物流業務を効率化することによる3つの魅力とは?方法や求物流業務を効率化することによる3つの魅力とは?方法や求められる理由を解説められる理由を解説
最新の物流技術トレンドとは?
物流業界でも、AIやIoT、ブロックチェーンなどの最新技術が注目されています。AIの使用は、需要予測やルート最適化、自動化・効率化などの物流業務改善に寄与しています。また、IoTは、適切な在庫管理や配送状況のリアルタイムの可視化に役立ちます。さらに、ブロックチェーン技術は透明性とトレーサビリティを提供し、サプライチェーン全体の効率化を実現する可能性を秘めています。これらの最新技術は、物流の効率化と最適化という課題への解決策の一つでしょう。
物流最適化のためのベストプラクティスとは?
物流最適化を進めるためには、以下のベストプラクティスを参考にするとよいでしょう。まず、経営者全体で物流の改善意識を高め、全社員が物流効率化につながるアイデアを提案する環境を作ることが必要です。次に、ITツールを導入し、データ分析に基づく戦略的な意思決定を行います。その後、スタッフの育成と教育に力を入れ、高度なスキルを持つ物流プロフェッショナルを育てます。また、物流パートナーとの良好な関係を維持し、共に業務を改善していきましょう。最後に、継続的に物流の改善活動を行い、状況に応じて改善策を見直します。これらは物流最適化の効果的な進め方の一部です。
物流業務の効率化や課題解決を進めるなら「発送代行365」に相談しよう!

物流とは、商品を生産地から消費地に適切に運ぶ仕組みのことです。ビジネスの世界においてとても重要であり、効率的な物流が求められています。そして、そのためには物流の全体像の理解、物流プロセスをスムーズにする方法、そして物流を最適化するためのステップなどが必要となります。それはどういうことか、以下で詳しく解説していきます。
物流の全体像の理解
物流の全体像とは、仕入れから出荷、そして配送までの一連のフローを指します。適切な商品の選定、製造や包装の手順、輸送、そして商品の受け取りまで、全体の視野を持つことが重要です。また、これら一連の物流プロセスのうち、効率的に行うべきポイントを見極め、それぞれをスムーズにつなげる必要があります。具体的には、商品がどこから供給されているのか、どのように運ばれているのか、どのように配布するのかなどの情報を把握することです。これにより、不必要な遅延を避け、更に初期コストを低減させることが可能となります。
物流プロセスをスムーズに進める方法
物流プロセスをスムーズに進める方法として、まずは適切な情報共有を行うことが大切です。関係各所との確認、情報のアップデート、そして進捗管理など、全体の流れを把握し、適切な行動を取ることが求められます。また、在庫管理も重要な要素となります。在庫の状況を正確に把握し、必要な時に必要な分だけ商品を仕入れることが求められます。これにより、在庫の余剰や不足を防ぎ、効率的な物流を実現することが可能になります。
物流を最適化するための一歩
物流を最適化するための一歩としては、自社の物流に関するデータの分析が欠かせません。流通経路や輸送方法、在庫管理など、物流に関する様々なデータを収集し、そこから必要な情報を引き出すことで、より効率的な物流を構築することができます。具体的には、過去のビジネスパターンから最も効率の良い配送ルートや在庫管理方法を見つけ出したり、新たなビジネスチャンスを探したりします。これにより、物流コストを抑えながらも、顧客への迅速な対応を実現し、ビジネスの競争力を高めることができるのです。
富士ロジテックホールディングスでは輸出入に関わる通関業務や輸配送業務、適切な物流拠点の提案をさせて頂いております。
商品に合わせた入庫、保管、出庫や納品先に合わせた配送手段・ルート便や共同配送などの実績もございます。
自社物流からのアウトソーシングや物流改善をご検討の場合はお問い合わせください。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

監修者
株式会社富士ロジテックホールディングス
西間木 智 / 通販営業部 部長
物流会社で20年経験しD2C EC スタートアップから中規模、大規模のeコマース事業者へフルフィルメントサービスの提供や物流の見直し・改善、スピード配送、複数拠点展開を設計して提唱している。 事業者様の売上貢献するために 「購買体験」 「リピート施策」 「Unboxing」 やOMO対応での「オムニチャネル」 「返品交換物流」 を提案し、事業者と常に伴走して最新の物流設計を試みる。
タグ一覧
カテゴリー



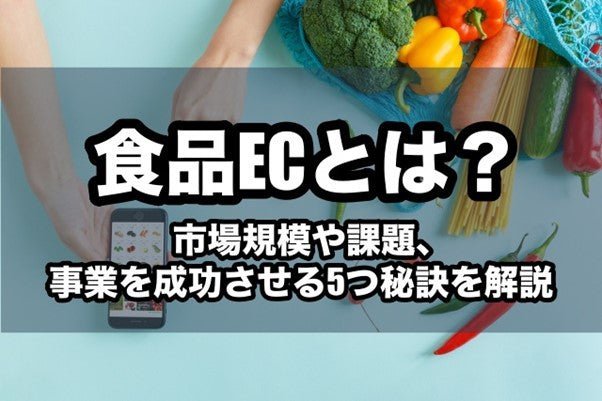
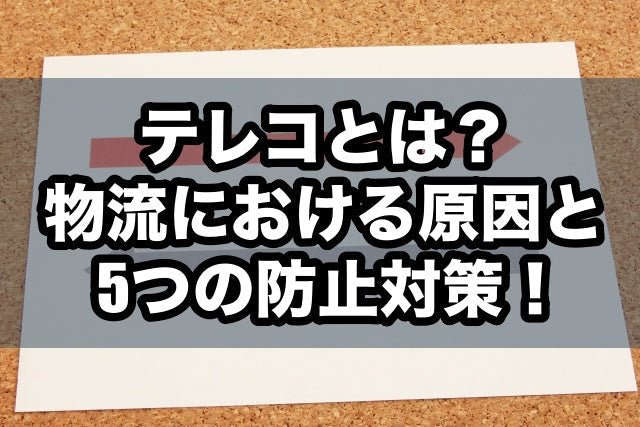
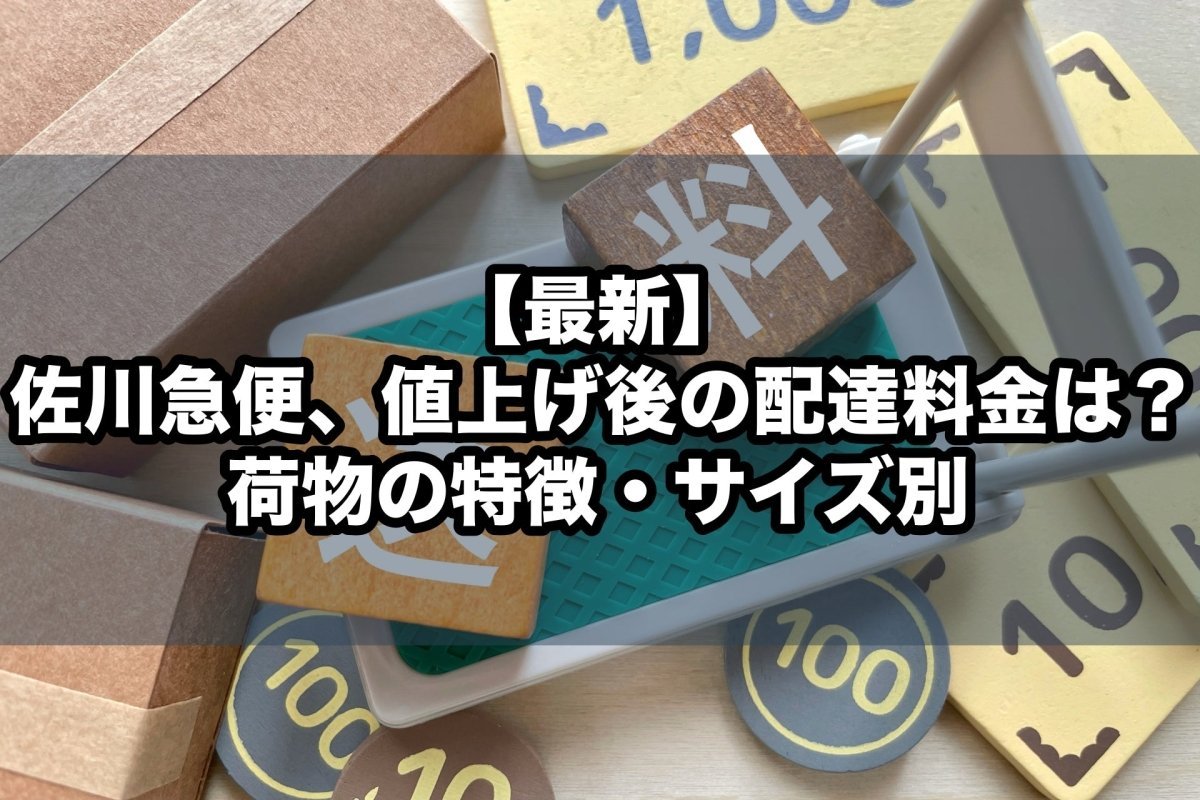
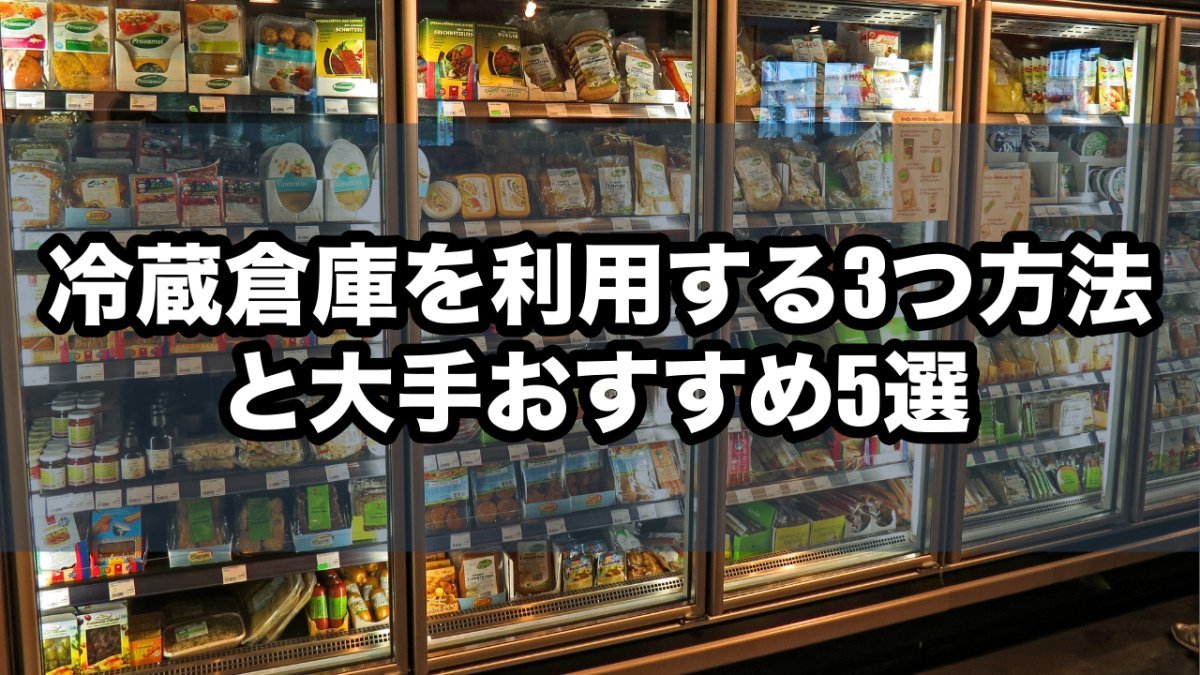

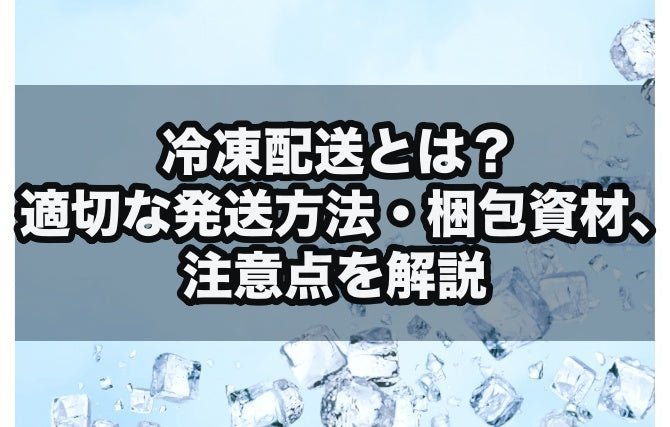
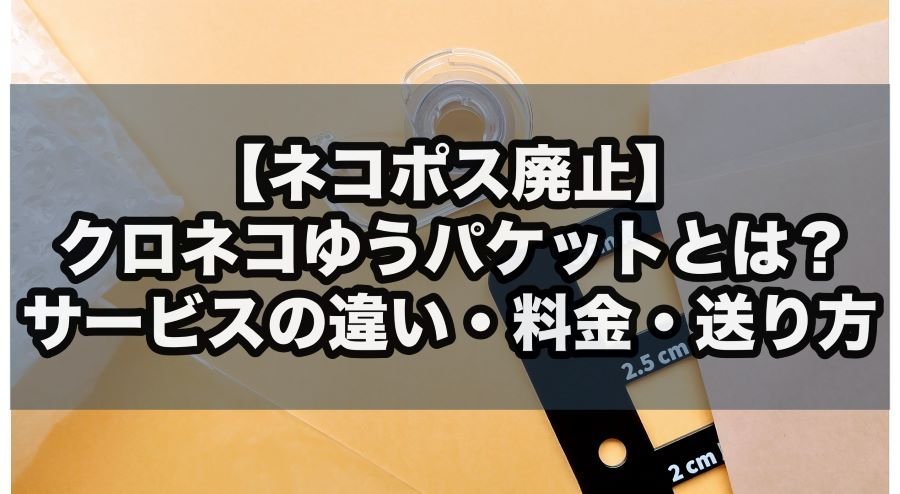







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)