ECロジスティクスとは?特徴と課題・改善のポイントを解説

近年、スマートフォンの普及によりオンラインで買い物をするスタイルが定着し、消費者の「早く・正確に商品を受け取りたい」というニーズがますます高まっています。
このような消費者ニーズに応えるには、商品をスムーズかつ効率的に届けるためのECロジスティクスの整備が欠かせません。
本記事では、ECロジスティクスの基本的な仕組みから実際の業務の流れ、よくある課題とその改善策までをわかりやすく解説します。
これからEC事業を始めたい方や物流の最適化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ECロジスティクスとは
ここでは、ECロジスティクスを正しく理解するために、以下の3つのポイントを解説します。
- ECロジスティクスの概要
- ECロジスティクスとEC物流の違い
- ECロジスティクスの重要性
ECロジスティクスとは、EC事業における仕入れから商品が顧客に届くまでの一連の流れを指します。単なる配送にとどまらず、経営管理やコスト管理などを含んだ総合的な仕組みです。
ECとは電子商取引(Electronic Commerce)の略称で、インターネットを利用して商品やサービスの売買を行う取引形態です。ネット通販やサブスクリプションサービスがあり、ECサイトにはAmazonや楽天市場などのマーケットプレイス型と、企業やブランドが自社で運営する自社EC型があります。
インターネットやスマートフォンの普及によりEC事業は成長しており、それに伴い効率的な商品配送を支える仕組みとしてECロジスティクスの重要性が年々高まっています。
ECロジスティクスとEC物流の違い

ECロジスティクスとEC物流は、どちらも電子商取引に関連する物流の概念ですが、その仕組みや定義には明確な違いがあります。EC物流は、商品の入出荷、保管、梱包、発送といったEC取引におけるモノの流れを指す言葉です。
一方でECロジスティクスは、より広範な概念で原材料の調達から商品の生産、販売、回収品までを一元管理し、最適化する仕組みを指します。そのため、単にモノを運ぶだけでなく、需要と供給の適正化といった戦略的な領域までが対象となるのが大きな特徴です。
つまり、EC物流は商品の輸送や保管業務、荷役など部分的な機能を表すのに対し、ECロジスティクスはこれらの機能を効率的に計画・実行・管理することを指しています。したがって、EC物流はECロジスティクスに含まれる要素の一つであるといえるでしょう。
ECロジスティクスをアウトソースすると、商品やサービスが消費者に届くまでの全過程を最適化し、EC事業全体の競争力強化につながります。
出典:物流用語_JIS
<関連記事>「通販物流(EC物流)とは?特徴や課題、4つの改善方法を徹底解説」
ECロジスティクスの重要性
インターネットの普及により、消費者は時間や場所を問わずいつでも商品を購入できるようになり、顧客のニーズが多様化しています。特に「より高品質な商品を早く受け取りたい」といった利便性とスピードを重視する傾向が強まっています。
こうしたニーズに対応するには、市場動向を的確に把握してサービスの品質を高め、他社との差別化を図るためのECロジスティクスの整備が不可欠です。一方、ECロジスティクスが不十分な場合は、以下の問題が発生しやすくなります。
- 的確な需要予測が立てられず、過剰在庫や欠品が発生するリスクが高まる
- 出荷体制が不十分で、配送遅延による顧客満足度の低下を招く
さらに、国内のEC市場は年々拡大しており、2024年の市場規模は24.8兆円、特に物販系分野は14.8兆円と大きな割合を占め、今後もさらにECロジスティクスの重要性が高まると予想されています。
ECロジスティクスの運用体制の特徴

ECロジステティクスには、以下のような特徴があります。
- 個人向けの小口配送が中心
- 配送先が多く全国に分散
- 専門知識を活かした物流管理
- 同梱物による顧客へのアプローチ
- 迅速な返品対応
これらの運用体制の特徴を詳しく見ていきましょう。
個人向けの小口配送が中心
EC事業ではBtoC向けが多く、顧客が少量の商品を注文するため個人向けの小口配送が中心です。これは、幅広い顧客層に対応するECショップならではの運用スタイルです。
令和5年の宅配便取扱個数は50億733万個で前年比で約0.3%増加しています。令和元年の約43億個から比較すれば約14%増加しており、小口配送の需要の高まりと、EC市場がさらに拡大していることが分かります。
個人向けの小口配送では、1件ごとの注文に応じてピッキング、梱包、流通加工、発送業務が必要になるため、物流現場では効率的なオペレーションが求められます。そのため、これらの業務を効率的に処理できるECロジスティクスの運用体制の強化が不可欠です。
出典:令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について|国土交通省
配送先が多く全国に分散
EC事業では、実店舗とは異なり全国から注文が入るため、配送先が全国に分散しているのが特徴です。BtoBでは企業や物流センターに荷物をまとめて納品する方法が一般的ですが、BtoCの場合は一般消費者が個別に注文するため、それぞれの指定先へ正確に商品を届ける必要があります。
そのため、多くの配送先を管理しなければならず、ピッキングミスや誤発送のリスクも高まります。さらに、即日出荷、翌日配送、日付指定、置き配、コンビニエンスストア受け取りなど、多様な配送ニーズへの対応も求められます。
配送ニーズへの的確な対応は顧客の満足度やリピート率にも大きく影響するため、ECロジスティクスの活用は欠かせない要素といえるでしょう。
専門知識を活かした物流管理
食品や医薬品を扱うEC事業者は、品質を維持するために適切な温度管理が不可欠です。
また、アパレルECではカラーやサイズなどバリエーションが多く、正確な在庫管理が求められます。素材によってはシワを防ぐためのハンガー保管やプレス加工、商品品質を保証するための検針作業など専門的な対応が必要となるケースもあります。
このようにEC事業者は、専門知識を活かした高度な物流管理を含めたECロジスティクスの整備が必要です。
<関連記事>「食品ECとは?市場規模や課題、事業を成功させる5つ秘訣を解説」
<関連記事>「アパレルECの市場規模と成功事例!5つの課題と対策も紹介」
同梱物による顧客へのアプローチ
ECロジスティクスでは、顧客との関係構築に向けた販促活動である同梱物の活用も重要な役割のひとつです。例えば、サンプル品やキャンペーンチラシ、クーポン券、サンクスレターなどを商品と一緒に同梱することで、再購入の促進やリピート率の向上につながります。
ただし、効果を最大化するためには、顧客の過去の購入履歴や属性をもとに、パーソナライズされた同梱物への対応が求められます。同梱物による顧客へのアプローチを物流プロセスに組み込み、効率よく実行できるのがECロジスティクスの大きな強みといえるでしょう。
<関連記事>「初回同梱物が通販の売上げを伸ばすワケとは?役割と10のツール事例」
迅速な返品対応
EC事業において「イメージと違った」「サイズが合わなかった」といった顧客都合の返品も少なくありません。そのため、スピーディかつ柔軟な返品対応もECロジスティクスに欠かせない要素のひとつです。
返品対応には、返送品の受付、返金、交換の手続き、在庫管理、顧客からの問い合わせ対応など幅広い業務が発生します。返品対応をスムーズに処理するには、専門の人材や効率的な業務フローの整備が必要です。
そのため、ECロジスティクスをしっかりと構築しておくと、スムーズで柔軟な返品対応が実現し、顧客からの信頼度も高まるでしょう。
<関連記事>「返品・交換の物流構築が売上に繋がるワケ!顧客体験向上のメリットを解説」
ECロジスティクスの主な業務内容

ECロジスティクスの主な業務内容は、以下のとおりです。
- 供給管理
- 倉庫管理
- 在庫管理
- 受注処理
- 配送管理
- アフターフォロー
順番に解説します。
供給管理
供給管理とは、商品を効率的に仕入れるためのプロセスです。信頼できるサプライヤーを選定し、価格交渉や納期調整、市場動向の把握、需要予測を通じて計画的に対応します。
安定した供給体制を整えると、欠品防止や在庫回転率の向上につながります。
倉庫管理
倉庫管理は、商品の入庫から出庫までを管理する業務です。具体的には、入庫、検品、棚入れ、保管、ピッキング、流通加工、梱包、出荷作業などが含まれます。
現場では、バーコードリーダーやピッキングシステムロボットなど自動倉庫の導入に加え、倉庫内の効率的なレイアウト設計や作業動線の工夫、商品特性に合った保管方法など、作業効率を高める対策が求められます。
在庫管理
在庫管理は、過剰在庫や欠品を防ぐために在庫量を適正に管理する業務です。在庫管理システムを活用すると、在庫数の把握と物流コストの最適化が可能になります。
受注処理
受注処理は顧客からの注文を受け、商品を正確かつ迅速に出荷するためのプロセスです。受注内容の確認から出荷指示までの一連業務を正確かつスピーディに処理できると、顧客満足度の向上につながります。
配送管理
配送管理は、梱包された商品を配送業者に引き渡し、顧客の指定した住所へ発送する業務です。配送状況をリアルタイムで追跡できるシステムの活用により、トラブルの防止や信頼性の向上が期待できます。
アフターフォロー
購入後のアフターフォローもECロジスティクスの重要な業務のひとつです。返品、交換対応に加え、製品保証や修理サービス、商品到着後の感謝のメッセージや使用方法の案内送付などにより顧客への安心感を高められます。
顧客からの問い合わせ内容を収集、分析を行うと、サービスや商品の改善にも役立てられます。
ECロジスティクスにおける4つの課題

ECロジスティクスでは、以下のような課題が発生しやすい傾向です。
- 在庫管理が煩雑化しやすい
- 配送までのリードタイムが長くなる
- 人員確保が難しく運用が不安定になる
- 物流コストがかさむ
4つの課題を詳しく解説します。
課題1.在庫管理が煩雑化しやすい
EC事業では、異なる商品を少量ずつ保管する必要があり、在庫管理が複雑化しやすい点が課題です。特に、季節商品は需要予測が難しく、在庫切れによって販売機会を逃がすリスクも高まります。
また、複数の販売チャネルを運営している場合は、在庫管理が不十分だと在庫数の不一致が発生しやすくなります。欠品であるにもかかわらず、誤って受注するようなミスが発生すれば、謝罪や在庫の調整が必要になるだけでなく、顧客からの信頼を損ないかねません。このように在庫管理が煩雑になると、業務フロー全体が非効率になりヒューマンエラーを引き起こす要因となるため、在庫管理体制の見直しが必要です。
課題2.配送までのリードタイムが長くなる
供給の遅れにより在庫切れや倉庫作業の停滞が発生すると、商品が顧客に届くまでのリードタイムが長くなる点がECロジスティクスの課題です。特に、繁忙期には出荷件数が急増するため、人員確保が難しい倉庫では配送遅延につながるケースもあります。
さらに、配送拠点と顧客の住所が離れている場合は、物理的に時間がかかるため迅速な配送を求める顧客ニーズに対応しづらくなります。
課題3.人員確保が難しく運用が不安定になる
EC事業では、入荷、検品、梱包、出荷、返品対応など多様な業務内容が特徴です。また、温度管理やSKUの多い商品の在庫管理、オリジナルの流通加工業務など専門性が求められます。
加えて、繁忙期や閑散期の波が激しい商材は、適切な人員確保が難しく、結果として運用が不安定になる場合もあるでしょう。パートやアルバイトなどの短期雇用では、教育コストがかかり作業ミスや誤出荷のリスクも高まりやすくなります。
課題4.物流コストがかさむ
近年は燃料費の高騰や2024年問題によるドライバー不足の影響により、配送コストが増加傾向です。また、EC物流では返品対応も多く、それに伴う人件費や梱包資材費が膨らみやすいことも課題です。
また自社倉庫の場合は光熱費や維持費といった固定コストが発生し、全体的な物流コストの負担が大きくなります。そのため、システムの導入や外部委託によるリソースの最適化など、ECロジスティクスの効率的な運用が求められます。
ECロジスティクスの課題を改善するポイント

前述した課題を改善するためには、ECロジスティクスの整備が欠かせません。ここでは、ECロジスティクスの課題を改善するために押さえておきたいポイントを、以下で詳しく解説します。
- 物流業務のフローを見直す
- ITツールを導入し業務効率化を図る
- 消費者ニーズの把握と分析を行う
- 物流代行サービスを活用する
物流業務のフローを見直す
まずは、現在の業務のフローを正確に把握します。作業員からのフィードバックを収集し、どの工程に無駄や非効率があるのかを洗い出すことが重要です。改善の余地がある部分を明確にしておくと作業の効率化が図れます。
また、出荷頻度の高い商品を取りやすい場所に配置し、作業員の移動時間を削減する倉庫内のレイアウトの見直しも効果的です。商品を分類する際はABC分析の活用がおすすめです。
|
分類 |
特徴 |
レイアウト方法 |
|
A |
出荷頻度が高い |
作業同性の最も近い棚に配置 |
|
B |
中程度の出荷頻度 |
中央部に配置 |
|
C |
出荷頻度が低い |
倉庫の奥や高所に配置 |
このように、商品をABCの3種類に分類して管理を行えば、無駄な動線や在庫の滞留を減らし、倉庫全体の運用効率を向上できるでしょう。
ITツールを導入し業務効率化を図る
ECロジスティクスの課題を改善するには、ITツールの導入が効果的です。特に、ピッキングや配送、在庫管理、流通過程の追跡をシステム化すると、人的ミスや作業の効率化につながります。
代表的なITツールは、以下のとおりです。
|
主なITツール |
用途 |
特徴 |
|
倉庫管理システム(WMS) |
入出庫管理・在庫管理・ロケーション管理 |
倉庫内の作業を可視化し、作業効率と精度を向上させる |
|
デジタルピッキングシステム |
商品のピッキング作業支援 |
ランプや音声で作業指示を出し、作業スピードと正確性を高める |
|
輸配送管理システム(TMS) |
配送ルートや車両の管理 |
配送の最適化によりコスト削減やリードタイムの短縮が期待できる |
|
トレーサビリティシステム |
商品の流通履歴の追跡 |
商品の流れを記録・管理し、クレーム対応や品質管理に役立つ |
ITツールを適切に運用すると、日々の業務が効率化されるだけでなく、業務全体の可視化や分析が進み、企業の経営改善にも役立ちます。
<関連記事>「物流DXとは|物流業界の課題やDX推進へのポイント、事例を解説」
消費者ニーズの把握と分析を行う
消費者ニーズの把握と分析も、ECロジスティクスを最適化するうえで欠かせないポイントです。例えば、過去の販売データを分析すると需要の変動を予測でき、適切な在庫計画や仕入れに反映できます。
さらに、閲覧履歴や購買履歴などのデータから顧客の関心を読み取り、ターゲットに応じたクーポンの発行やチラシの同梱により、リピート率の向上も期待できます。こうした顧客ニーズの分析は物流戦略に活かせるため、サービス品質の向上にもつながり、競合他社との差別化を図れるでしょう。
物流代行サービスを活用する
ECロジスティクスにおける課題のひとつに、物流コストの増大があります。この課題を解決する方法として、物流業務のアウトソーシングがおすすめです。
物流代行サービスを活用すれば、入荷から出荷、在庫管理までの一連の業務を外部委託でき、人件費や教育コストを削減できます。また、物流専門のノウハウを持つ業者を選定すると、作業品質が安定し、誤出荷や遅延といったトラブルの防止にもつながります。
外部委託により自社の従業員は、商品開発やマーケティング、カスタマーサポートなど戦略的な業務にリソースを注力できる点がメリットです。ただし、取り扱う商品の種類や特性に対応できるかは業者によって異なるため、自社の商材に適した代行業者を選ぶことが重要です。
<関連記事>「EC物流代行サービスとは?業者の選び方とおすすめ代行会社15選を紹介」
ECロジスティクスの最適化に向けて、物流のアウトソーシングを活用しよう

EC市場は成長分野であり、今後さらに重要性が増しています。まずは、自社が抱える課題を洗い出し、業務フローの見直しが第一ステップです。
富士ロジテックホールディングスでは在庫管理から梱包、発送までをトータルで委託でき、冷凍・冷蔵・常温・定温の4温度帯に対応も可能です。365日出荷や返品対応サービス、ギフトラッピングなどの顧客ニーズに応じたサービスも充実。在庫水準の適正化するためのご提案や、受注処理からのフルフィルメントサービスにも対応しており、
ECロジスティクスの強化につながります。
物流の最適化に向けて、専門性の高いパートナーを選ぶことでECビジネスの成長を支える重要な一歩となるでしょう。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
森恵
貿易事務と物流代行営業の経験を活かし、専門知識に基づいた記事作成を行っています。お客様に寄り添い、分かりやすく役立つ情報を提供します。
タグ一覧
カテゴリー


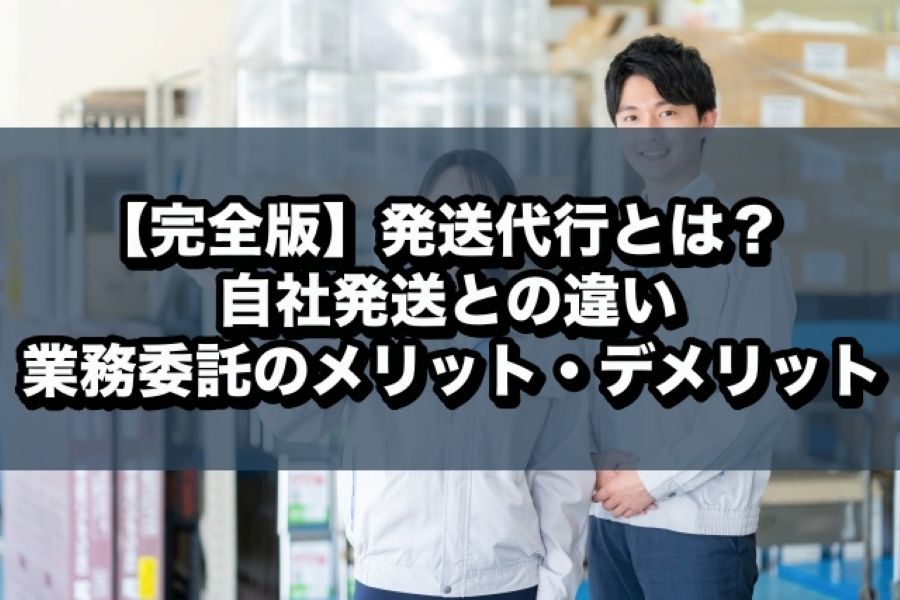

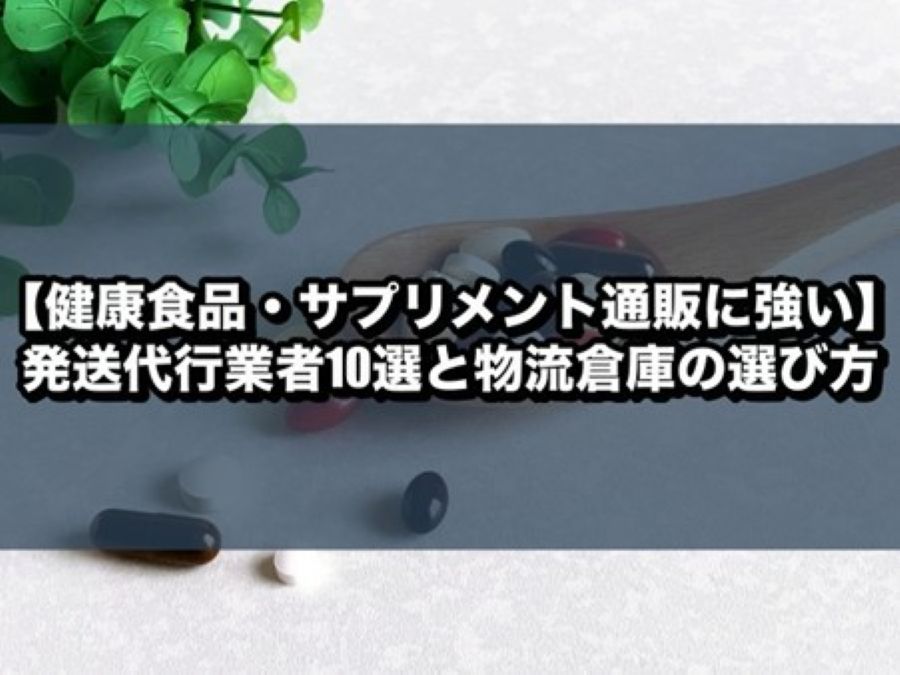
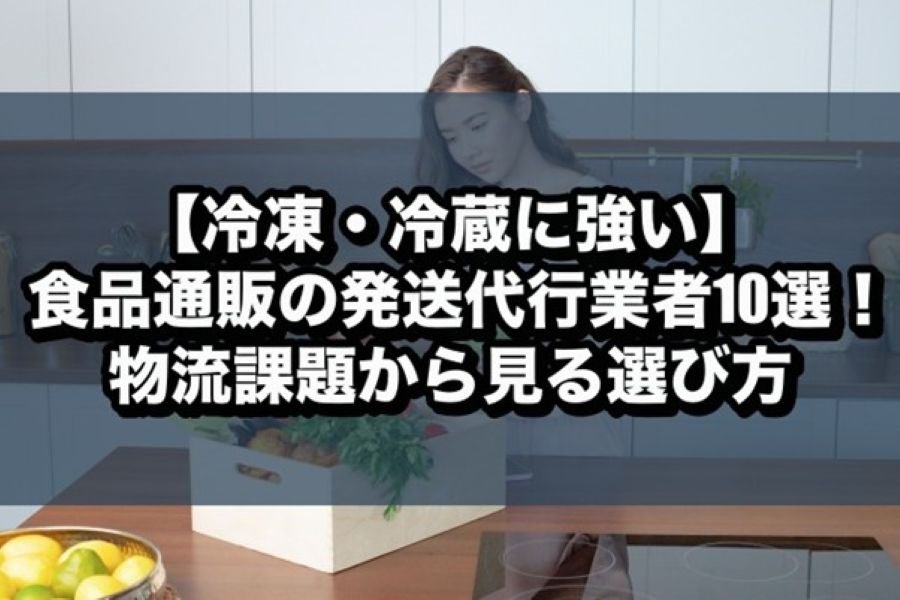

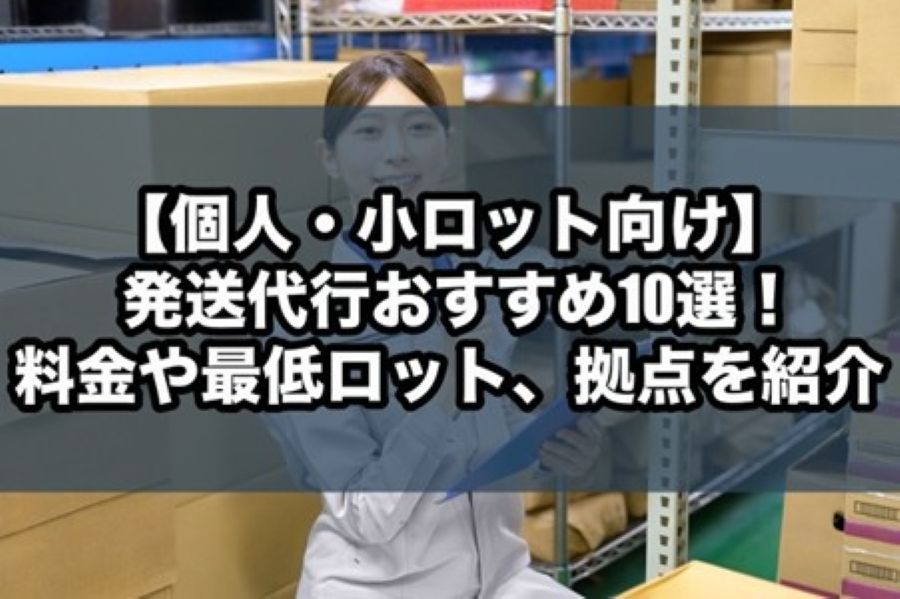
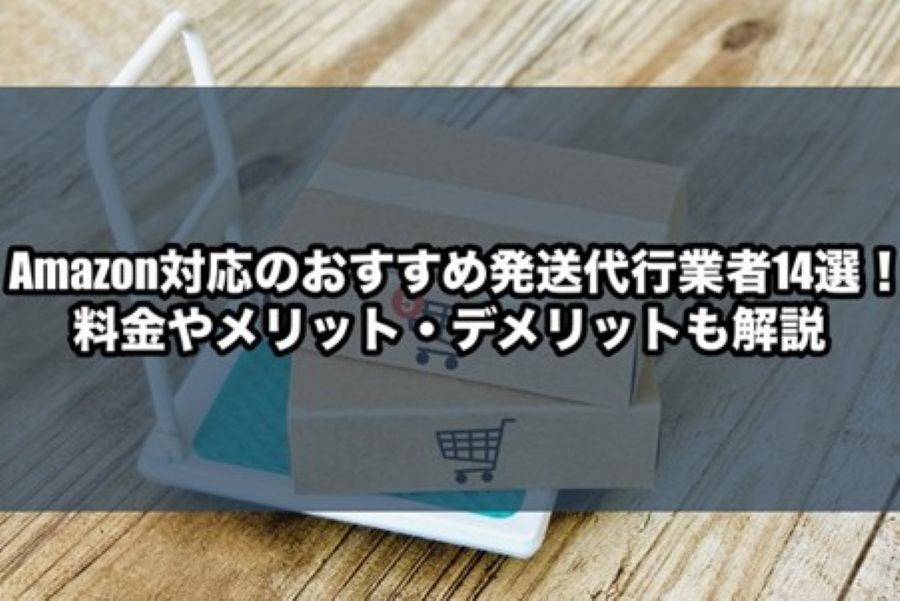
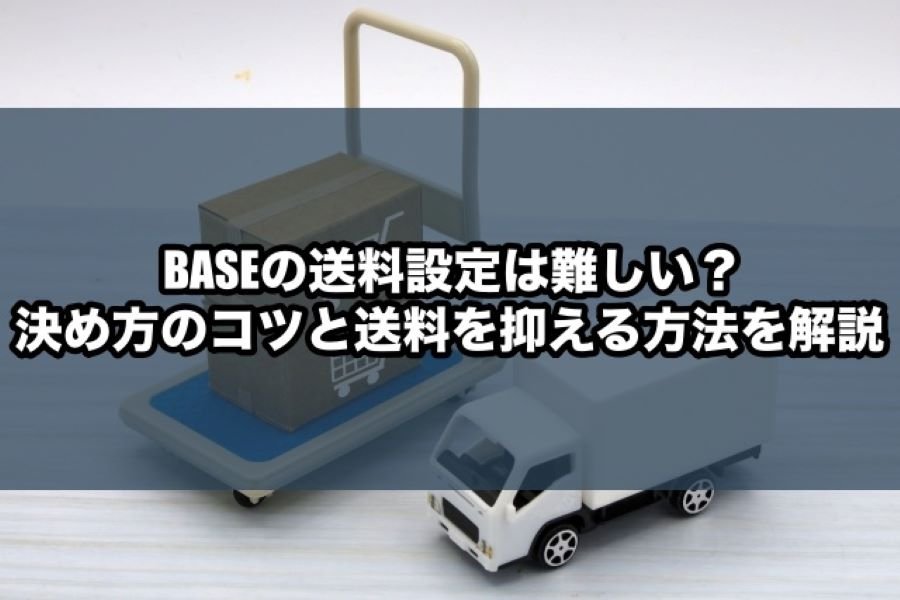







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)