
国内外のECをはじめ、リユース、美容・健康、音楽などあらゆるジャンルで執筆中のフリーランスライター。中国への留学経験を生かし、13年間、繊維製品や楽器、雑貨の輸入業務に携わる。現在はライター業のかたわら、個人で越境ECのセラーとしても活動中。

ギフトECはソーシャルギフトの需要拡大とともに、今後成長が見込めるECの形態です。
本記事では、今後参入をお考えのかたに向けてギフトECのメリットとデメリット、構築や運用のポイントを解説します。
ギフトECとはギフトに特化したECサイト
ギフトECとは、ギフトを専用で取り扱うギフトに特化したECサイトを指します。
ラッピングやメッセージカード、熨斗などのギフトに不可欠なサービスが整っているのが特徴です。
またお祝いしたい日に届ける配送日の指定や、分割配送にも対応しているサイトが多い点も特徴としてあげられます。
今後ギフトEC市場規模は拡大する見込み
ギフト市場の調査報告によると、今後ギフトECは拡大する見込みです。
ギフト市場全体でみると、コロナ禍の影響で2020年は出産祝いや結婚祝いなど人と対面するイベントでのギフト需要が減少しています。
一方、人と会えない代わりに友人や離れて暮らす家族に手軽にプレゼントを贈り合うカジュアルギフトの需要が増えました。
その後「ソーシャルギフト」が台頭します。ソーシャルギフトとは、メールやSNSで送れるギフトのこと。LINE ギフトやAmazonギフトカードなどの電子ギフトを指します。このソーシャルギフトの登場も手伝って、カジュアルギフトはコミュニケーション手段として定着しつつあります。
結果、新型コロナウィルスが収束しつつある2022からはフォーマルギフトの回復と同時に市場全体が盛り返している傾向に。

引用元:株式会社矢野経済研究所「ギフト市場に関する調査を実施(2022年)」
またギフトの購入場所についておこなった調査では、4人に1人以上が「ギフト特化型のECサイト」で購入していることが明らかになりました。

以上2つの調査結果から、今後はギフト市場の盛り返しとともにギフトEC市場が拡大する見込みです。
これからギフトECに参入をお考えの方や企業のご担当者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。以下、ギフトECのメリットや構築・運用のポイントについても解説していきます。
ギフトECのメリット

ギフトECのメリットについて、以下3つに分けて解説します。
- リピーターがつきやすい
- サイト認知度の向上と新規顧客の獲得
- ユーザーの利便性が高い
リピーターがつきやすい
ギフトECには、一般のECサイトに比べてリピーターがつきやすいという特長があります。
ギフトを贈る機会は年間を通して複数回あるため、一度利用したユーザーが次の機会にも同じサイトを利用する確率が高いからです。
カジュアルギフトの習慣が根付いたことで、ちょっとしたお礼などでもプレゼントを贈るようになり、リピーター獲得の機会はさらに拡大しているといえます。
リピーターを獲得するためには、ラッピングや配送面などギフト特有のサービスの使い勝手のよさは確保しておくことが不可欠です。
サイト認知度の向上と新規顧客の獲得
ギフトECの2つ目のメリットは、サイト認知度の向上と新規ユーザーを獲得できる点です。
プレゼントを購入する場合は、贈る相手の好みを想定します。その際、自分用に購入するときには選択肢に上がらなかった商品やサイトを知るきっかけになります。
同時にギフトを受け取った側も、ギフトECサイトの存在を知る機会が得られます。お返しや自分でギフトを選ぶ際に利用してみようというきっかけになるので、サイトの認知拡大と新規顧客の獲得につながりやすいといえます。
ユーザーの利便性が高い
ギフトに特化したギフトECでは、商品が選びやすく利便性が高いというメリットがあります。
ギフトEC内では、相手との関係性や年齢、贈るシーンなどのカテゴリ別に予めおすすめ商品がピックアップされていることが多いためです。
以下は、eBay Japan合同会社が全国の20代〜30代の働く独身女性500名を対象に「贈り物に関する調査」をおこなった結果です。

引用元:PR TIMES(eBay Japan合同会社 調べ)
プレゼントを選ぶ際に苦労した理由として、54.4%が「相手の欲しいものがわからない」45.7%が「じっくり悩むので時間がかかる」と回答しています。
この結果からも、ギフトに特化したギフトECなら商品を選ぶ時間が大幅に減らせるため、ユーザーの利便性が高いといえます。
ギフトECのデメリット

ギフトECでは、ギフト特有のラッピングやのし対応、分割配送対応など通常のECサイトよりも必要な機能が増えます。
当然ながら、必要な機能を追加すればするほどコストが高くなっていく点がデメリットです。
またソーシャルギフトにもデメリットがあります。LINEギフトなどのソーシャルギフトは受け取る側もインターネット操作に慣れていることが前提条件の形態です。ギフトの受取りURLに期限が設定されているため、操作に問題があり期限切れになってしまうケースもあります。
こうした理由からソーシャルギフトはシニア層にはややハードルが高く、ターゲットの年齢層が絞られる点もデメリットです。
ギフト ECを構築・運用する際の6つのポイント

ここからは、ギフトECを構築、運用する際のポイントを以下の通り6つご紹介します。
- ソーシャルギフト対応の機能を実装する
- ギフト梱包に細かく対応する
- 分割配送に対応させる
- 名入れ機能を実装する
- AIやおすすめ機能を実装する
- オンラインとオフラインで在庫を一元管理する
【1】ソーシャルギフト対応の機能を実装する
今後のギフトEC運営で外せないのが、ソーシャルギフトに対応することです。
住所を知らない相手にも気軽に贈れるので、Z世代の中でも需要が広まりつつあります。
なかでもソーシャルギフトの代表格、LINEギフトの売上は急激に拡大しています。2021年の総流通額は前年比の330%増で、累計ユーザー数が2,000万人を突破したと発表しました。

幅広い年齢層のユーザーを取り込むには、今後ソーシャルギフトに対応したギフトECサイトの構築が不可欠となるでしょう。
【2】ギフト梱包に細かく対応する
ギフトECの運営に必要なポイント2つ目は、ギフト梱包に細かく対応することです。
たとえば、ギフトラッピングやのし、メッセージカードの作成、封入があげられます。のしやメッセージカードは用途によって違いがあり種類が多く、その都度の対応では現場が混乱してしまいます。ある程度のフォーマットやメッセージのテンプレートを準備することでユーザーの利便性を高める工夫が必要です。
テンプレート以外の選択肢を用意するなど臨機応変に対応する場合は、現場への指示が難しくヒューマンエラーが発生しやすくなります。こうしたミスを防ぐためには、物流代行会社の利用もおすすめです。
富士ロジテックホールディングスの物流代行サービスでは、オリジナルの梱包資材や同梱物にも細かく対応できます。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。
富士ロジテックホールディングスのフルフィルメントサービスを見てみる
【3】分割配送に対応させる
ギフトECでは、分割配送が必須です。
ギフト配送の特徴として、複数の商品を同時に購入し一度に複数の住所に届けるということがよくあるからです。
たとえばお歳暮やお中元、結婚祝いのお返しなどは1回の注文で配送先が複数に分かれます。その際、ユーザーが配送先ごとに都度購入を行っていては多大な手間がかかってしまいます。
そのため、ギフトECでは一度の注文で複数の配送先の設定ができる機能が必要です。
【4】名入れ機能を実装する
ギフトでラッピングやメッセージカード以外にも外せないのが、名入れ機能です。
たとえば筆記用具などの雑貨やお酒など贈る相手の名前を入れるサービスをおこなうことで他のショップとの差別化できます。
具体的には、文字制限やフォントの選択、名入れ代金の上乗せなどを機能として追加する必要があります。
名入れ対応は流通加工ができる物流代行業者に問い合わせてみましょう。以下の記事で詳しく解説しています。
「流通加工とは?その種類と課題、物流倉庫に外注するメリット・デメリット」
【5】AIやおすすめ機能を実装する
ギフトECでは、贈る相手との関係性、シチュエーションや年齢をもとにあらかじめオススメをピックアップしておく必要があります。
前述したように、ギフトを選ぶ際には相手の欲しいものが分からない、選ぶのに時間がかかるという悩みが突出して多いからです。
予算に余裕があれば、AIで贈る相手の好きなものや年代、趣味などを分析しおすすめを抽出するツールを利用するのも便利です。
【6】オンラインとオフラインで在庫を一元管理する
実店舗を持つギフトECなら、オンラインとオフラインで在庫を一元管理しておく必要があります。
ユーザーの中にはECサイトで購入した商品を手渡しで贈りたい人もいるでしょう。そのようなニーズを取りこぼさないよう、店頭受取サービスに対応しておくのが理想的です。
また実店舗を持たないショップでも、催事や期間限定のポップアップストアなどのオフライン販売が想定できます。
これらの展開に対応するには、在庫切れを起こさないよう在庫情報の一元管理が必要です。
ギフトEC構築のプラットフォームを比較
ギフトEC構築のプラットフォームを、
- ECモールに出店する場合
- 自社で運営する場合
に分け、それぞれどのようなサービスがあるのかを見ていきましょう。
ECモールに出店する場合
1つ目のパターンは、ギフトECサイトを集めたECモールに出店する形式です。
モールにユーザーがついているため、ゼロから集客する必要がない反面、顧客情報を自社で管理できないデメリットもあります。
|
おもなサービス例 |
● ギフトモール ● LINEギフト |
|
メリット |
● モールの集客力を利用できる ● システム開発の費用がかからない |
|
デメリット |
● 販売手数料がかかる ● 自社システムなど外部との連携が難しい ● 顧客情報を直接管理できず自社にファンを取り込みにくい |
自社で運営する場合
クラウド型ASP
ASPとは、Application Service Providerの略。
カートや決済システムの他、ソーシャルギフト対応などギフトに必要な機能があらかじめ備わっているプラットフォームです。
|
おもなサービス例 |
● BASE ● STORES ● Shopify ● MakeShop ● futureshop ● aishipGIFT |
|
メリット |
● ITスキルが不要 ● 低コストで構築可能 ● 短期間で導入できる ● メンテナンスもASP事業者側が実施 |
|
デメリット |
● デザインや機能を自由にカスタマイズできない ● 自社システムなど外部との連携が難しい ● サービス利用料がかかる |
オープンソース型
ソースコード(プログラムの元になるデータ)が公開されているソフトウェアをアレンジして構築する方法です。
カスタマイズには高いIT技術が必要です。
|
おもなサービス例 |
● EC-CUBE |
|
メリット |
● ソースコードでサイトを自由にアレンジできる ● ショップの独自性が出せる ● 低コストでカスタマイズ可能 |
|
デメリット |
● ソースが公開されているので、セキュリティの脆弱性を狙ったサイバー攻撃にあうリスクがある ● ドメイン取得やサーバー契約の初期費用がかかる ● カスタマイズやメンテナンス、セキュリティ保守にはITスキルのある人材が必要 |
パッケージ型
ギフトECに必要な機能がパッケージングされたソフトウェアを自社サーバーにインストールし、ニーズに合わせてカスタマイズできます。
オープンソースのように元になるデータ(ソースコード)が開示されていないので、セキュリティ面で安心です。
|
おもなサービス例 |
● ecbeing |
|
メリット |
● 分割配送やラッピングなどギフトサイトに必要な機能が充実 ● カスタマイズ性が高い ● セキュリティー面でも安心 ● カスタマイズやサポートはベンダーに任せられる |
|
デメリット |
● 導入・運営コストが高額 ● 導入に数ヶ月はかかる ● システムのメンテナンスやリニューアルはベンダーとの密な連携が必要 |
フルスクラッチ型
他のサービスとは違い、既存のプラットフォームを使わずゼロからオリジナルのECサイトを構築する方法です。
高いIT人材が確保できて、自社の独自性を出したい企業に向いています。
|
おもなサービス例 |
● システム開発会社などに依頼 |
|
メリット |
● 自社のデザインの機能すべてを自由に構築できる ● 社内の計画を実行し、問題点を改善しやすい ● オムニチャネル化など販売戦略を展開しやすい |
|
デメリット |
● 開発期間が長期にわたる ● 開発費用が高額 ● アップデートやメンテナンスにハイレベルのIT人材の確保が必要 |
<関連記事>「D2C/ECサイト構築システムの比較!注目の手法ASPとクラウドECとは」
ギフトECにはアウトシーシングもおすすめ!サイト構築から物流までフルサポート

ギフトEC成功の秘訣は、ギフトに特化したサービスに対応することにより顧客の利便性を高めることです。
ギフト特有のサービスには、
- ソーシャルギフト対応
- ラッピング・のし・メッセージカード
- 分割配送
- 名入れサービス
- ギフトおすすめ機能
などがあげられます。
なかでもラッピングやのし、メッセージカードの対応はギフトECにおいて、最も悩みやすいポイントです。なぜなら、システムでの対応以外にも物流加工の現場に対し煩雑な作業の指示を的確におこなう必要があるからです。
そのためギフトECには、アウトソーシングの検討をおすすめします。富士ロジテックホールディングスでは、きめ細かい梱包作業やメッセージカードのアレンジ、封入にも柔軟に対応しています。これまでサブスクリプションや各種EC事業において、顧客体験を重視したオリジナルデザインの梱包や同梱物の封入サービスで数々の実績を積み上げてきました。
多様なECカートシステム・モールとスムーズに連携できる環境を用意しているため、出荷指示の手間も簡略化できます。
これから参入をお考えの方には、ECサイトの立ち上げを支援するパートナーの紹介も可能です。
ギフトECにすでに参入済みで梱包サービスに問題をお抱えのかたも、ぜひいちど弊社にご相談ください。
<関連記事>「EC自動出荷の仕組みとは?一般的な物流代行との違い、メリット、注意点を解説」
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

ライター
オガミキヨ
国内外のECをはじめ、リユース、美容・健康、音楽などあらゆるジャンルで執筆中のフリーランスライター。中国への留学経験を生かし、13年間、繊維製品や楽器、雑貨の輸入業務に携わる。現在はライター業のかたわら、個人で越境ECのセラーとしても活動中。
タグ一覧
カテゴリー


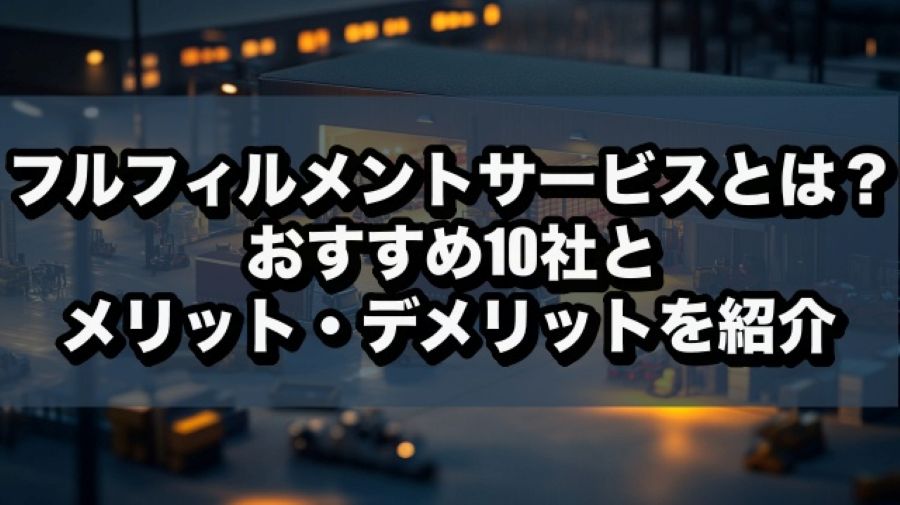
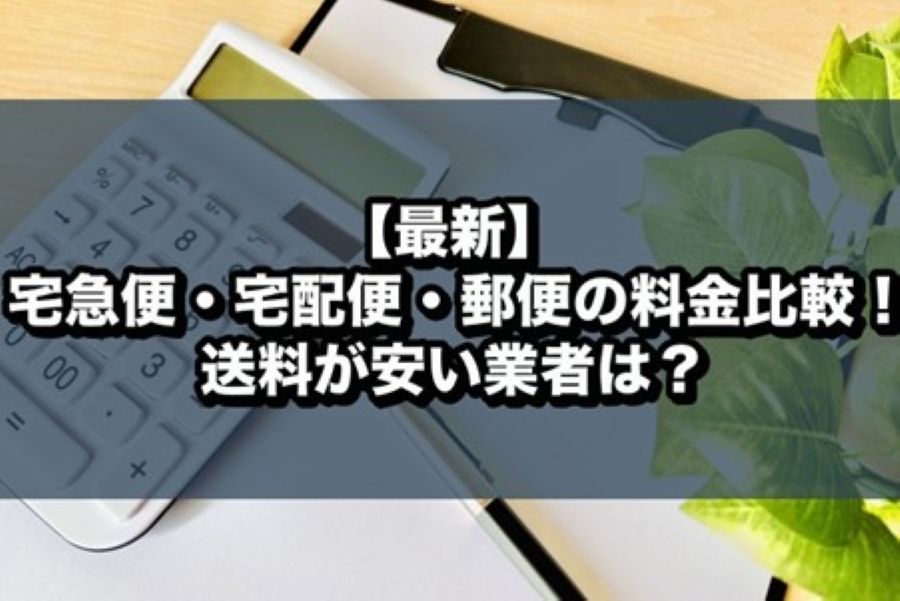
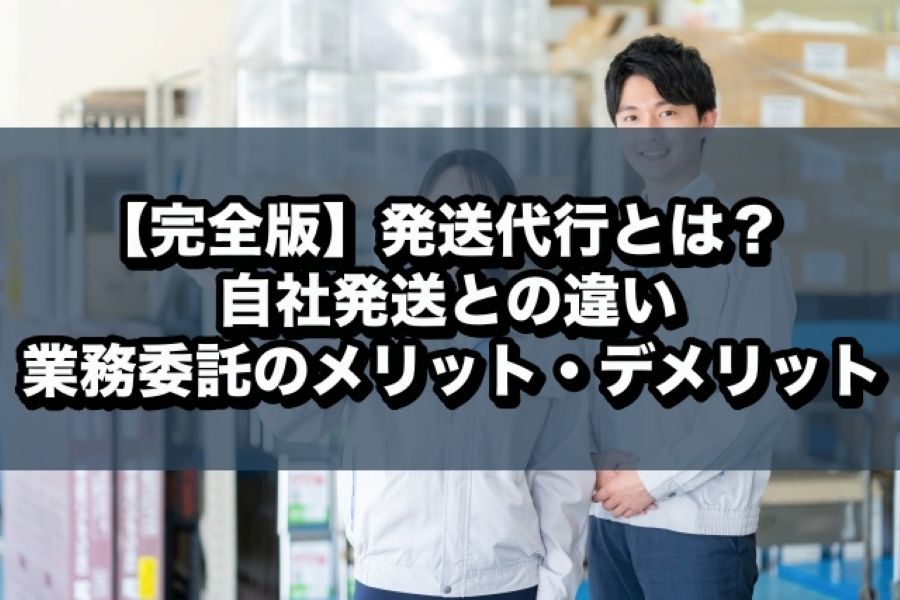

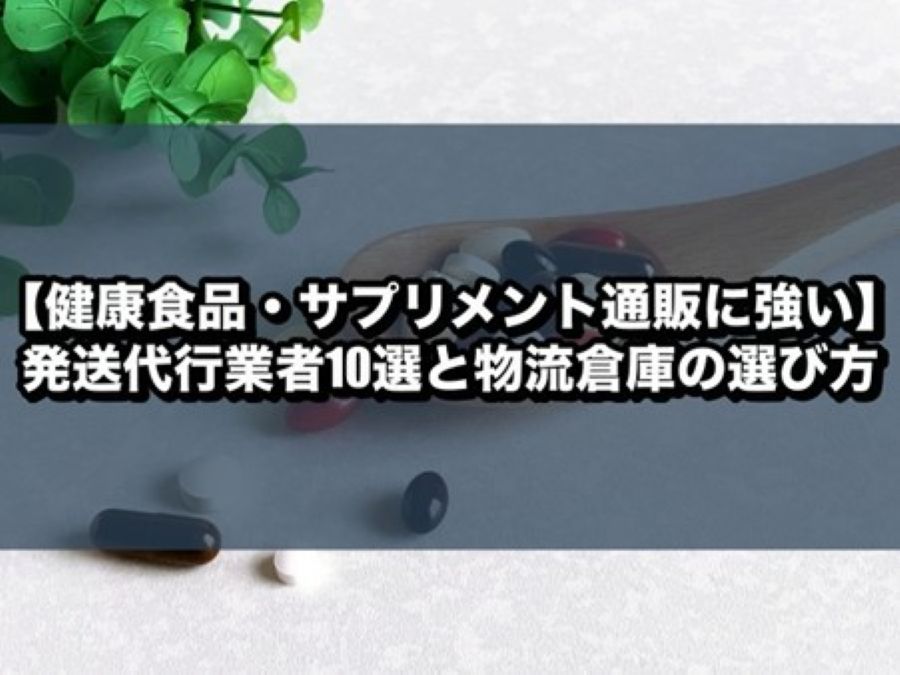
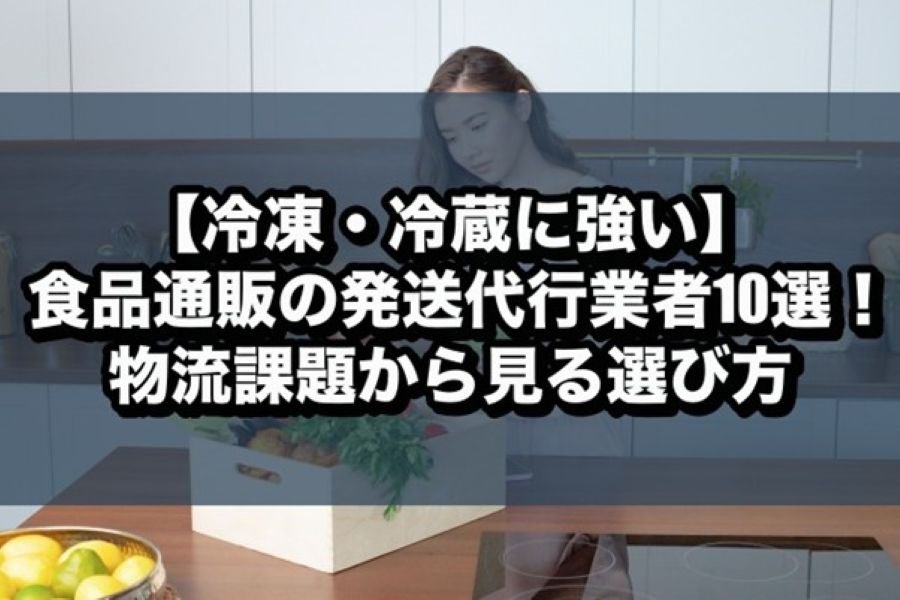

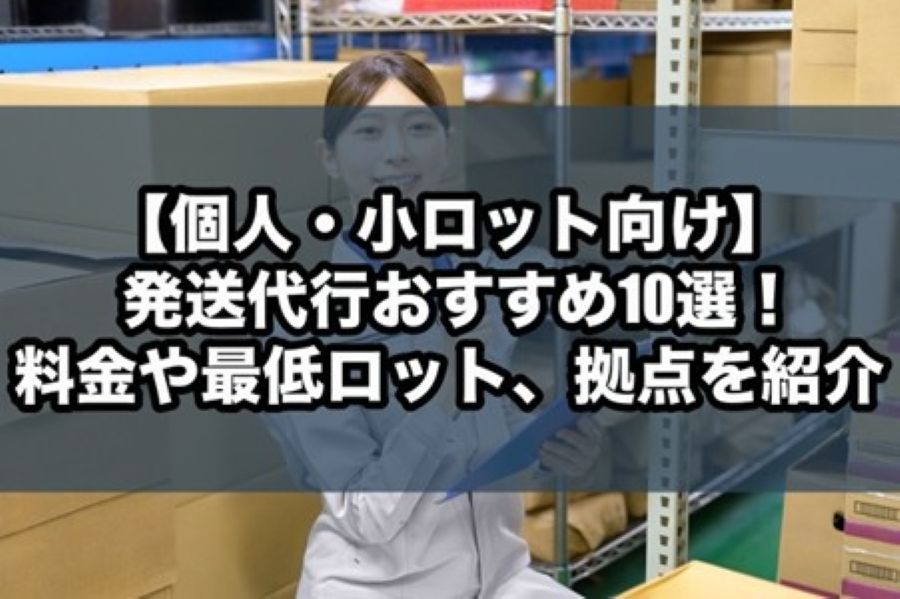







![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)