
物流会社で20年経験しD2C EC スタートアップから中規模、大規模のeコマース事業者へフルフィルメントサービスの提供や物流の見直し・改善、スピード配送、複数拠点展開を設計して提唱している。 事業者様の売上貢献するために、常に伴走して最新の物流設計を試みる。
D2C/eコマース/OMO ビジネスモデル シリーズ

「DNVB(Digitally Native Vertical Brand)」のことを日本では「D2C」と表現すること多いです。(海外では、DTC:Direct to Consumer)がしかし、バズワードとして呼称として使っているだけで、日本におけるD2Cの意味は、
- 「メーカーがeコマースで何かを売る」
- 「SNSを使ってダイレクトコミュニケーション・マーケティングをする」
- 「だから、儲かる」
という定義になっています。
日本でこのビジネスモデルは、「単品リピート通販」(今*サブスクリプションと言い換えていますがバズワード)では、として広く採用されていたモデルと差異はありません(アパレルを除く)。
一方で「DNVB」を本質的に追い求めている事業者も少しずつではありますが、生まれてきていることは見受けられます。いよいよ日本の商習慣や日本の顧客の特性に合わせてDNVBを作っていく環境が認知されてきたのかもしれません。
今回は、「DNVB」と「D2C」とはどのようなビジネスモデルなのかについて考察していきたいと思っています。
参考データ
米国のネット広告業団体「IAB(Interactive Advertising Bureau/インタラクティブ・アドバタイジング・ビューロー)」でさえ3年前から「デジタルネイティブなバーティカルなブランドこそが、メディアであり、メディア戦略である」というレポートを出しています。
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/02/IAB_Direct-Brand-Economy-2019-Report-Short-Form-2019_2_11_FINAL-3.pdf
ビジネスモデル「DNVB(Digitally Native Vertical Brand)」について
DNVBとはデジタルネイティブ世代を対象にWebで商品やサービスを提供し、ブランド展開していくビジネスモデルです。
デジタルネイティブ世代とは、
一定の層を世代という言葉でくくると共通した傾向が見られるので、よくマーケティング的に定義されています。
古い世代から、
- 団塊の世代
- 新人類世代
- 団塊ジュニア
- 就職氷河期世代
- ゆとり世代
に続く世代層になります。

特徴としては、生まれてから物心がつく頃にはインターネットをはじめとしたIT技術やパソコン、スマートフォンといったIT製品が普及した環境に育ったデジタルネイティブと言われています。

具体的には、
ミレニアル世代(Y世代):
1980年代~1995年ごろに生まれた2000年代に成人・社会人となる世代
Z世代:
1995年以降に生まれた年齢層です。
第2次大戦後に生まれたX世代、20世紀終盤に生まれたミレニアル世代(Y世代)の次の世代ということでZ世代です。
ミレニアル世代が小売業にとって重要な理由
同じデジタルネイティブな世代の中でも、ネットやテクノロジーの利用の仕方には異なる傾向がみられます。物心がついたころからインターネットや携帯といった「デジタル機器」が身近にあった世代です。
DNVBは、価格やデザイン・性能といった商品自体(モノ)をアピールする、従来型のマーケティング手法と異なり、商品よりも対象となる顧客層からの共感、自社ブランドの価値向上(コト)に重点を置いていて、世界観の醸成を目的とされているのが特徴でもあります。
マーケティング&コミュニーションとしては、Webサイト(ブランドサイト)上のオウンドコンテンツやSNSが重点的に利活用されています。
SNSを利活用することで、共感した顧客層によって自社のコンテンツや、顧客が作成したコンテンツが拡散(バイラル)されブランドの認知度、好感度などが向上する循環する仕組みを目指しています。
*ミレニアル・Z世代の最新トレンドについては、ビートラックスさんのこちらの記事に詳しく解説されています。
記事より
Z世代の特徴 具体的な行動・志向
- 特徴1:新しいテクノロジーにも順応に対応する
- 特徴2:オンラインでのソーシャル性の高さ
- 特徴3:利用サービスの移り変わりが激しい
- 特徴4:8秒しか保たない集中力
- 特徴5:共通のUIに慣れ親しんでいる
- 特徴6:ブランドイメージよりもブランドの活動内容を重視
- 特徴7:高い社会貢献に対しての意識
- 特徴8:環境に対しての意識も高い
- 特徴9:仕事に関しては会社の将来性と自分のスキルが高められる場所を優先
ビジネスモデル「D2C」について
日本では、D2C(本来的にはDTC:Direct to Consumer)と呼ばれるビジネスの形態になります。
事業者、既存企業が自ら商品を企画・製造し、自社の独自のチャネルで、直接顧客に提供するビジネスモデルのことと定義しておきます。
日本では「サブスクリプションコマース・サービス」という表現を選択することも多いです。
月々定額(費用)で、一定の商品を定期間隔(指定)配送するD2C型のビジネスを展開している事業者・企業があります。
そういった意味で、D2Cは「従前からある:単品リピート通販モデルとどう違うのかは、事業者からの顧客からも疑問の残るモデルでもあります。」としても、
単品リピート通販モデルは、日本固有・発祥のモデルでもあり、良い意味だけではなく、悪い意味でも顧客からの評価が劣悪でもあることなどからも反面教師としてわかるように、かなり普及していたモデルです。
DNVBモデルの顧客価値観の変化などについて
①ブランド購買体験価値の提供
また、従来の、小売・流通などの仲介業者を利用しないことも可能なので自社の「世界観」を思いきり表現することが可能と言われています。

②顧客購買体験や態様変化をファーストパーティデータ(一次情報)から得られる

DNVBは本当に必要とされているか、必要とされるために
生産消費者(プロダクション(生産)とコンサンプション(消費)の融合従来の定義である、消費者はもはや少数派なのかも知れません。
「欲しいものを購入して手に入れる」
という消費形態は、自分自身に置き換えても体験としてはハッピーではありません。また、企業から獲物(ターゲット、獲得、囲い込みなど)のように扱われているマーケティングには恐怖感をとおり越して、嫌悪しているのではないでしょうか。
自分のこうなりたいという、スタイルに対してそれを充足してくれる欲しいものではなく、体験を重視していると考えています。それと出会う(しあわせる=幸せの語源)ために、自分との価値観が近しい友人・知人という先行体験顧客の声に、共感するのだと考えてています。また、それらの体験をトランスベアレンシーとして、ブランドオーナーと、アウアー(Our Weなど)としての共鳴するかを無意識の内に選別していると考えています。
自らを、アウアーとして、企画、生産、流通、広報にも関わりながら購買体験と態様を創っていくという存在に進化を遂げているのです。
ケーススタディ分析
*LOLA:WOMEN’S HEALTHとしてのDNVBを考える

③顧客とのコミュニケーションから生まれるコミュニティとしての資産

④業務プロセスコストの相対的な逓減
*購買後体験・開封体験・Unboxingがポイントになる理由
これまではUNIQLO:SPA(企画から販売までを一貫するモデル)スタイルやアップルような大手資本企業しかできなかったことが、DNVBスタートアップでも小規模から展開・ローンチが可能になったことも大きなファクターです。
D2Cと定義されているは別として、ファストファッションで成長を遂げている、SHEINはビジネスの運用方法については正しくデジタルネイティブでビジネスをリデザインしています。
SHEINのビジネスモデル要素を分割検証する #1
DTC(D2C) トレンドに関するよくある質問
なぜブランドは消費者に直接販売するのですか?
ブランドは DTC (D2C)を活用して、卸売小売業者やその他の流通業者などのサードパーティへの依存を取り除きます。その結果、消費者に直接販売します、これはダイレクトマーケティングの時代から続くモデルです。
中間業者を排除、無くすることで、ブランドは購買体験をよりデザインして、コミュニケーションすることでコントロールして、販売された各商品から、結果としてユニットエコノミクス的により多くの利益を得ることができます。
DTC(D2C)が普及したのはいつからですか?
リアルの実店舗とは別に商品を消費者に直接配布する方法は、何千年も前からあります。しかし、DTC (D2C)モデルは、1990 年代のドットコム バブルの間にオンライン小売業者がインターネットを通じて商品を販売し始めたときに人気を博しました。
そして、2020年のCOVID-19 のパンデミックにより店舗が一時的に閉鎖され、消費者がオンラインで購入することを余儀なくされたとき、それは爆発的に増加しました。
そして、2023年新しくモデルの変換が、OMO・オムニチャネルとして求められています。
DTC(D2C)は流行ですか?
DTC (D2C)は間違いなく一時的な流行ではありません。消費者へ直販は数千年前に始まり、e コマースの成長、経済のグローバル化、フルフィルメントの進歩により、最近は、新たな勢いを増して、モデルも変化しています。一番、わかりやすいのは、SNSでの広告のコストが変化しているために、より顧客へのデリバリーコストを低減させるための、卸小売流通との提携や、リアル体験を通じての顧客とのコミュニケーションを拡大するための、POP-UP などです。
2023年の DTC e コマース トレンドは何ですか?
2023 年の最大の DTC トレンドには、マイクロインフルエンサーパートナーシップ、十分なサービスを受けていないオーディエンスにリーチするためのニッチ化、サブスクリプションコマース モデル、オフライン ストア エクスペリエンス、バックオーダー(予約販売)などです。
*SHEINのモデルやソリューションシステムの解説はこちらから

関連コンテンツ
EC・D2C・DNVBのビジネスモデルとは?バズワードにしないために徹底比較
富士ロジテックホールディングスが提供する、フルフィルメントサービス
スタートアップから10億越えまでにするべきこと
*EC立ち上げTODOリスト無料進呈しています。
詳細はYouTubeをご覧ください。
 殿堂入り記事
殿堂入り記事
発送代行完全ガイド
発送代行に関しての基礎知識が全てわかる徹底ガイドです。発送代行サービスを検討されているEC事業者様は是非ご覧下さい。

監修者
株式会社富士ロジテックホールディングス
西間木 智 / 通販営業部 部長
物流会社で20年経験しD2C EC スタートアップから中規模、大規模のeコマース事業者へフルフィルメントサービスの提供や物流の見直し・改善、スピード配送、複数拠点展開を設計して提唱している。 事業者様の売上貢献するために 「購買体験」 「リピート施策」 「Unboxing」 やOMO対応での「オムニチャネル」 「返品交換物流」 を提案し、事業者と常に伴走して最新の物流設計を試みる。
タグ一覧
カテゴリー






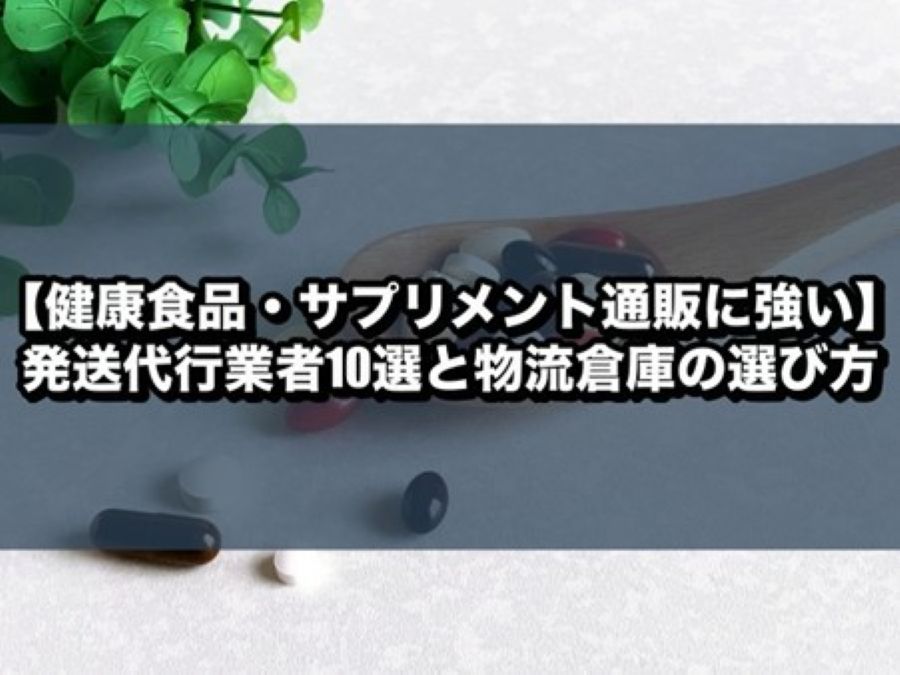
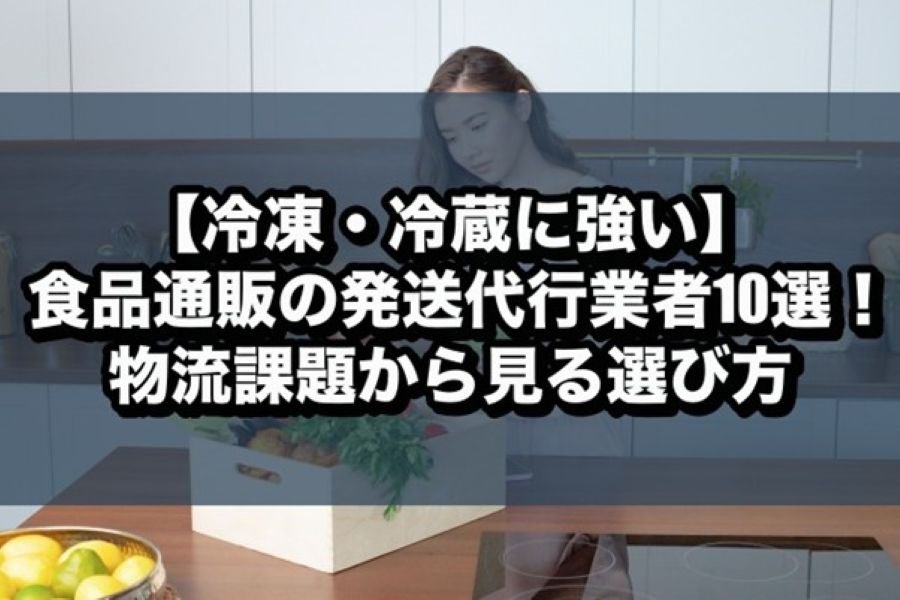

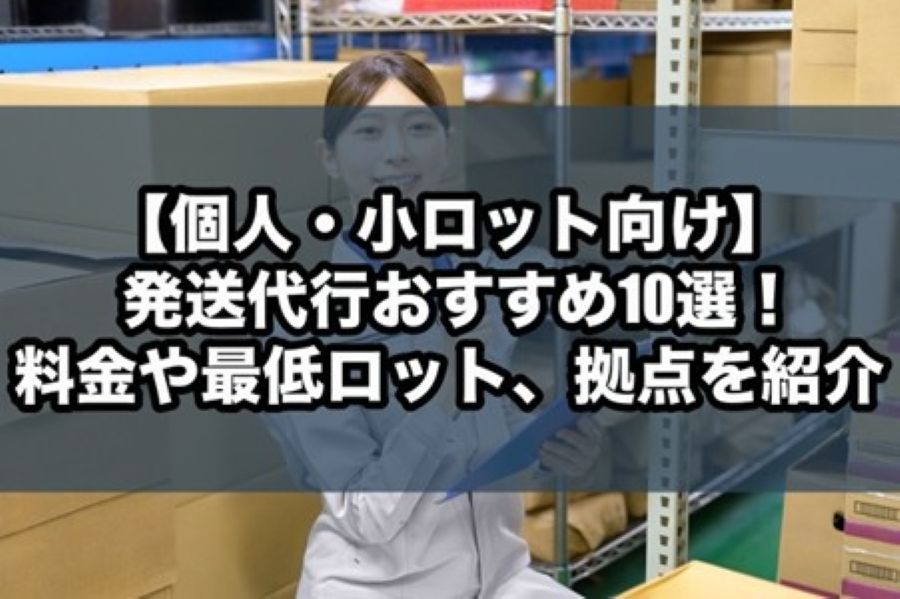
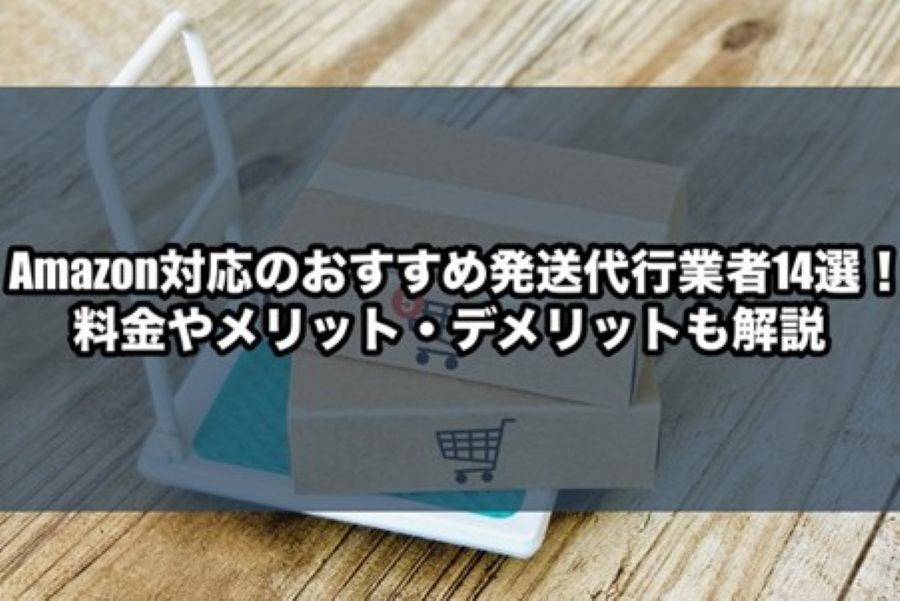
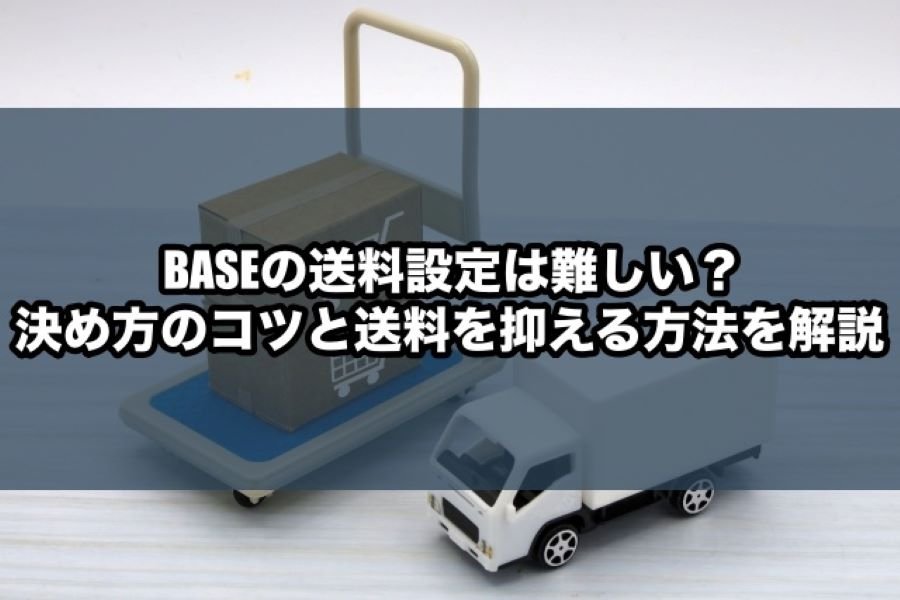
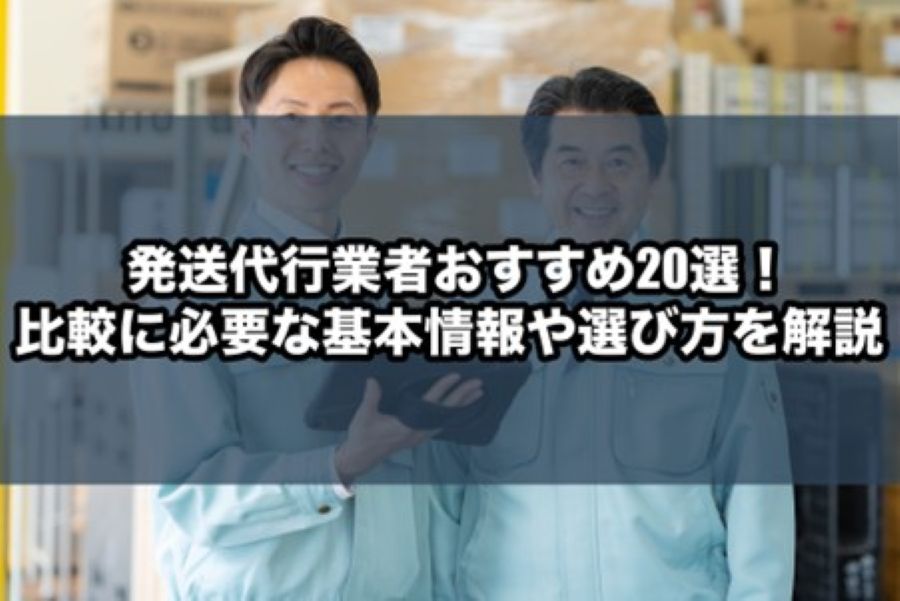








![[Yahooストアと楽天市場のEC担当者向け]ラベル取得に向けた物流攻略ガイド](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8323/5489/files/w_paper01.png?v=1738665471)